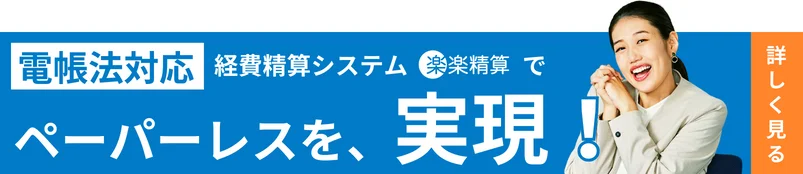支払手数料の勘定科目、間違わないための正しい使い方とは?

振込手数料やカード決済手数料、システム利用料など、日々の取引で発生する手数料は、経理処理のなかでも判断が難しい項目のひとつです。
適切な勘定科目で処理できていないと、消費税区分の誤りや、インボイス制度への対応漏れといったトラブルにもつながるおそれがあります。
この記事では支払手数料の基本的な考え方から、具体的な仕訳の例、よくある間違いや注意点までを、経理初心者にもわかるように丁寧に解説します。
迷いながら処理していた手数料を正確に扱えるようになりたい方は、ぜひ参考にしてください。
この記事の目次
支払手数料とは
経理実務において、支払手数料という勘定科目は、登場頻度の高い項目です。
ここでは、経理実務で頻繁に登場する支払手数料という勘定科目について、基本的な定義から具体的な範囲までをわかりやすく紹介します。
お金を支払うときに発生する手数料のこと
支払手数料とは、銀行やクレジットカード会社、不動産会社などに支払う手数料のことです。
たとえば、銀行で振込をする際にかかる振込手数料や、契約の仲介をしてくれた業者に支払う紹介料などが支払手数料にあたります。
こうした手数料は、取引の本体ではなく、その取引をスムーズに進めるための費用です。商品やサービスの代金とは別にかかる付随的な費用と考えるとわかりやすいでしょう。
このような手数料は、会計のうえでは「販売費および一般管理費」として扱われ、会社の経費として記録されます。
たとえば取引先に10万円を振り込むときに、手数料として550円かかった場合、以下のように処理します。
- 10万円 → 商品代金
- 550円 → 振込手数料(支払手数料として処理)
この550円は、銀行のサービスを利用するための費用であり、「支払手数料」という名前の経費として記録されます。
支払手数料に該当する費用一覧
支払手数料として処理できる費用は多岐にわたります。
正しい勘定科目で処理するためには、どのような支出が支払手数料に該当するのかをしっかりと把握しておきましょう。
| 費用の種類 | 具体例 |
|---|---|
| 銀行関連の手数料 | ・振込手数料 ・ATM利用手数料 ・外貨送金時の為替手数料 |
| 不動産関連の手数料 | ・店舗やオフィスの賃貸契約時に発生する仲介手数料 |
| 決済代行、ECサイトなどの利用料 | ・クレジットカードの決済手数料 ・ECサイト利用料 ・代引き手数料 |
| その他 | ・保証会社へ支払う信用保証料 ・解約に伴うキャンセル料 ・業務委託の紹介料 |
支払手数料は「サービスへの対価」であることがポイントです。
ただし、すべての手数料がこの勘定科目に該当するわけではありません。たとえば、不動産を購入する際に支払った仲介手数料は、取得原価の一部として資産計上し、減価償却を通じて費用化する必要があります。
判断が難しいケースもあるため、迷った場合は「事業活動の過程で必要なサービスかどうか」を基準に考えるとよいでしょう。
さらに、社内でルールを設けておくと、処理のばらつきを防ぎ、経理業務の効率化にもつながります。
支払手数料のほかにも、経理処理で使われる勘定科目にはさまざまな種類があります。ほかの勘定科目の使い分けについても詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
支払手数料の具体的な仕訳例
日々の経理業務では、支払手数料の仕訳が必要となる場面が多くありますが、実際にはどの費用をどの勘定科目で処理すればよいのかと迷うことも少なくありません。
ここでは、実務でよく発生する以下の4つのケースについて、それぞれの仕訳方法を具体的に解説します。取引内容や相手先によって適切な処理が異なるため、しっかりとポイントを押さえておきましょう。
- 金融機関にかかる手数料
- クレジットカード手数料
- 不動産や紹介業者への仲介手数料
- 保証会社への保証料
金融機関にかかる手数料
銀行振込やATMの利用、小切手の発行などにかかる手数料は、支払手数料の勘定科目を使って処理します。
金融機関にかかる手数料は、1件あたりの金額こそ小さいですが、年間を通じて合計すると大きなコストになります。手数料のなかでも、日々の取引で頻繁に発生する費用の1つともいえるでしょう。
それゆえに、企業のコストを漏れなく管理し、そして帳簿上の預金残高と実際の銀行口座の残高とを一致させるためにも、正確な勘定科目での仕訳が求められます。
仕訳例:取引先への買掛金5万円を普通預金から支払い、手数料550円が発生した場合
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 買掛金 | 50,000円 | 普通預金 | 50,550円 |
| 支払手数料 | 550円 | ||
金融機関に支払う手数料は、金額の大小にかかわらず、発生の都度、支払手数料として正確に記帳する習慣をつけましょう。
クレジットカード手数料
顧客がクレジットカードで支払った代金は、いったんカード会社を経由して入金されます。このときカード会社は、決済手数料を差し引いて振り込むのが一般的です。
差し引かれた分が、経理上の支払手数料にあたります。
仕訳例:カード売上10,000円から手数料500円を差し引いた売上金が入金された場合
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 9,500円 | 売掛金 | 10,000円 |
| 支払手数料 | 500円 | ||
仕訳例のように顧客がクレジットカード決済した場合、売上の金額は1万円であっても、実際の入金額はそれより少ないため、差額を支払手数料として費用計上します。
なお、クレジットカードの手数料は、原則非課税で処理しますが、契約内容によっては課税対象となる部分があるため、カード会社との契約書を一度確認しておくと安心です。
キャッシュレス決済は今や多くの店舗で導入されていますが、手数料の処理を正しく行うことで、売上の実態や経費の管理がより正確になります。
帳簿と入金額にズレがないよう、明細や振込通知を見ながら仕訳する習慣をつけましょう。
参考:国税庁「質疑応答事例 クレジット手数料」
不動産や紹介業者への仲介手数料
事務所や店舗を借りる際、不動産会社に支払う仲介手数料は、支払手数料として経理処理します。
ほかにも、広告代理店に支払う紹介料や、求人サービスの手数料なども、同じように仕訳されるケースが一般的です。
仕訳例:不動産会社に仲介手数料を5万円現金で支払った場合
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 支払手数料 | 50,000円 | 現金 | 50,000円 |
ただし、不動産の仲介手数料は、取引の目的によって会計処理がまったく異なります。
事務所などを借りる場合の仲介手数料は支払手数料として処理しますが、購入する場合は、仲介手数料も資産の取得価額に含めて計上します。
なぜなら、賃貸は一定期間サービスを利用するための費用であるため、支払時に経費となります。一方で、購入は長期間使用する資産を取得する行為であり、取得時にかかった費用は資産本体の価値の一部とみなされるためです。
仕訳前に契約書の内容を確認し、「借りているのか」「購入しているのか」をしっかり確認しましょう。
保証会社への保証料
賃貸契約や借入契約などで保証会社へ支払う保証料も、基本的には支払手数料で処理します。
仕訳例:融資を受けるにあたり、1年分の保証料として2万円を普通預金で支払った場合
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 支払手数料 | 20,000円 | 普通預金 | 20,000円 |
上記の仕訳例のように、契約期間が事業年度を超えない場合は、支払手数料として費用処理すれば問題ありません。
ただし、保証期間が1年を超える場合など、契約期間が事業年度を跨ぐ場合には注意が必要です。契約期間が事業年度を超える場合、事業年度を超えた分に関しては、前払費用で資産計上します。
また、複数年にわたる保証料をまとめて支払った場合も、経理上は前払費用や長期前払費用としていったん資産計上し、各会計年度に分けて費用化していく方法で仕訳します。
理由としては、保証料の金額をすべて当期の費用にしてしまうと、翌期以降の利益が不正確になってしまうことから、あくまでも費用計上は当期にかかった分だけを計上するルールとなっているためです。
仕訳例:融資を受けるにあたり、3年分の保証料として6万円を普通預金で支払った場合
支払時
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 長期前払費用 | 60,000円 | 普通預金 | 60,000円 |
決算時(6万円を3年で分割した1年分を費用計上する)
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 支払手数料 | 20,000円 | 長期前払費用 | 20,000円 |
決算時に、保証期間に対応した費用を各年度で分けて計上することで、適切な費用配分になり、財務諸表の正確性が保たれます。
また、保証料は消費税が非課税となる点も見落とさないようにしましょう。これは、保証が保険と似た性質をもつサービスとされているためです。
そのため保証料を支払う際は、「契約期間が1年を超えていないか」「消費税の扱いはどうか」の2点を必ず確認しましょう。
支払手数料と混同しやすい勘定科目
支払手数料は幅広い費用を対象とするため、実務では他の勘定科目との使い分けに迷うことが少なくありません。
しかし、費用を正しく分類することは、経営状況を正確に分析し、適切な税務申告を行うための基本です。
誤った処理はコスト構造の把握を困難にしたり、税務調査で指摘を受けたりする原因にもなります。ここでは、とくに混同しやすい以下の勘定科目との違いを、具体的な判断基準とともに解説します。
- 雑費
- 支払報酬
- 販売手数料
- 租税公課
- 支払利息
雑費
雑費は、金額が少なく、内容がはっきりしない費用を一時的に記録するための勘定科目です。たとえば、どの勘定科目にも当てはまらないような突発的な支出や、判断に迷うような小さな経費が雑費に該当します。
雑費を使いすぎると、帳簿上の費用内訳が不明確になり、経営分析が難しくなります。それだけでなく、税務調査においても「内容が不明な経費」として詳細な説明を求められる可能性が高まります。
手数料は少額であるため、雑費の勘定科目と混同しやすいですが、内容が明確で継続的に発生するような手数料であれば、支払手数料として処理するようにしましょう。
勘定科目に迷った場合は、費用の性質をよく見極め、可能な限り正しい勘定科目で処理することを心がけることが大切です。
支払報酬
弁護士や税理士、デザイナーなど、個人の専門家に仕事を依頼し報酬を支払う場合は、支払報酬という勘定科目を使います。これは、特定のスキルや専門知識に対する対価としての支出を適切に記録するための項目です。
たとえば、税理士に月額の顧問料を支払うケースでは、支払報酬で処理するのが一般的です。一方で、同じ税理士であっても、決算書作成など一時的な業務をスポットで依頼する場合には、支払手数料など別の勘定科目で処理するケースもあります。
このように、継続的な取引か単発の依頼かなど、実態に応じて社内で勘定科目の使い分けルールを設けておくことが重要です。曖昧な運用を避けるためにも、事前に経理内で判断基準を統一しておくと、業務のばらつきや確認作業の手間を減らせます。
なお、源泉徴収の要否については、勘定科目とは関係なく所得税法に基づいて判断する必要があります。たとえば、税理士報酬には原則として源泉徴収が必要ですが、処理を支払報酬とするか支払手数料とするかにかかわらず、法律上の規定を踏まえた正確な対応が求められます。
外部の専門家と頻繁に取引がある企業では、こうしたルールの明確化と運用の徹底が、経理処理の正確性や法令遵守の維持に大きく貢献します。
参考:国税庁「タックスアンサー No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」
販売手数料
販売手数料とは、商品やサービスの販売促進や販路拡大を目的として、外部のパートナーなどに支払う手数料を指します。
たとえば、以下のような支出が該当します。
- 販売代理店へのインセンティブ
- ECモールへの出品手数料(Amazon、楽天など)
- 商品を紹介してくれた業者への成果報酬(紹介料)
この販売手数料は、売上を生み出すために直接かかわる費用であり、販売活動に紐づくものです。
販売手数料は支払手数料と混同されやすいですが、これらの2つの費用の違いは「何のための費用か」という目的が異なる点です。
- 販売手数料 :売上を増やすための直接的な販促・営業活動に伴う費用
- 支払手数料:売上が発生した後の決済処理や業務遂行に伴う費用
たとえば、Amazonに商品を出品して販売した際に発生する販売手数料は、その売上を得るための費用であるため、販売手数料で処理します。
一方で、クレジットカード決済代行会社に支払う手数料は、代金を回収するための費用という位置づけとなり、支払手数料として処理します。
仕訳処理の際には、「この費用は売上を伸ばすための販促的な支出かどうか」を意識して判断すると、勘定科目の選定を誤りにくくなるでしょう。
租税公課
租税公課とは、会社が国や地方自治体などの公的機関に支払う税金や公的な手数料を処理するための勘定科目です。
代表的なものとして、以下のような費用が含まれます。
- 登録免許税
- 印紙税
- 自動車税
- 事業所税
支払手数料と租税公課の違いは支払先です。民間企業や個人に支払うものは支払手数料、公的機関に支払うものは租税公課として区別するのが基本です。
たとえば、会社設立時に法務局へ支払う登録免許税や、契約書に貼付する印紙代などは、すべて租税公課として処理します。これらはサービスの対価というよりも、法律にもとづいて支払う義務のある費用だからです。
この区別を誤ると、消費税の計算に影響を及ぼす可能性があります。なぜなら支払手数料は原則として課税対象となるのに対し、租税公課の多くは非課税または不課税に分類されるためです。
消費税申告の誤りを防ぐために、経費処理の際は「誰に対して支払ったのか」を必ず確認する習慣をつけましょう。
支払利息
支払利息とは、借入金やローンに対して支払う利息を処理するための勘定科目です。
銀行や金融機関などから資金を借りた際、その借入金に対して支払う金利は、支払利息として記録されます。これは資金調達のコストにあたるため、通常は営業外費用に分類されるためです。
支払手数料と混同しやすい点として、借入時に発生する事務手数料や保証料などが挙げられます。
たとえば、借入時に金融機関へ支払う保証料や契約事務手数料は、利息とは異なり、具体的なサービスへの対価として発生する費用です。そのため、これらは支払手数料として処理するのが原則です。
支払利息と支払手数料の主な違いは、「支払う理由」にあります。利息は時間の経過に応じて発生する金銭の対価であり、手数料はサービス提供に対する対価です。
たとえば1,000万円を借り入れ、年利3%で月に25,000円の利息を支払った場合、25,000円は支払利息として計上します。一方で、借入時に支払った50,000円の契約事務手数料は、支払手数料で計上が必要です。
支払利息と支払手数料の勘定科目を正しく使い分けることで、企業の財務活動による費用と、営業活動にかかる間接費を明確に分けられます。
とくに損益計算書における「営業利益」や「経常利益」の算出に影響するため、支出の内容を見極めて正しく処理することが重要です。
支払手数料の税区分
支払手数料にも、消費税がかかるかどうかの税区分があります。
ここでは代表的な例とともに、どのようなときに消費税がかかるのか、またはかからないのかをわかりやすく解説します。
原則「課税対象」
ほとんどの支払手数料は、消費税がかかる「課税仕入」に分類されます。
具体的な課税対象の例は、以下のとおりです。
- 銀行の振込手数料
- 仲介業者への紹介料や仲介手数料
- 広告代理店やクラウドサービス会社への利用料
上記の費用はすべて、日本国内の事業者が提供するサービスに対する対価です。そのため、消費税法の国内取引や事業者間取引、サービスの対価といった要件を満たしており、課税対象になります。
適切に課税処理することで、企業は支払った消費税額を仕入税額控除として活用でき、納付すべき消費税額を正確に計算できるため、仕訳時には税区分に注意を払いましょう。
非課税や不課税になるケース
支払手数料の多くは消費税の課税対象となりますが、すべてが課税対象とは限りません。中には「非課税」や「不課税」に該当するケースもあります。
まずは両者の違いを簡単に確認しておきましょう。
| 税区分 | 概要 | 例 |
|---|---|---|
| 非課税取引 | 本来は課税対象の性質を持ちながらも、社会政策的な理由で消費税が課されない取引 | 保険、医療、住宅の家賃など |
| 不課税取引 | そもそも消費税の対象外とされている取引 | 給与の支払い、寄付金、海外取引など |
上記の違いを踏まえ、支払手数料の中で非課税または不課税として処理される主な例を以下にまとめます。
| 税区分 | 取引例 | 概要 |
|---|---|---|
| 非課税になるケース | クレジットカードの決済手数料 | 「金銭債権の譲渡」とみなされるため、通常は非課税扱い |
| 信用保証料 | 保証という金融性質の高い取引のため | |
| 不課税になるケース | 解約に伴うキャンセル料 | ペナルティとして支払うものは対価性がないため不課税扱いとなる |
ただし、クレジットカードの決済手数料は、契約形態や提供内容によっては課税対象となる場合もあるため、契約書の確認が重要です。
参考:国税庁「タックスアンサー No.6253 キャンセル料」
支払手数料のよくある間違いと対策
支払手数料の経理処理では、科目の選び方や消費税の扱い方において、ついうっかり間違ってしまうケースが少なくありません。
ここでは、とくにありがちな3つの間違いと、それらを防ぐためのポイントを紹介します。
- 勘定科目の選択ミス
- 消費税区分の誤り
- 自動仕訳設定のミスによる誤処理
勘定科目の選択ミス
支払手数料に関するミスでよくあるのが、勘定科目の選び間違いです。
手数料という名前だけで判断して、すべてを支払手数料にまとめてしまったり、雑費や販売手数料など似たような科目で処理してしまったりするケースが多く見られます。
たとえば、以下のように処理すべき取引も、間違った科目で記録してしまうと、経費の内容があいまいになってしまうため、注意が必要です。
<正しい仕訳の例>
- 銀行の振込手数料:支払手数料
- 弁護士への報酬(源泉徴収あり):支払報酬
- ECサイト中での販売手数料:販売手数料
上記のように、費用の内容や支払先の業種によって、適切な勘定科目は変わります。
対策ポイントとしては、次の2点を意識することで、勘定科目の選択ミスを防ぎやすくなります。
| 費用の目的 | 何のために発生した手数料か? |
|---|---|
| 支払先の種類 | 相手は銀行なのか、士業なのか、ECサイトのような取引先なのか? |
雑費は、分類が難しい費用を処理する際に便利な科目ですが、むやみに雑費に入れてしまうのはNGです。
後から集計や経費分析をする際に、費用の内容がわからなくなってしまうため、明確に分類できない場合の最後の選択肢として使うようにしましょう。
消費税区分の誤り
支払手数料でよくある間違いのひとつが、消費税の「課税・非課税・不課税」の区分ミスです。
同じ手数料でも、「誰に支払ったのか」「何のサービスか」など、取引の相手や内容によって税区分が異なります。
| 取引内容 | 税区分 | 具体例 |
|---|---|---|
| 行政機関への支払い | 非課税 | 住民票・登記簿謄本の取得手数料など |
| 海外取引に関する支払い | 不課税 | 現地空港での航空券発行手数料、海外支社設立にあたり現地業者に支払った紹介料など |
| 国内の民間事業者への支払い | 課税対象 | 銀行振込手数料、仲介業者への紹介手数料など |
ただし、国内の民間事業者への支払いであっても、クレジットカード決済手数料のように、非課税の規定が適用される取引には注意が必要です。
クレジットカード会社への決済手数料は、契約内容によって税区分が変わることがあります。
たとえば、「金銭債権の譲渡」として扱われる場合は非課税となるケースもあるため、契約書や請求書に記載された消費税の有無を必ず確認しましょう。
帳簿の信頼性にもかかわるため、取引のたびに税区分を見直し、慎重に処理する習慣をつけることが重要です。
自動仕訳設定のミスによる誤処理
クラウド会計ソフトや経費精算ソフトには、銀行明細やカード明細を自動で読み取り、仕訳を自動登録してくれる便利な機能があります。
しかし、初期設定のまま使い続けると、誤った勘定科目や消費税区分で処理されてしまうケースもあるため、ソフトを導入した際には注意が必要です。
<よくある間違い例>
- 〇〇銀行からの引き落としをすべて支払手数料として処理していたが、実際はローンの元本返済も含まれていた
- クレジットカードの決済手数料を、ある月は課税、別の月は非課税で処理してしまった結果、AIが誤学習してしまった
上記のようなミスは、経費の分類ミスだけでなく、消費税の仕入税額控除や財務数値の誤差にもつながります。
自動仕訳機能は便利ですが、誤ったままの情報を放置していたり、設定ミスがあったりすると、正確な帳簿にならないリスクがあります。
そのため、以下の対策を講じて、誤処理を防ぐようにしましょう。
| 対策 | 具体例 |
|---|---|
| 初期設定の自動仕訳ルールを必ず見直す | 勘定科目・税区分が合っているか、実際の取引内容に即しているか確認する |
| 毎月の締め時に「手数料関連の仕訳」だけ抽出してチェック | 仕訳帳や明細から、該当項目だけをフィルタする |
| 同じ取引先でも内容が異なる場合は、「摘要」や「ラベル」で区別する | 「○○銀行(振込手数料)」と「○○銀行(ローン返済)」など |
| 一貫性のある処理ルールをチーム内で共有する | 担当者が変わっても、AIが誤学習しないように処理基準を統一する |
AIや自動仕訳はあくまで補助的なツールです。人の目による確認や見直しを定期的に行うことで、ミスの予防と帳簿の精度向上につながります。
支払手数料の仕訳をさらにラクにする方法
支払手数料の仕訳は細かくて面倒そうと感じている方もいるのではないでしょうか。
面倒に感じる支払手数料の仕訳も、社内のルールを整えたり、ツールを活用したりすることで、手間をぐっと減らせます。
ここでは、仕訳作業を効率化する3つの方法をご紹介します。
- 社内ルールと業務フローの見直し
- 定型的な仕訳業務はアウトソーシング
- 経費精算システムの導入で自動化
社内ルールと業務フローの見直し
支払手数料の仕訳ミスは、社内で統一された処理ルールがないことが原因で起こるケースが多く見られます。
たとえば銀行振込手数料を雑費で処理したり、紹介料を支払報酬として処理してしまったりと、担当者ごとに判断が異なると、帳簿の整合性が取れなくなってしまいます。
そこで重要なのが、勘定科目の使い分けルールや申請・承認フローを文書化することです。
- 手数料の種類別マニュアルを作成し、誰でも判断できるようにする
- 承認ステップを簡素化し、経理部で最終チェックできるように設計する
- 担当者の引継ぎ時にも迷いが出ないよう、業務マニュアルを定期的に見直すグループ会社・拠点ごとの運用ルールを統一し、グループ全体での整合性を確保する
社内ルールと業務フローの見直しは、経理業務の属人化を防ぎ、誰が担当しても同じ処理ができる仕組み作りが大切です。
定型的な仕訳業務はアウトソーシング
毎月必ず発生するようなルーティンワークは外注(記帳代行)で大幅な省力化が可能です。
たとえば、以下のようなケースでは外注が有効です。
- 仕入先への定期的な支払いと、それにともなう銀行振込手数料の仕訳
- クレジットカード決済による売上入金とそれにともなう手数料の処理
- Amazon・楽天などを通じた売上入金と、販売手数料や決済手数料の差引処理
- 外部パートナーや業務委託先への月額報酬とその送金手数料の処理
- 顧問税理士・社労士・弁護士への定額顧問料
- 交通費や通信費などの定期経費
これらは取引内容が定まっているため、あらかじめルールを決めて外注先に渡しておけば、正確かつスピーディーに処理してもらえます。
なお、外注を活用するメリットは、以下のとおりです。
- 担当者の負荷軽減と人的ミスの削減
- 処理スピードと会計データの正確性向上
- 経理のスキルやリソースが足りない中小企業にも有効
仕訳業務をアウトソーシングする際は、コストと効果を比較しながら、外注範囲を見極めるのがポイントです。
定型的な経理業務を外注することで、大幅な効率化と精度の向上が期待できます。
「実際にどこまで外注できるのか」「依頼する際の注意点は?」といった詳しい内容は、こちらの記事でわかりやすく解説しています。
関連記事:経費精算をアウトソーシングするメリットは?経理の負担を軽減する方法
経費精算システムの導入で自動化
経費精算システムを導入することで、領収書の管理・手入力・仕訳作業を一気に効率化できます。
とくにAI-OCR(画像読み取り機能)付きのツールであれば、紙の領収書をスマホで撮るだけで、日付・金額・取引先などが自動で読み取られ、仕訳も半自動で作成されます。
経費精算システムを導入するメリットは、以下のとおりです。
- 手書き・エクセル管理から脱却し、入力ミスや漏れを防止できる
- 経費精算から会計連携までの一連の流れを自動化できる
- 社員からの経費申請の手間も削減し、経理だけでなく全社的に業務改善を期待できる
- インボイス制度対応済みのツールを使えば、仕入税額控除のチェックもラクになる
ただしシステム導入時には、次の点に注意しましょう。
- 初期設定(勘定科目、税区分、部門など)をしっかり行う
- 経費ルールをシステムに反映させる(申請金額上限、用途制限など)
- 従業員への研修やマニュアルを整備する
経費精算システムを導入することで、仕訳ミスの防止だけでなく、経費全体の見える化にもつながります。人的リソースが限られている企業ほど、ツールの導入は有効的です。
経費精算システムの導入には多くのメリットがありますが、実際にどれほどの業務改善が見込まれるのか気になる方も多いでしょう。
具体的な導入効果や活用ポイントについては、以下の記事で詳しく解説しています。
「楽楽精算」で仕訳業務を効率化
振込手数料やカード決済手数料など、支払手数料の処理には意外と多くの手間がかかります。
「楽楽精算」を活用すれば、経費精算から仕訳作成、会計ソフトとの連携まで一元化でき、担当者の業務負担を大幅に削減できます。
たとえば領収書をスマートフォンで撮影するだけで、AIが自動で金額や日付を読み取り、あらかじめ設定したルールにしたがって勘定科目や税区分まで正しく仕訳されます。
振込手数料は事前に「支払手数料/課税」で設定しておけば、申請時に自動でその内容が反映され、入力ミスを防げます。
さらに、2023年にスタートしたインボイス制度にも対応しており、仕入税額控除の条件を満たす記録や登録番号の管理もスムーズです。
仕訳データは、主要な会計ソフトに直接連携可能なため、手入力や二重処理のリスクもなくなります。
支払手数料の仕訳や経費精算にかかる手間を削減したい方は、まずは資料をご覧ください。導入メリットや機能が詳しくわかる資料を以下より無料でダウンロードいただけます。
「楽楽精算」の
資料をメールでもらう

電子帳簿保存法対応!経費精算システム「楽楽精算」の製品概要や導入メリット、機能などが詳しくわかる資料をメールでお送りします。
この記事を読んだ方におすすめ!
オススメの人気記事
記事執筆者紹介

「楽楽精算」コラム編集部です。
経理担当者様の日々の業務にプラスとなるお役立ち情報
「楽楽精算」最新情報をお届けしていきます!
使い勝手が気になる方へ。