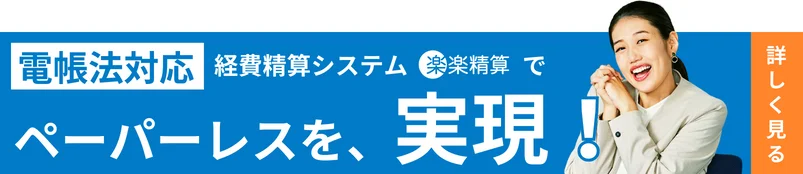【2025年最新版】実務で使える勘定科目一覧と仕訳ミスがなくなる基本ルール

勘定科目の種類が多すぎて、どれを使ったらよいのかわからない、そのようなお悩みをお持ちの方もいるのではないでしょうか。
勘定科目の適切な使用は、お金の流れを把握するためだけではなく、適切な経営判断をするためにも重要な情報源となります。
本記事では勘定科目の基本から、実務でよく使う科目や仕訳例、迷ったときの選び方、さらに経費管理に役立つ補助科目の活用法までをわかりやすく解説します。
勘定科目の選び方に不安がある方や、これから経理業務をはじめる方は、本記事を参考にして、仕訳の理解を深めていきましょう。
この記事の目次
勘定科目とは
はじめに、会計や経理の基本となる勘定科目について、わかりやすく解説します。
お金の出入りを分類するための項目である
勘定科目とは、「何にお金を使ったのか」「どこからお金が入ってきているのか」が一目でわかるように、取引の内容を記録・管理するための「分類名」のことです。
企業では、日々さまざまな取引が行われ、お金が出入りしています。
たとえば「売上が発生した」「交通費を使った」「事務用品を買った」といった取引を、それぞれ「売上」「旅費交通費」「消耗品費」などの科目に分けて帳簿に記録します。
家計簿で言えば、「食費」「光熱費」「交際費」といった分類に似たイメージです。
勘定科目を用いて取引内容を記録や管理することで、どのような目的でお金が動いたのかについて、後からでも一目でわかるようになります。
「どのような取引のときに、どの勘定科目を使うか」については明確な規定があるわけではなく、企業や使っている会計ソフトによって異なります。
ただし、一度使う勘定科目を決めたら、以後の同じ取引は同じ勘定科目を使って記録するのが仕訳の基本です。
勘定科目は大きく5つに分類される
勘定科目は、大きく分けて以下の5つのカテゴリに分類されます。
| カテゴリ | 概要 |
|---|---|
| 資産 | 会社が持っている経済的価値のあるお金やモノ |
| 負債 | 会社が将来支払う義務のある債務 |
| 純資産 | 出資や利益など会社の元手部分 |
| 収益 | 企業の活動によって得られた収入 |
| 費用 | 収益を得るためにかかったコスト |
上記の5つの分類は、会社の財政状態や経営の成果を整理するための基本的な分類です。
資産や負債、純資産は貸借対照表に表示され、会社が今どのような財産や借金を持っているかがわかります。一方で、収益と費用は損益計算書に表示され、売上や経費など、会社がどれだけ儲けたかを把握するために用いられます。
この5つの分類を理解すれば、どの科目に仕訳すべきかが判断しやすくなり、仕訳作業の効率化だけでなく、財務状況の把握もしやすくなります。
また、自社でよく使う勘定科目を分類ごとにまとめた勘定科目一覧表を作っておくと、仕訳作業がスムーズになり、ミスも防ぎやすくなります。
代表的な勘定科目一覧
ここからは、資産・負債・純資産・収益・費用という5つの分類ごとに、実務でよく使われる勘定科目を紹介していきます。
資産に関する勘定科目
資産とは、企業が保有する現金やモノ、将来的に受け取る権利など、会社の財産にあたるものを指します。たとえば「現金」や「売掛金」など、日々の取引でよく使われる項目もこの分類に含まれます。
資産の具体的な勘定科目例は、以下のとおりです。
| 勘定科目 | 概要 |
|---|---|
| 現金 | 硬貨や紙幣のほか、他人が振り出した小切手や郵便為替証書、配当金領収書なども現金として扱われる |
| 有価証券 | 企業が売買目的で所有している株式や国債、社債、投資信託といった金融商品 |
| 売掛金 | 取引先に掛け売りした商品やサービスの代金を受け取る権利 |
| 原材料 | 製品を製造するために仕入れた材料や部品、燃料など |
| 仕掛品 | 原材料を製品に加工している途中のまだ完成していない製品 |
| 商品 | 販売目的で仕入れた品。倉庫に保管している在庫だけでなく、店頭に並んでいるものも含む |
| 建物 | 企業が所有している店舗や事務所などの建造物。借りているオフィスや店舗などは、建物は含まれない |
| 車両運搬具 | 企業が所有する乗用車やトラック、バイクなど |
上記はすべて、企業の「資産の増減」に関わる取引に使われる勘定科目です。
負債に関する勘定科目
負債とは、いずれ返済しなければならない会社の借金などのことです。金融機関からの借入金や、商品・サービスを後払いで受け取った際の未払い金などが該当します。
負債の具体的な勘定科目例は、以下のとおりです。
| 勘定科目 | 概要 |
|---|---|
| 買掛金 | 取引先から掛けで商品やサービスを購入した際の未払金 |
| 短期借入金 | 金融機関から借りたお金のうち、1年以内に返済しなければいけないもの |
| 長期借入金 | 金融機関から借りたお金のうち、1年を超える長期間で返済しなければいけないもの |
| 未払金 | 事務所の家賃や水道光熱費など、本業の取引以外で発生したお金のうち、料金は確定しているけれどまだ支払っていないもの |
負債科目を正しく使うことで、会社の返済義務や未払状況が明確になり、財務の信頼性向上にもつながります。
純資産に関する勘定科目
純資産は「資産-負債」で算出される、会社が本当に保有している純粋な資産のことです。
出資者からの資金や、企業が積み立てた利益などが含まれます。
資産総額より負債総額のほうが大きければ、純資産の値がマイナスになることもあります。
純資産の具体的な勘定科目例は、以下のとおりです。
| 勘定科目 | 概要 |
|---|---|
| 資本金 | 株主などの出資者が企業に払い込んだお金と、事業主が準備したお金をもとに設定された金額 |
| 資本準備金 | 出資者から払い込まれたお金のうち、資本金に入れなかった分の累積額 |
| 利益準備金 | 企業が蓄えた利益のうち、会社法で積み立てが義務づけられているお金 |
| 自己株式 | 企業が自分で保有している自社の株式 |
上記の勘定科目は、企業の財務基盤や健全性を判断する重要な指標となります。
収益に関する勘定科目
収益は、企業が得た利益を指します。ただし、売上などの本業からの収益だけでなく、補助金や利息収入といった本業以外の利益も収益に含まれる点に注意が必要です。
収益の具体的な勘定科目例は、以下のとおりです。
| 勘定科目 | 概要 |
|---|---|
| 売上 | 商品やサービスの販売など、会社の本業によって得た収益 |
| 雑収入 | 補助金や手数料収入など、企業が本業以外の活動から得た収益 |
| 受取利息 | 預貯金や貸付金、有価証券などの利息として受け取った分 |
上記はすべて、損益計算書に記載され、企業の経営成績をあらわす重要な項目です。収益科目を正しく分類・記録することで、利益の構成を把握でき、経営判断にもつながります。
費用に関する勘定科目
費用は、仕入や外注など、企業が営業活動を行って利益を得るために使われるお金のことです。
費用の具体的な勘定科目例は、以下のとおりです。
| 勘定科目 | 概要 |
|---|---|
| 仕入 | 商品や原材料の購入代金 |
| 租税公課 | 事業税や自動車税、事業用の不動産にかかる固定資産税などの税金や、営業上、加盟が必要な商工会の会費 (法人税・法人住民税・法人事業税や延滞税・交通反則金などは、会計上は費用として計上しますが、税金の計算上は経費として認められません。そのため、税務申告の際に調整が必要) |
| 消耗品 | ペンやコピー用紙といった事務用品をはじめ、使用期間が1年未満か10万円未満の電化製品・家具など |
| 福利厚生費 | 残業した社員の食事代や慰安を目的とした社員旅行の費用、健康診断の費用など、従業員が働きやすい環境を整えるために使ったお金 |
| 給与手当 | 従業員に支払う給与や賞与、役職手当など |
| 接待交際費 | 得意先の接待に使ったお金や会社訪問の際の土産代のほか、お中元やお歳暮といった贈答品代 |
| 宣伝広告費 | チラシや広告、テレビCMなど、企業自身や商品・サービスを宣伝するために使ったお金 |
| 地代家賃 | 事務所や店舗、倉庫などの賃料、駐車場の利用料 |
| 旅費交通費 | 得意先への訪問や出張など、業務を行ううえで発生した移動に使ったお金 |
| 通信費 | 電話や郵便、インターネット、バイク便など、モノや情報などの通信に使ったお金 (商品の発送・購入時の送料は除く) |
| 減価償却費 | 高額な資産(例:機械、設備など)を複数年にわたって費用計上する際の分割費用 |
通信費と間違いやすいのが、商品の発送・購入時の送料です。発送時の送料は「荷造運賃」や「発送費」といった勘定科目を使い、購入時の送料は、仕入であれば「仕入」、家具などであれば「消耗品」に分類するのが一般的となっています。
上記のように、費用をきちんと分けて記録しておくことで、会社が何にどれだけお金を使っているかが一目でわかるようになり、経費の管理や税金の処理もスムーズに進められます。
よく使われる勘定科目の仕訳例
「この取引、どの勘定科目で処理すればよい?」と迷うことは、経理初心者の方にとって少なくありません。とくに実務でよく使われる勘定科目については、基本的な仕訳パターンを覚えておくことで、日々の処理がグッと楽になります。
ここでは、勘定科目の5分類ごとに、実務で多用される仕訳例を厳選して紹介します。
資産の仕訳例
資産の仕訳は、会社が持っているお金やモノが増えたり減ったりしたときに用いる勘定科目です。
たとえば、売上代金を現金で受け取った場合は現金が増加したとして処理し、備品を購入した場合は資産が増加し、同時に現金が減少したとして仕訳します。
資産は、基本的に「増えたときは借方(左)」「減ったときは貸方(右)」に記録するのが原則です。このルールを押さえておくと、仕訳の判断がスムーズになるため、覚えておきましょう。
以下で具体的な例を紹介します。
例:売上30万円を現金で受け取った場合
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 現金 | 300,000 円 | 売上 | 300,000 円 |
現金が増えたので「借方」に計上し、売上の発生で「貸方」にも記録します。
例:50万円の商品を掛けで販売した場合
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 売掛金 | 500,000 円 | 売上 | 500,000 円 |
実際の現金はまだ受け取っていませんが、代金を請求できる権利(売掛金)が発生します。
例:後日取引先から売掛金50万円を現金で回収した場合
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 現金 | 500,000 円 | 売掛金 | 500,000 円 |
売掛金が減り、現金が増えたという処理になります。
例:業務用パソコン20万円を現金で購入した場合
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 工具器具備品 | 200,000 円 | 現金 | 200,000 円 |
固定資産の増加と、現金の減少を記録します。
例:決算時に減価償却費5万円を計上する場合(耐用年数にもとづく)
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 50,000 円 | 工具器具備品減価償却累計額 | 50,000 円 |
固定資産の価値が少しずつ減っていく分を費用として計上します。
負債の仕訳例
負債の仕訳では、「会社があとで払わなければならないお金」に関係する取引を記録します。たとえば、商品を買って代金を後払いにする買掛金や、銀行からお金を借りたときの借入金などが代表的な例です。
負債は、基本的に「増えたときは貸方(右)」「減ったときは借方(左)」に記録するのが原則であり、資産の増減とは逆になるため、混乱しないように注意しましょう。
また、負債の仕訳では支払期限と金額を正確に記録し、支払い漏れを防ぐことが重要です。
以下で具体的な例を紹介します。
例:仕入先から商品40万円を掛けで購入し、後日、買掛金を銀行振込で支払った場合
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 仕入 | 400,000 円 | 買掛金 | 400,000 円 |
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 買掛金 | 400,000 円 | 預金 | 400,000 円 |
仕入れた時点で買掛金が発生し、支払い時に買掛金が減ります。
例:銀行から500万円を1年以内の返済条件で借り、借入金を返済したとき(※利息を含まない場合)
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 5,000,000 円 | 短期借入金 | 5,000,000 円 |
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 短期借入金 | 5,000,000 円 | 普通預金 | 5,000,000 円 |
借入時は負債の増加、返済時は減少として処理します。
例:オフィスの家具5万円を後払いで購入、翌月に銀行振込で支払った場合
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 消耗品費 | 50,000 円 | 未払金 | 50,000 円 |
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 未払金 | 50,000 円 | 消耗品費 | 50,000 円 |
本業以外の支払いで、後払いになっている費用は未払金で処理します。
純資産の仕訳例
純資産の仕訳は、会社が実際に持っている自分のお金(自己資本)がどう変化したかを記録するものです。たとえば、新たに資本金を受け取ったときや、利益が積み上がったときなどが該当します。
原則として、純資産が増えたら貸方(右)、減ったら借方(左)に記録するのが、基本ルールです。
資本金の変動は、会社の財務基盤を示す重要な要素であり、利益剰余金の増減は会社がどれだけ利益を積み重ねてきたかを表します。これらの動きを正しく仕訳することで、企業の財務状態を的確に把握できるようになるため、経営判断の大切な要素といえるでしょう。
以下で具体的な例を紹介します。
例:新たに出資を受けて資本金200万円を受け取った場合
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 2,000,000 円 | 資本金 | 2,000,000 円 |
会社の資産(預金)が増えると同時に、純資産(資本金)も増加します。
例:決算で当期純利益100万円が出た場合
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 損益 | 1.000,000 円 | 繰越利益剰余金 | 1,000,000 円 |
会社が出した利益は、そのまま内部に蓄積され「利益剰余金」として処理されます。
収益に関する仕訳例
収益の仕訳は、会社がサービスの提供や商品販売などの事業活動を通じて得た収入を記録するものです。たとえば、商品を販売して代金を受け取ったときや、銀行預金の利息を受け取ったときなどが収益に該当します。
仕訳の基本ルールとして、収益が発生したときは貸方(右)に記録し、返金や取消などで減ったときは借方(左)に記録するのが原則です。
売上計上は、商品の引渡しやサービスの提供が完了した時点で行う必要があり、請求書の発行日や掛取引の入金日などではありません。
売上が発生した事実にもとづいて正確に記録することが、健全な会計処理の基本となるため、売上計上のタイミングには注意しましょう。
また、売上の計上漏れがないように、請求書・納品書・売上台帳の定期的な照合が重要です。
以下で具体的な例を紹介します。
例:商品を現金60万円で販売した場合
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 現金 | 600,000 円 | 売上 | 600,000 円 |
例:商品を掛けで80万円販売した場合
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 売掛金 | 800,000 円 | 売上 | 800,000 円 |
商品やサービスを販売した収入は売上で記録し、現金か掛けかで借方の科目が変わります。
例:普通預金についた利息5千円を受け取った場合
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 5,000 円 | 受取利息 | 5,000 円 |
銀行からの利息収入や貸付金利息は、受取利息で処理します。
例:不要になった資材を2万円で売却した場合(本業以外からの収入)
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 現金 | 20,000 円 | 雑収入 | 20,000 円 |
雑収入の勘定科目は、不定期な収入や事業の本筋とは関係のない収入があったときに使います。後から何の収入であったかわかるように、摘要欄などを用いて内容を記録しておきましょう。
費用に関する仕訳例
費用の仕訳は、事業活動を行ううえでかかった支出を記録するためのものです。たとえば、商品の仕入や家賃、従業員の給料や備品の購入などが対象になります。
会計処理上の基本ルールとして、費用が発生したときは借方(左側)に記録し、その支払い元(現金や預金など)は貸方(右側)に記録しましょう。
費用は、5つの分類の中でも勘定科目が多岐にわたり、さらに選択ミスが起こりやすい区分です。
たとえば「交際費と会議費」「消耗品と固定資産」など、税務上の取り扱いがわかれるものは、区分を間違えると経費として認められないおそれがあります。
とくに高額な備品や設備を購入した場合は、消耗品費ではなく固定資産として処理し、減価償却費として複数年にわたって費用化する必要があります。
このように、勘定科目の選択ミスにより、正しい税務申告ができない場合や、経費状況の把握が困難になるケースもあるので、仕訳の際、勘定科目は慎重に選ぶようにしましょう。
以下で具体的な例を紹介します。
例:商品を現金45万円で仕入した場合
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 仕入 | 450,000 円 | 現金 | 450,000 円 |
例:従業員の給与35万円を普通預金から支払いした場合
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 給与手当 | 350,000 円 | 普通預金 | 350,000 円 |
例:事務所家賃15万円を普通預金から支払いした場合
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 地代家賃 | 150,000 円 | 普通預金 | 150,000 円 |
例:取引先との会食費8,000円を現金で支払いした場合
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 接待交際費 | 8,000 円 | 現金 | 8,000 円 |
なお、領収書や請求書などの証憑書類は、法律で定められた期間保存する義務があります。とくに2024年1月からは、メールやWebサイトからダウンロードした請求書などの電子データは、原則として電子データのまま保存することが義務化されました。
紙に印刷しての保存は認められないため、データの保管方法には十分注意しましょう。
費用は、他にも多数の勘定科目が存在するため、一例を以下の記事で紹介しています。是非参考にしてみてください。
関連記事:
タクシー代を仕訳する際の主な勘定科目は?仕訳例や損金算入の注意点
香典の勘定科目とは?仕訳方法や経費計上のポイント、注意点
勘定科目「通信費」とは?該当する経費や仕訳の例、注意点について
勘定科目を選ぶ際の5つのポイント
勘定科目は、取引の内容を記録するうえで欠かせない分類名のようなものです。
正しい科目を選ぶことで、帳簿がわかりやすくなり、税務申告や経営判断もしやすくなります。
ここでは、科目選びで迷わないための5つの基本ポイントを、わかりやすく解説します。
- お金の動きを整理する
- 会計ソフトの科目を参考にする
- わかりやすい項目名を使う
- 同じような取引は同じ科目で統一する
- 未確定の取引は仮科目で一時的に処理する
お金の動きを整理する
はじめに確認すべきなのは、会社におけるお金の動きです。
たとえば、以下のように何が増えて何が減ったのか、何のために動いたのかを整理することで、適切な勘定科目が明確になります。
| 商品を売って現金を受け取った | 現金(資産の増加)+売上(収益の発生) |
| 備品を購入した | 消耗品費(費用の発生)+現金(資産の減少) |
このように、取引の実態を把握することが仕訳ミスを防ぐ第一歩です。
会計ソフトの科目を参考にする
勘定科目をどう設定するか迷ったときは、会計ソフトにあらかじめ用意されている、標準の科目を参考にしてみましょう。
多くの会計ソフトでは、業種や業態に合わせたテンプレートが用意されており、実務でよく使われる科目が最初から設定されています。
標準的な勘定科目を参考にするメリットは、誰が見ても何に対する取引かがひと目でわかることです。
たとえば、交通費=旅費交通費、広告=広告宣伝費、といったように、会計ではある程度この費用ならこの科目という共通認識ができあがっています。
そのため、会計ソフトの科目を参考にして仕訳を行えば、社内のほかのメンバーが帳簿を見ても内容が一目瞭然になり、税理士などともやり取りがスムーズになるでしょう。
わかりやすい項目名を使う
勘定科目は、誰が見ても意味が伝わる名称にすることが大切です。「SNS広告費」や「サブスク利用料」といった、担当者にしかわかりにくい名前は避けましょう。
勘定科目の選択は、仕訳した人以外にも内容が伝わることが大前提です。
- SNS広告費:宣伝広告費の勘定科目を使用し、備考欄にSNS広告と記載
- サブスク利用料:通信費または支払手数料を利用し、備考欄に内容を記載
雑費やその他経費など、曖昧な名称も避け、数年後に見返しても理解できる項目名にしましょう。
同じような取引は同じ科目で統一する
同じ内容の支出を毎回違う科目で処理してしまうと、帳簿が煩雑になり、分析しにくくなります。
経理処理には継続性が重要です。社内で勘定科目の使い方を統一するルールを作り、同じような取引は同じ科目で処理しましょう。
税務上で注意が必要な項目は、用途や金額に応じて分ける必要がありますが、基本的には過去の類似取引を参考にして処理を統一するのがベストです。
未確定の取引は仮科目で一時的に処理する
取引内容がまだ確定していない、どの科目に分類すべきか判断がつかない場合は、仮払金や未払金などの仮科目を一時的に使う方法があります。
仮科目を使うことにより記帳の遅れを防ぎ、後から正しい勘定科目に振り替えることが可能です。
仮科目の具体的な使用例は、以下のとおりです。
| ケース | 対応方法 |
|---|---|
| 会食費が交際費か広告宣伝費か迷った場合 | 一旦仮払金で処理し、後から用途確認の上振替 |
| クレジットカード明細の詳細が不明な場合 | 月末締めで未払金に計上し、明細確認後に振替 |
ただし、仮科目を使用した場合は、長期間そのまま放置してしまうと使途不明金と判断されるおそれがあるため、定期的に精算・見直しを行いましょう。
補助科目の活用で経費管理を最適化
勘定科目だけでは把握しきれない経費の使途や内訳を明確にするには、補助科目の活用が効果的です。
ここからは補助科目とは何か、どのように設定しどのような場面で活用できるのかを具体例を交えて解説します。
補助科目とは
補助科目は、勘定科目をさらに細かく分類する内訳用の科目です。
たとえば、広告宣伝費という科目だけでは、具体的な使用状況を把握することが困難です。しかし、Web広告やチラシ印刷、テレビCMといった補助科目を設けると、どの媒体に費用を使ったかがすぐにわかります。
内訳を明確にすることにより、「どの部門が」「何に」「いくら使っているか」を正確に把握でき、効果的なコスト管理と経営判断が可能になります。
補助科目の導入を検討する際は、まず現在の経費でさらに詳しく知りたい項目を特定しましょう。とくに複数の用途が混在している科目からはじめると、効果を実感しやすく、補助科目の運用にスムーズに慣れます。
補助科目の活用方法
補助科目は、勘定科目の内訳をさらに細かく分類して管理するための項目であり、具体的には、以下のような活用例があります。
- 用途別に分類
- 部門別に分類
- 媒体やプロジェクト別に分類
- 取引先や預金口座別に分類
- 値引きや返品の内訳把握
同じ勘定科目でも使い道が異なる場合は、用途別に補助科目を設けることで、それぞれの支出の目的を明確にできます。
| 勘定科目 | 補助科目 |
|---|---|
| 旅費交通費 | 出張費、通勤交通費、研修交通費 |
| 通信費 | 電話代、インターネット利用料、切手代 |
| 租税公課 | 消費税、事業税、印紙税、固定資産税 |
| 支払手数料 | 銀行振込手数料、決済サービス利用料 |
「部門別」での補助科目の設定は、部署ごとのコスト管理や予算管理に有効的です。
| 勘定科目 | 補助科目 |
|---|---|
| 消耗品費 | 営業部、総務部、開発部 |
マーケティング活動やイベント施策など、目的が多岐にわたる場合は「媒体別」や「プロジェクト別」で分類すると、費用対効果の分析が容易になります。
| 勘定科目 | 補助科目 |
|---|---|
| 宣伝広告費 | SNS広告、チラシ印刷、〇〇展示会出展 |
売掛金・買掛金や預金残高を取引先や口座単位で把握したい場合にも、補助科目の活用が有効です。
| 勘定科目 | 補助科目 |
|---|---|
| 普通預金 | 〇〇銀行本店口座、△△信用金庫口座 |
| 売掛金 | A社、B社、C社 |
売上や仕入の値引き・返品など、通常の処理では目立たないマイナス要素も、補助科目で分類すれば把握しやすくなります。
| 勘定科目 | 補助科目 |
|---|---|
| 売上 | 売上値引き、返品分 |
| 仕入 | 仕入値引き、返品処理 |
補助科目は最初からすべての勘定科目に設定する必要はありません。「金額が大きい」「内訳を詳しく把握したい」項目から段階的に導入するのがおすすめです。
補助科目を活用するメリット
補助科目を導入することで、日々の経理業務から経営判断まで役立つ、以下のようなメリットが得られます。
- 経費の内訳が明確になり支出の偏りや無駄を早期発見できる
- 部門ごとの比較や分析に役立つ
- 決算書の信頼性が向上する
- 経営判断にとって非常に価値の高い情報源となる
このように、日々の経理処理が将来の経営戦略にも活かせるのが、補助科目活用の大きな魅力です。
補助科目を導入する際の注意点
補助科目は、費用の内訳が明確になる、経営戦略にも有効的であるというメリットがあります。一方で、導入の際は以下の点に注意しましょう。
- 細かくしすぎると管理が大変になるため、作りすぎに注意する
- 科目名や使い方がバラバラになるのを防ぐために社内ルールを統一する
- 誰が見ても内容の伝わるわかりやすい名称をつける
- 使用頻度の低い補助科目は削除や統合するなど定期的に見直す
運用の目安としては、まず大きな科目に導入し、定期的に使用状況をチェックしながら徐々に拡大することが効果的です。
定期的な勘定科目と仕訳のチェックが重要
定期的に勘定科目や仕訳を見直すことは、正確な帳簿づくりや経営の意思決定に欠かせません。最初に科目を設定したら終わりではなく、日々の取引や事業内容の変化に応じて、定期的に確認する習慣をつけましょう。
仕訳ミスや勘定科目の使い方のブレは、少しずつ積み重なることで、月次・年次の集計や決算時に大きなズレを生んでしまいます。
たとえば、似たような取引なのに担当者ごとに違う科目を使っていたり、仮払金や未払金のまま放置されていたりすると、正確な費用の把握や資金の流れが見えにくくなってしまいます。
こうしたリスクを防ぐには、日頃の帳簿を正しくつけるだけでなく、定期的に見直すことが欠かせません。具体的には以下の項目をチェックするのが効果的です。
- 科目の重複や無駄な項目がないか確認
- 仮払金や未払金のまま放置していないか
- 部門ごとに科目の使い方がブレていないか
- 雑費や仮払金の残高が多くないか
- 科目名がわかりやすいか
帳簿のチェックは手間がかかる作業ですが、経営に役立つ数字を得るためにも、定期的な確認を習慣にしましょう。
「楽楽精算」の自動仕訳機能を活用しよう
勘定科目は種類が多くて覚えるのが大変、という方におすすめなのが、経費精算システム「楽楽精算」です。
「楽楽精算」は自動仕訳機能を搭載しており、あらかじめ設定した勘定科目や税区分が自動で反映されます。勘定科目の判断に悩むことが少なくなり、手入力でのミスも防げるでしょう。また、「楽楽精算」内で仕訳を行った後に仕訳データをCSVファイル形式で取り出し、そのままお使いの会計システムへアップロードできる会計ソフト連携機能も搭載。手入力による手間を削減します。
「楽楽精算」は、経理業務の精度と効率を両立させたい企業にとって、非常に心強いツールです。勘定科目で悩む時間がもったいない、さらに経費精算業務を効率化したい、という方は、この機会にぜひ気軽にご相談ください。
「楽楽精算」の
資料をメールでもらう

電子帳簿保存法対応!経費精算システム「楽楽精算」の製品概要や導入メリット、機能などが詳しくわかる資料をメールでお送りします。
この記事を読んだ方におすすめ!
オススメの人気記事
記事執筆者紹介

「楽楽精算」コラム編集部です。
経理担当者様の日々の業務にプラスとなるお役立ち情報
「楽楽精算」最新情報をお届けしていきます!
使い勝手が気になる方へ。