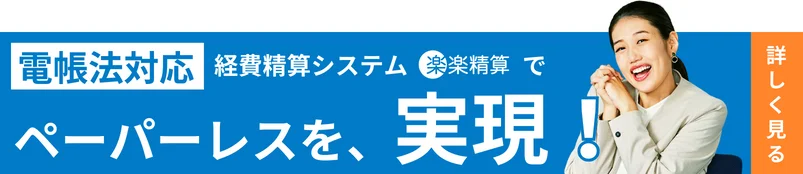ソフトウェアの勘定科目を正しく理解しよう!購入形態や金額による判断基準を解説

経理担当者の方の中には、会社の業務効率を上げるためにソフトウェアを導入したものの、「新しい会計ソフト、勘定科目は何にすればいいんだろう?」「インストール型とクラウド型で、経理処理は違うの?」と迷った経験のある方も多いのではないでしょうか。ソフトウェアは、金額や利用形態によって勘定科目が変わり、正しく処理しないと税務調査で指摘されるリスクもゼロではありません。
ソフトウェアの勘定科目は「購入形態」と「金額」で判断します。この記事では、ソフトウェアの勘定科目や仕訳ルールについて、具体的な仕訳例も交えて詳しく解説していきます。
この記事の目次
そもそも「ソフトウェア」とは?会計・税務上の定義
会計や税務の世界では、ソフトウェアは単なるプログラムではなく、「無形固定資産」として扱われます。建物や機械装置のように物理的な形はありませんが、事業に長期的にわたって使用する「資産」として考えられるためです。
この無形固定資産としてのソフトウェアは、時間の経過とともに価値が減少していくとみなされ、減価償却の対象となります。そのため、購入時に一括で費用にするのではなく、定められた期間で少しずつ費用として計上していくことになります。
ソフトウェアの勘定科目の基本的な考え方
ソフトウェアの経理処理で最も重要なのは、「購入型(インストール型)」か「利用型(クラウド/SaaS)」かを区別することです。この違いによって、費用にするか資産にするかの判断が大きく変わります。
購入型(インストール型)の場合
購入型(インストール型)の場合、金額によって処理が異なります。
- 10万円未満:「消耗品費」などとして、購入時に一括で費用処理します。
- 10万円以上かつ耐用年数1年以上:「無形固定資産(ソフトウェア)」として、資産計上し減価償却を行います。国税庁が定める法定耐用年数は5年です。
利用型(クラウド/SaaS)の場合
月額や年額で利用料を支払うクラウドサービスは、資産には計上しません。支払った利用料は「支払手数料」「通信費」「ソフトウェア使用料」などとして、支払った期の費用として処理します。
【パターン別】ソフトウェアの仕訳方法
ここからは、具体的なパターンごとに仕訳例を見ていきましょう。
パターン1:市販のインストール型ソフトウェアを購入
10万円未満の場合
パソコン用の業務管理ソフト(8万円)を現金で購入した場合の仕訳は、以下のとおりです。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 消耗品費 | 80,000 | 現金 | 80,000 |
10万円以上の場合
会計ソフト(20万円)を銀行振込で購入した場合の仕訳は、以下のとおりです。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| ソフトウェア | 200,000 | 普通預金 | 200,000 |
パターン2:自社で利用するソフトウェアを制作依頼
業務効率化のためにソフトウェアを制作会社に依頼し、開発費用(50万円)を支払った場合の仕訳は以下のとおりです。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| ソフトウェア | 500,000 | 普通預金 | 500,000 |
パターン3:クラウドサービス(SaaS)を月額で利用
クラウド経費精算ツール(月額1万円)の利用料を口座引き落としで支払った場合の仕訳は以下のとおりです。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 支払手数料 | 10,000 | 普通預金 | 10,000 |
【補足】少額減価償却資産の特例
青色申告の中小企業者は、30万円未満のソフトウェアであれば、年間合計300万円まで一括で費用処理できる特例があります。この場合も「消耗品費」として処理することが可能です。
ソフトウェアの仕訳で注意すべきポイント
ソフトウェアの仕訳において注意すべきポイントについて解説します。
購入代金に付随する費用の扱い
ソフトウェアを購入する際、本体価格以外に保守サポート費用や導入コンサルティング費用が発生することがあります。これらの付随費用は、ソフトウェア本体の取得価額に含めるべきか、別途費用として処理すべきかという点で注意が必要です。
例えば、以下のようなケースでは、ソフトウェアの取得金額に含めるべきです。
- ソフトウェアの購入と保守サポートが一体の契約になっており、費用を切り分けられない場合
- ソフトウェアを事業に使える状態にするために不可欠な導入費用やコンサルティング費用である場合
一方で、ソフトウェア本体とは別に、追加で保守契約を締結し、保守費用を支払う場合は、別途費用として処理すべきでしょう。契約書の内容をよく確認し、判断することが重要です。
資産と費用の区分
ソフトウェアは、10万円以上の購入代金と1年以上の利用期間が想定される場合、「無形固定資産」として資産計上することが原則です。
これを「消耗品費」や「事務用品費」などの勘定科目で一括費用処理してしまうと、その事業年度の利益が過少に見積もられることになります。結果として、法人税の申告漏れと判断され、追徴課税の対象となる可能性があるため、注意が必要です。
正しい償却期間
ソフトウェアの法定耐用年数は、国税庁によって「5年」と定められています。
この耐用年数に従って、毎年均等に費用として計上する「定額法」で減価償却を行うのが一般的な方法です。
もし、この5年という法定耐用年数から外れた期間で償却を行っていたり、償却処理自体を忘れていたりすると、税務上のルールに沿っていないとして、税務調査で指摘される対象となります。
まとめ
本記事では、ソフトウェアの正しい経理処理について解説しました。最も重要なポイントは、ソフトウェアの「購入形態」と「金額」によって、勘定科目や仕訳方法が異なることです。具体的には、購入型(インストール型)の場合は、10万円未満であれば「消耗品費」として費用処理し、10万円以上であれば「ソフトウェア」として資産計上し、5年で減価償却を行います。一方で、利用型(クラウド/SaaS)の場合は、「支払手数料」などとして費用処理します。
安易な費用処理は税務上のリスクにつながる可能性があるため、金額や償却期間のルールを正しく理解しておくことが重要です。
ソフトウェアの仕訳を自動化!経費精算システムの活用
「ひとつひとつの仕訳を覚えるのは大変…」「社員によって勘定科目の選び方がバラバラで、属人化している…」
そんな悩みを抱えているなら、経費精算システムの導入が解決策になります。
クラウド型の経費精算システムの中でもおすすめなのが「楽楽精算」です。「楽楽精算」には、仕訳の効率化につながる以下のような機能が搭載されています。
特徴1:自動仕訳機能
申請内容から勘定科目や税区分の振り分けを行い、仕訳を自動化します。大量の領収書・請求書の内容を自動で仕訳できるため、経費精算から会計処理までの手間を軽減できます。仮払いや立替金の仕訳にも対応可能です。貸方・借方の内容チェックのみで仕訳が完了するので、経理担当者の仕訳作業を大幅に効率化できます。
特徴2:会計ソフト連携機能
データ連携によって、「楽楽精算」に登録された仕訳データをそのまま会計ソフトに取り込むことが可能です。経理担当者が手入力で会計ソフトに転記する時間と手間を減らし、会計業務の効率化やミス削減に貢献します。
特徴3:法人カード連携機能
法人クレジットカードの利用明細データをそのままシステムに取り込み、経費申請に活用できます。データに基づいて申請を行えるため、申請者の入力時間が削減される上に、手入力で発生するミスを無くすことが可能です。さらに、立て替えたお金の返金作業がなくなることで、経理担当者の対応業務が減り、負担を抑えられます。
さらに、「楽楽精算」を導入するだけで電子帳簿保存法やインボイス制度などの法対応を簡単に進められます。具体的な導入メリットについて詳しくは無料の資料でご紹介しているため、以下のフォームからぜひお問い合わせください。
「楽楽精算」の
資料をメールでもらう

電子帳簿保存法対応!経費精算システム「楽楽精算」の製品概要や導入メリット、機能などが詳しくわかる資料をメールでお送りします。
この記事を読んだ方におすすめ!
オススメの人気記事
記事執筆者紹介

「楽楽精算」コラム編集部です。
経理担当者様の日々の業務にプラスとなるお役立ち情報
「楽楽精算」最新情報をお届けしていきます!
使い勝手が気になる方へ。