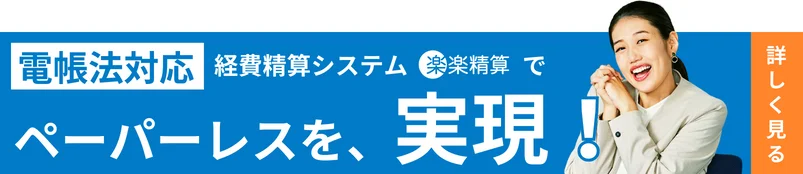社内に据え置く常備薬は何費として経費管理すればいいのでしょうか?

会社で社員のために常備薬を設置することになりましたが、これは経費管理上、勘定科目は何費に仕訳すればいいのでしょうか?また、どんな薬でも経費として認められるのでしょうか?
この記事の目次
常備薬は福利厚生費となります
社員のために設置する常備薬の購入費用は、経費管理上、一般的に「福利厚生費」として計上することとなります。ただし、福利厚生費とする以上は、すべての社員を対象とすることが前提のため、一部の役職者のためだけに購入するのではなく、社員なら誰でも使える仕組みにする必要があります。
また、常備薬として設置する以上は、その使用や在庫管理についても経理で徹底するようにしましょう。
どんな薬でも福利厚生費となるの?
常備薬として福利厚生費となるものを限定しているわけではありませんが、基本的には緊急性の高い症状に対する薬が中心となります。例えば、社員が熱を出したとき用の解熱鎮痛剤や下痢止め、感昌薬、整腸剤などとなります。
特定の人のみが使うような薬については、本来各自で購入すべきもののため、ここでは誰もが使うこととなるような薬に限定すべきでしょう。
仕訳作業や会計ソフトへの入力作業も大幅削減!その方法とは?
常備薬はルールに則っていれば、一般的には福利厚生費として経費計上が可能です。ただ、使用や管理を徹底しないと経費の無駄使いとなってしまう場合もありますので、そのあたりは経理担当として徹底するよう心がけましょう。
また、今回のように「これは勘定科目では何費だろう」と調べる手間も経費精算システム「楽楽精算」を導入すれば削減できます。予め勘定科目をシステムに設定しておけば、申請のタイミングで勘定科目仕訳が完了します。また、その勘定科目付きの金額データも会計ソフト連携機能を使えば効率化できます。
ひとつひとつ勘定科目を調べて、会計ソフトに入力という作業から解放される経費精算システム「楽楽精算」の機能を是非ご確認ください!
>> 「楽楽精算」の自動仕訳機能詳細を見る!>> 「楽楽精算」の会計ソフト連携機能詳細を見る!
「楽楽精算」の
資料をメールでもらう

電子帳簿保存法対応!経費精算システム「楽楽精算」の製品概要や導入メリット、機能などが詳しくわかる資料をメールでお送りします。
この記事を読んだ方におすすめ!
オススメの人気記事
記事執筆者紹介

「楽楽精算」コラム編集部です。
経理担当者様の日々の業務にプラスとなるお役立ち情報
「楽楽精算」最新情報をお届けしていきます!
使い勝手が気になる方へ。