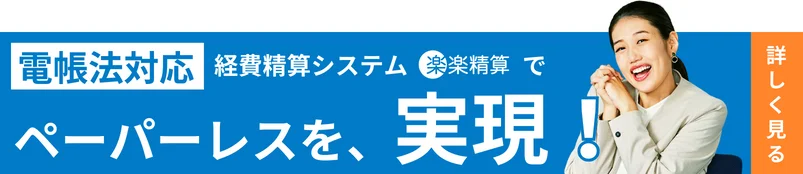労働保険料の主な勘定科目と仕訳例は?よく使われている計上方法3つ

会社は従業員に代わって社会保険料の管理や手続きを行っています。なかでも労働保険料は、会社負担分と従業員負担分に分けられる点や、概算保険料と確定保険料に分けて納付する点から「わかりにくい」と感じる経理担当者の方も多いでしょう。
そこでこの記事では、労働保険料の手続きに関する基本情報や、主な勘定科目、仕訳例などを具体的に解説します。経理業務を効率化する専用システムもご紹介するため、保険料の計上でお悩みの経理担当者の方は、ぜひ参考にしてみてください。
この記事の目次
労働保険料とは?
そもそも労働保険とは、労働者を守るための「雇用保険」と「労災保険」を合わせた総称のことです。
労働者を1人でも雇っている事業所は、雇用保険・労災保険に加入し、保険料を納めることが必須となります。
それぞれの保険制度には、以下のような大切な役割があります。
-
雇用保険
労働者が失業したときや、育児・介護をするときに支援を行うための保険制度です。会社側と従業員側がそれぞれ一定の割合を負担し折半します。このうち従業員負担分は毎月の給与から天引きし、会社側がまとめて納付します。 -
労災保険
業務中や通勤中に発生するケガや病気に対して補償を行うための保険制度です。保険料は全額会社側が負担します。
保険料の納付期間は、当年度の6月1日~7月10日です。納付額は、4月1日~翌年3月31日までの1年間に支払った賃金をもとに計算されます。
次に納付の流れですが、ここが少し複雑です。
まず、 当年度の賃金見込み額から算出した「概算保険料」を一旦納付した上で、翌年度に実際の賃金総額から算出した「確定保険料」を精算する流れとなっています。
- 概算保険料…賃金見込み額から概算し、前もって仮に納付する保険料
- 確定保険料…実際の賃金総額から算出した保険料
確定保険料の精算では、すでに納付した概算保険料との差額に応じて、追加納付または還付が行われます。このように、概算保険料と確定保険料に分けて二度納付・精算することになるため、仕訳の方法が難しいと感じる方もいるはずです。
以降では、労働保険料を仕訳する際の主な勘定科目や、仕訳方法についてさらに詳しく解説します。
参考:厚生労働省「労働保険料の申告・納付」
労働保険料を仕訳する際の主な勘定科目
労働保険料のうち会社負担分は損金算入できます。会社負担分は福利の一部にあたると考えられているため、勘定科目は「法定福利費」とすることがポイントです。
一方、従業員負担分は損金算入できないものの、帳簿には「立替金」などの勘定科目を用いてお金の流れを記録する必要があります。
労働保険料の仕訳では、以下の勘定科目を用いて処理を行いましょう。
会社負担分で使用される勘定科目
・法定福利費
法定福利費とは、法律上で事業主に支払い義務がある保険料を計上するための勘定科目です。 会社負担分の労働保険料を仕訳する際に用いられます。労働保険のほかに、健康保険や厚生年金などの仕訳でも用いられます。
・前払費用
前払費用とは、提供前のサービスに対して事前に支払った費用を計上するための勘定科目です。 労働保険料のうち、概算保険料を処理する際に用いられます。
従業員負担分で使用される勘定科目
・立替金
立替金とは、会社が代わりに支払ったお金を計上するための勘定科目です。 企業が概算保険料を支払ったタイミングで、一時的に立て替えた従業員負担分を「立替金」として計上し、毎月の給与支払時に相殺していきます。
よく使われている労働保険料の仕訳方法3つ
ここでは、一般的によく使われている労働保険料の仕訳方法を3パターンご紹介します。
- パターン1:主に中小企業で使われるシンプルな仕訳
- パターン2:国税庁が提示している仕訳の方法
- パターン3:上場企業や従業員数の多い大企業で用いられる方法
それぞれの種類の特徴を理解して、自社に適した方法で仕訳を行いましょう。
パターン1:主に中小企業で使われるシンプルな仕訳
概算保険料の納付時に一旦「法定福利費」として全額を計上した上で、以降の給与支払時に従業員負担分をマイナス計上していく方法です。税法上はやや不正確であるものの、シンプルに仕訳できることから小規模な会社で用いられています。
以下では、概算保険料60,000円(うち従業員負担分24,000円)、確定保険料90,000円(うち従業員負担分27,000円)の場合の仕訳例をご紹介します。
【概算保険料の納付時】
まずは、概算保険料60,000円の全額を「法定福利費」として計上します。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 法定福利費 | 60,000円 | 普通預金 | 60,000円 |
【給与支払時】
毎月の給与支払時に、従業員負担分を12カ月で案分した金額(24,000円÷12カ月=2,000円)を、「法定福利費」としてマイナス計上していきます。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 給料 | XX円 | 普通預金 | XX円 |
| 法定福利費 | 2,000円 | ||
【確定保険料の納付時】
確定保険料の納付時に、概算保険料との差分である30,000円を計上します。なお、確定保険料が概算保険料よりも少ない場合は、以下の仕訳例と貸借が反対になります。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 法定福利費 | 30,000円 | 普通預金 | 30,000円 |
<注意点>
-
税務的に不正確であり誤解を招きやすい
パターン1では、会社負担分と従業員負担分をまとめて処理します。厳密にいうと税務的に不正確である点に注意が必要です。 -
従業員負担分の保険料が損金に過大計上されるおそれがある
概算保険料・確定保険料の納付時は、それぞれ従業員負担分が過大計上されます。ただし、従業員数が少なければ比較的影響を抑えられるため、経理処理の負担軽減を優先してこちらの方法が採用される場合もあります。
パターン2:国税庁が提示している仕訳の方法
概算保険料の納付時に、会社負担分を「法定福利費」、従業員負担分を「立替金」として仕訳する方法です。国税庁の「法令解釈通達」においては、労働保険料の損金算入の時期について、従業員負担分を「立替金」として処理する方法が提示されています。
参考:国税庁「法令解釈通達 第3節 保険料等 (労働保険料の損金算入の時期等)」
以下では、パターン1と同様に概算保険料60,000円(うち従業員負担分24,000円)、確定保険料90,000円(うち従業員負担分27,000円)の場合の仕訳例をご紹介します。
【概算保険料の納付時】
まずは、概算保険料のうち会社負担分36,000円を「法定福利費」、従業員負担分24,000円を「立替金」として仕訳します。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 法定福利費 | 36,000円 | 普通預金 | 60,000円 |
| 立替金 | 24,000円 | ||
【給与支払時】
毎月の給与支払時に、従業員負担分(24,000円÷12カ月=2,000円)を立替金と相殺します。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 給料 | XX円 | 預金 | XX円 |
| 立替金 | 2,000円 | ||
【確定保険料の納付時】
確定保険料の納付時は、会社負担分27,000円を「法定福利費」、従業員負担分3,000円を「立替金」として仕訳します。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 法定福利費 | 27,000円 | 預金 | 30,000円 |
| 立替金 | 3,000円 | ||
<注意点>
-
保険料の納付時に法定福利費が大きくなりやすい
パターン2では、労働保険料を納付する月に、法定福利費がまとめて計上されます。特に従業員数が多い企業では月次決算の金額への影響が大きくなりやすく、財務状況を正確に判断しにくくなるのが注意点です。
パターン3:上場企業や従業員数の多い大企業で用いられる方法
概算保険料の納付時に、会社負担分を「前払費用」、従業員負担分を「立替金」として仕訳する方法です。発生主義の原則に基づき、前払費用を実際に属する期間に案分することで精度を高められます。
以下では、概算保険料60,000円(うち従業員負担分24,000円)、確定保険料90,000円(うち従業員負担分27,000円)の場合の仕訳例をご紹介します。
【概算保険料の納付時】
まずは、概算保険料の会社負担分36,000円を「前払費用」、従業員負担分24,000円を「立替金」として仕訳します。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 前払費用 | 36,000円 | 預金 | 60,000円 |
| 立替金 | 24,000円 | ||
【給与支払時】
毎月の給与支払時に、会社負担分の労働保険料(36,000円÷12カ月=3,000円)を以下のように仕訳します。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 法定福利費 | 3,000円 | 前払費用 | 3,000円 |
また、従業員負担分の労働保険料(24,000円÷12カ月=2,000円)は立替金と相殺します。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 給料 | XX円 | 預金 | XX円 |
| 立替金 | 2,000円 | ||
【確定保険料の納付時】
確定保険料の納付時は、「未払費用」と「立替金」で処理を行います。立替金の3,000円は、その後の給与支払時に従業員から不足分を回収して調整します。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 未払費用 | 27,000円 | 預金 | 30,000円 |
| 立替金 | 3,000円 | ||
<注意点>
-
仕訳方法が煩雑になりやすい
パターン3では、会社負担分を「前払費用」とし、実際に属する期間に案分して処理します。標準化によって月次決算の正確性を高められる反面、仕訳方法が煩雑になりやすい点には留意しましょう。
労働保険料は正確な勘定科目で仕訳しましょう!
ここまで、労働保険料の手続きに関する基本情報や、主な勘定科目、仕訳例などをご紹介しました。経理部門では労働保険料のほかにも、従業員全員分の社会保険料を処理する重要な役割を担っています。 正確性を求められる経費精算業務を効率化するなら、専用のシステムを導入する方法がおすすめです。 例えばクラウド型経費精算システム「楽楽精算」には、仕訳をラクにする機能が充実しています。
「楽楽精算」の機能1:自動仕訳機能
事前に設定した勘定科目で自動的に仕訳されるので、経理担当者が画面上でチェックするだけで簡単に作業が完了します。立替金や仮払いの仕訳にも対応可能です。
「楽楽精算」の機能2:会計ソフト連携機能
「楽楽精算」の仕訳データをデータ連携によってそのまま会計ソフトへ取り込めます。金額や取引内容の転記が不要となるため、入力作業の効率化や人的ミスの低減に貢献します。
「楽楽精算」についてさらに詳しく知りたい方へ向けて、無料の資料をご用意しています。以下のフォームからお気軽にお問い合わせください。
「楽楽精算」の
資料をメールでもらう

電子帳簿保存法対応!経費精算システム「楽楽精算」の製品概要や導入メリット、機能などが詳しくわかる資料をメールでお送りします。
この記事を読んだ方におすすめ!
オススメの人気記事
記事執筆者紹介

「楽楽精算」コラム編集部です。
経理担当者様の日々の業務にプラスとなるお役立ち情報
「楽楽精算」最新情報をお届けしていきます!
使い勝手が気になる方へ。