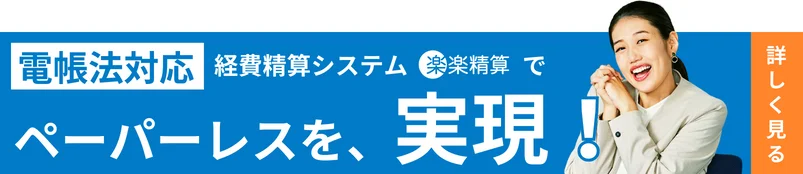【保存版】所得税の勘定科目ガイド|納付・源泉徴収・修正申告対応

「所得税の仕訳は、どの勘定科目を使えばいいの?」「源泉徴収した税金って、どうやって処理するの?」年度末や年末調整の時期になると、こうした疑問を感じる経理初心者の方は少なくありません。
法人の場合、所得税は自社の負担ではなく、従業員の給与などから一時的に預かって税務署に納めるものです。そのため、使うべき勘定科目や仕訳方法には、基本的なルールがあります。
本記事では所得税の会計処理について、初心者でも理解しやすいように以下の内容を中心に解説します。
- 所得税に使う正しい勘定科目
- 給与や賞与を支払う際の具体的な仕訳例
- 延滞税や修正申告など、特殊なケースの処理方法
- ミスを防ぐためのスケジュール管理やツール活用のポイント
正しい処理を身につけることで、月次・年次の決算や税務申告もスムーズに行えるようになります。経理業務の不安を減らし、安心して対応できるよう、実務で役立つ知識をぜひ参考にしてみてください。
この記事の目次
はじめに知っておきたい所得税の基本
所得税とは、個人が1年間に得た所得に対して課される国税です。日本では累進課税制度が採用されており、所得が高くなるほど税率も上がる仕組みです。
企業の経理に関してよく登場する所得税は、主に従業員の給与や賞与から天引き(源泉徴収)する所得税を指します。
この源泉徴収された所得税は、会社が従業員から一時的に預かっているお金であり、後日まとめて企業が税務署へ納付します。
所得税はあくまで従業員の個人に課される税金であり、会社が立て替えて払うものではありません。仕訳の際も、経費ではなく預り金などの負債科目で処理するのが基本です。
所得税の処理は「預り金」が基本
従業員や役員に対して給与や報酬を支払う際、会社は所得税を源泉徴収します。このときの会計処理で重要となるのが「預り金」という勘定科目です。
ここでは、法人経理における「預り金」の正しい使い方と、具体的な仕訳例について解説します。
従業員の所得税は預り金で処理
会社が従業員の給与から天引きした源泉所得税は、「預り金」という負債の勘定科目で処理します。
源泉徴収した所得税は、会社の売上や利益ではなく、あくまで従業員に代わって税務署へ納付するために一時的に預かっているお金です。そのため、会計上は負債として「預り金」勘定を使って仕訳を行います。
仕訳例:給与支給時(支給額:30万円、源泉税:3万円)
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 給与手当 | 300,000 円 | 預り金 | 30,000 円 |
| 預金 | 270,000円 | ||
仕訳例:源泉所得税の納付時
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 預り金 | 30,000 円 | 預金 | 30,000 円 |
会計ソフトでは、「預り金」の中でも源泉所得税や社会保険料などを補助科目で分けておくと、税金ごとの管理がスムーズになります。
役員報酬や賞与で徴収した所得税も預り金で処理
役員報酬や賞与(ボーナス)から源泉徴収した所得税も、毎月の給与と同じく「預り金」勘定で処理するのが原則です。
役員報酬や賞与も、会計上は従業員の給与と同じく個人の所得と見なされます。そのため会社は所得の種類にかかわらず、支払いを行う際に所得税を天引きする「源泉徴収義務者」としての役割を担います。
仕訳例:役員報酬支給時(報酬:50万円、源泉税:5万円)
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 役員報酬 | 500,000 円 | 預り金 | 50,000 円 |
| 預金 | 450,000円 | ||
給与や役員報酬、賞与など支払い名目ごとに勘定科目を変えるのではなく、一貫したルールで管理することが、経理業務をシンプルにし、ミスを防ぐための重要なポイントです。
年末調整で還付金があった場合の仕訳
年末調整の結果、従業員に対して所得税を還付することがあります。これは税金を会社が負担するということではなく、預かりすぎた分を返金するという意味合いです。
そのため、会計上は「預り金」の残高を減らす仕訳となります。
仕訳例:還付金1万円を給与に上乗せして支給した場合(給与30万円)
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 給与手当 | 300,000 円 | 預金 | 310,000 円 |
| 預り金 | 10,000 円 | ||
年末調整で発生した還付金は、過剰に預かっていた金額を返す処理です。あらかじめ会計ソフトで年末調整用の補助科目を設定しておくと、処理のミスを防ぎやすくなります。
間違いやすい所得税に関するその他の勘定科目
所得税の処理には基本ルールがありますが、実務では例外的なケースに遭遇することも少なくありません。
たとえば、納付遅れによる延滞税や加算税、あるいは従業員の所得税を会社が負担するケースなど、正しい勘定科目の判断に迷う場面が出てきます。
そこで、経理実務でとくに間違いやすい5つのケースを取り上げ、それぞれの正しい処理方法をわかりやすく解説します。
- 不納付加算税・延滞税の勘定科目
- 会社が肩代わりした所得税の勘定科目
- 修正申告などによる再納付した所得税の勘定科目
- 復興特別所得税の勘定科目
- 定額減税の処理に対する仕訳と勘定科目
不納付加算税・延滞税の勘定科目
源泉所得税の納付が遅れた場合、税務署から延滞税や不納付加算税が課されることがあります。これらは罰則的な性質の強い税金であるため、通常の所得税とは会計処理が異なる点に注意が必要です。
会計上の仕訳では、これらの費用は「租税公課」で処理します。
仕訳例:延滞税10,000円を納付した場合
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 租税公課 | 10,000 円 | 預金 | 10,000 円 |
ただし、延滞税として納付し、租税公課で処理した支出は損金不算入となります。損金不算入とは、会計上は費用として計上していても、法人税の計算では経費として認められないお金のことです。
これらは納税の遅れに対するペナルティという性質をもつため、法人税法上、会社の経費(損金)として認めることはできないというルールになっているためです。
そのため、会計上は費用として処理しても、税務申告書では課税所得に加算しなおす必要がある点を覚えておきましょう。
納付漏れは思わぬコスト増につながるため、あらかじめ納付スケジュールを把握し、会計ソフトやカレンダー機能で通知を設定しておくのが有効です。
参考:損金の額に算入される租税公課等の範囲と損金算入時期|国税庁
会社が肩代わりした所得税の勘定科目
本来、源泉所得税は従業員の給与から天引きして納付するのが原則です。しかし、なんらかの理由で天引き漏れが発生し、会社が従業員の代わりに支払った場合、その金額は追加の給与として扱われることになります。
したがって、処理上は以下のように「給与手当」で仕訳を行います。
仕訳例:肩代わりした所得税10,000円を納付した場合
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 給与手当 | 10,000 円 | 預金 | 10,000 円 |
この仕訳は、会社が実質的に従業員へ追加の金銭を支給したという位置づけです。源泉徴収を忘れていた場合も、最終的には給与支給額に含めて税務処理する必要があります。
修正申告などによる再納付した所得税の勘定科目
年末調整や税務調査の結果、所得税の計算に誤りがあり、追加で税金を納めるケースもあります。このような場合も、基本的には従業員にかかる税金として「預り金」を使用して処理しましょう。
たとえば従業員の給与に関する過少申告が判明し、追加で源泉所得税を納める場合は以下のような仕訳になります。
仕訳例:再納付額 20,000円の場合
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 預り金 | 20,000 円 | 預金 | 20,000 円 |
このようなミスを防ぐには、年末調整の内容を事前に複数人で確認するなど、社内のダブルチェック体制を整えておくことが有効です。
復興特別所得税の勘定科目
「復興特別所得税」は、東日本大震災からの復興を目的に創設された税制度で、所得税に一定割合(2.1%)を上乗せして課されます。
計算上は所得税と別に扱いますが、会計処理上は通常の所得税に含めて「預り金」として一括処理するのが原則です。
たとえば、給与から天引きする源泉所得税の中に復興特別所得税が含まれている場合でも、仕訳では個別に分ける必要はありません。
仕訳例:給与30万円、源泉税(復興税含む)3万円の場合
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 給与手当 | 300,000 円 | 預り金 | 30,000 円 |
| 預金 | 270,000円 | ||
帳簿上で復興特別所得税を分けて処理すると、かえって管理が煩雑になりやすいため、原則として合算処理が推奨されます。
2037年(令和19年)まで課される制度ですが、特別な処理が必要な訳ではないので、復興特別所得税が上乗せされた金額である点だけ認識しておきましょう。
定額減税の処理に対する仕訳と勘定科目
2024年6月から始まった「定額減税」により、所得税および住民税の源泉徴収実務に変化が生じています。
同制度は、ひとりあたり年4万円(所得税3万円+住民税1万円)を、給与・賞与支給時の源泉税額から控除する形で実施されます。
この制度により、月々の源泉所得税が実質的に減額されるため、従業員の手取り額が一時的に増える点が最大の特徴です。
経理担当者は以下のポイントを押さえておきましょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 減税方法 | 給与・賞与支給時に源泉税から控除 |
| 対象者 | 原則すべての居住者(所得制限あり) |
| 控除額 | 所得税3万円(6月以降の給与から段階的に)、住民税1万円(6月支給分から一括控除) |
| 会計処理 | 預り金で控除後の金額を記帳 |
| 仕訳例の注意点 | 例年と異なり、源泉税額が少なくなる場合があるため「預り金」勘定の金額に注意 |
※令和6年度に実施された内容
月次減税で控除する額は、貸方の「預り金」から直接減額する形で処理します。
仕訳例:給与30万、本来の源泉税1万円、定額減税1万円の場合
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 給与手当 | 300,000 円 | 預金 | 300,000 円 |
| 預り金 | 0円 | ||
なお、2025年度においては情報が発表されていないため、最新情報を知りたい方は、国税庁の公式サイトを随時ご確認ください。
所得税の納付期日を逃さないためのスケジュール管理方法
企業の経理担当者にとって、税金の納付期日を正確に把握することは非常に重要です。
所得税をはじめ、法人税や消費税、住民税や事業税など法人が対応すべき税金は多岐にわたり、納付スケジュールもバラバラです。
納付が遅れると、延滞税や加算税などのペナルティが発生する可能性があるため、スケジュール管理の仕組みづくりは必須といえるでしょう。
ここでは、納付忘れを防ぐための実践的な方法として、以下の2点を解説します。
- 税目ごとの「年間納付スケジュール表」を作る
- 会計ソフトの納税スケジュール機能を活用する
税目ごとの「年間納付スケジュール表」を作る
まず取り組みたいのが、納付スケジュールを一覧表にまとめることです。税金の種類ごとに納付時期と期限を明記し、いつ・何の税金を支払う必要があるのかを可視化することで、対応漏れを防げます。
例:決算月が3月の場合の納付スケジュール表
| 税目 | 納付時期 | 納付先 | 納付期限の目安 |
|---|---|---|---|
| 法人税(確定) | 決算終了後 | 税務署 | 5月末(決算から2か月) |
| 消費税(確定) | 決算終了後 | 税務署 | 同上 |
| 源泉所得税 | 毎月または半年ごと | 税務署 | 源泉徴収の対象となる給与や報酬を支払った月の翌月10日、または従業員が常時10人未満である企業は特例として年2回の納付が可能 |
| 法人住民税 | 決算終了後 | 市区町村 | 5月末ごろ |
| 法人事業税 | 決算終了後 | 都道府県 | 5月末ごろ、中間納付もあり |
スケジュール表はExcelやGoogleスプレッドシートなどで作成すると便利です。カレンダー機能と連携させて、リマインダー通知を設定すれば、納付忘れをさらに防止しやすくなります。
参考:源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例|国税庁
会計ソフトの納税スケジュール機能を活用する
クラウド型の会計ソフトを使っている場合は、ソフトに備わっている「納税スケジュール管理機能」を活用するのも有効です。
たとえば、クラウド型の会計ソフトには以下のような機能が搭載されているケースが多くあります。
| 機能 | 効果 |
|---|---|
| 納税カレンダー表示 | 納付予定の税金と期日が自動で一覧化される |
| アラート通知 | 納付期限が近づくとメールで通知される |
| Todo機能との連携 | 未完了の納税タスクを可視化し、漏れを防ぐ |
| 納付書の自動作成・e-Tax連携 | 必要書類の作成やオンライン納税にも対応できる |
これらの機能を活用すれば、担当者の負担を減らしつつ、ヒューマンエラーによる納付遅れを効果的に防げます。
納税スケジュールを適切に管理することは、延滞税や加算税といった無駄な出費を防ぎ、企業の信用を守るうえでも重要です。
まずは年間スケジュール表の作成からはじめ、会計ソフトの管理機能も併用して、確実な納税管理体制を整えましょう。
所得税の勘定科目で悩んだら「楽楽精算」を活用しよう
所得税の仕訳ルールを理解していても、日々の経費精算や会計処理の中で判断に迷う場面は少なくありません。とくに、経費精算時に勘定科目を誤ると、月次決算や年末調整、税務申告にまで影響が及ぶおそれがあります。
そうしたミスを防ぎつつ、経理業務全体を効率化する手段として注目されているのが、クラウド型の経費精算システム「楽楽精算」です。
「楽楽精算」を活用する主なメリットと主な機能は、以下のとおりです。
| 機能 | メリット |
|---|---|
| 自動仕訳機能 | 勘定科目の選択ミスを防止できる |
| 会計ソフト連携機能 | 転記が不要になり、二重入力の工数を削減できる |
| 領収書読み取り(AI-OCR) | 領収書の内容をスマホで撮影するだけで、自動でデータ化できる |
| 交通系ICカード取込 | 利用日や経路、運賃といった交通費精算に必要なデータを自動で取り込み、そのまま申請に使用できる |
導入によって得られるメリットは、単なる作業時間の短縮にとどまりません。紙書類の回覧・保管が不要になることでペーパーレス化が進み、テレワーク環境下でも経費精算がスムーズに行えます。
また、ICカードの履歴や法人カードの明細と連携させることで、申請内容の正確性が高まり、不正防止や内部統制強化にもつながります。
所得税に関する会計処理のミスを減らしたい、経費精算に時間を取られている、そのような悩みがある方は、まず以下から「楽楽精算」の資料をご覧ください。
「楽楽精算」の
資料をメールでもらう

電子帳簿保存法対応!経費精算システム「楽楽精算」の製品概要や導入メリット、機能などが詳しくわかる資料をメールでお送りします。
この記事を読んだ方におすすめ!
オススメの人気記事
記事執筆者紹介

「楽楽精算」コラム編集部です。
経理担当者様の日々の業務にプラスとなるお役立ち情報
「楽楽精算」最新情報をお届けしていきます!
使い勝手が気になる方へ。