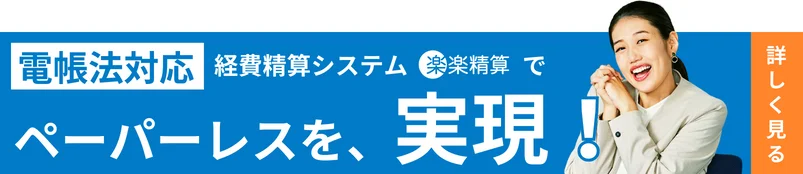消耗品費とはどのような勘定科目?仕訳例や正確な記帳のポイント

経費の仕訳の中でも、「消耗品費」は特に判断に迷いやすい勘定科目です。事業に必要な消耗品に対して用いられる勘定科目ですが、具体的にはどのような物品が該当するのか、経理処理に不安を感じている方も多いでしょう。
そこでこの記事では、勘定科目の「消耗品費」に関する基礎知識や、仕訳例、正確な記帳のポイントなどを解説します。現状の運用や仕訳に問題を感じている経理担当者の方は、ぜひ参考にしてみてください。
この記事の目次
「消耗品費」とはどのような勘定科目?
初めに、勘定科目の「消耗品費」に関する基礎知識を解説します。正確な経費処理のために、消耗品費に当たるものはなにか、その具体例を確認していきましょう。
勘定科目の「消耗品費」とは、業務で使用する消耗品の購入費用に対して用いられる勘定科目です。国税庁が解説する「確定申告書等作成コーナー よくある質問」においては、「使用可能期間が1年未満」または「取得価額が10万円未満」の什器備品が対象となるとされています。
参考:国税庁「消耗品費」
具体的に「消耗品費」に該当するのは、以下のような物品です。使うごとに消費・消耗して無くなる性質を持つバックオフィス用品は、一般的に消耗品と見なされます。
| カテゴリー | 消耗品の具体例 |
|---|---|
| 事務用品・文房具 | ボールペン、シャープペンシル、消しゴム、ステープラー、ノート、コピー用紙、封筒、付箋、クリアファイル、フォルダー、包装紙 など |
| OA機器などの小物・備品 | マウス、キーボード、USBメモリ、スマートフォンの充電ケーブル、延長コード など |
| プリンター・印刷関係 | トナー、インクカートリッジ、印刷用ラベルシール など |
| オフィス日用品・衛生用品 | トイレットペーパー、ティッシュ、洗剤、手指消毒スプレー、ハンドソープ、ごみ袋、掃除用品、電球 など |
上記の表のように、取得価額が10万円未満ですぐに使用される消耗品は減価償却の対象外です。
一方、会社の規模によっては特例によって10万円以上の資産が減価償却の対象外となる可能性もあります。この特定は「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」と呼ばれます。詳しくは以下で解説します。
中小企業者等の少額減価償却資産の
取得価額の損金算入の特例について
中小企業などが、取得価額30万円未満の減価償却資産(=少額減価償却資産)を取得して使用した場合、一定の要件を満たすと取得価額に相当する金額を損金算入することが可能です。この特例では、平成18年(2006年)4月1日から令和8年(2026年)3月31日までの期間に取得した資産が対象となります。
さらに詳しく確認したい方は、国税庁のWebサイトを併せてご覧ください。
「消耗品費」と「雑費」の勘定科目における違いは?
勘定科目の「消耗品費」と「雑費」には税法上の定義がないため、それぞれを明確に定義して区別することは難しいといえます。そのため、使い分け方はあくまでも企業側が自社のルールに則って利用を判断する形になります。
一般的に、「雑費」は分類が難しい少額の費用や、目には見えないサービスの費用などを処理する際に用いられるケースが多いです。具体的には、「クレジットカードの年会費」「振込手数料」「書類の発行手数料」といった支出に用いられます。
ただし、より適切な勘定科目に分類できる費用は、可能な限り「雑費」以外で処理するのが望ましいでしょう。経費計上の際に「雑費」を多用すると、経費の用途が混同されて不透明になりやすく、財務管理や税務調査で支障が出るおそれがあります。
消耗品費の仕訳の例
ここでは、消耗品費の仕訳例をご紹介します。業務で消耗品を使用する際は、大きく「購入してすぐに使用するパターン」と「購入後に一時的に未使用のまま保管するパターン」に分けられます。それぞれの仕訳方法や書き方を理解しておきましょう。
パターン1:購入時にすぐ使用する
消耗品を購入してすぐに使用するパターンでは、購入時点で「消耗品費」として処理を行います。こちらの仕訳方法に適しているのは、「出費が少額であるケース」「消耗品の購入・使用頻度が高いケース」「在庫管理が不要なケース」などです。
以下では、従業員が研修で使うボールペンやノートを4,000円で購入した場合の仕訳例をご紹介します。借方科目は「消耗品費」、貸方科目は「現金」と記載しましょう。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 消耗品費 | 4,000円 | 現金 | 4,000円 |
パターン2:購入後に一時的に未使用のまま保管する
消耗品の購入後に一時的に未使用のまま保管するパターンでは、購入時に「消耗品」として処理を行い、使用時に「消耗品費」へ振替を行います。こちらの仕訳方法に適しているのは、「高額な消耗品をストックするケース」「消耗品の数量・残高の管理が必要なケース」などです。また、学校・病院・倉庫のような期末に在庫調整が必要な業種で用いられる場合があります。
以下は、数年分の印刷用紙を現金80,000円でまとめて購入した場合の仕訳例です。購入時には、借方科目に「消耗品」、貸方科目に「現金」と記載しましょう。
【購入時の仕訳】
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 消耗品 | 80,000円 | 現金 | 80,000円 |
続いて、購入した印刷用紙を10,000円分使用したとします。使用時には、以下のように借方科目に「消耗品費」、貸方科目に「消耗品」と記載して振替を行います。
【使用時の振替仕訳】
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 消耗品費 | 10,000円 | 消耗品 | 10,000円 |
その後、期末決算の時点で1,000円分の印刷用紙が未使用だったとします。この場合、期末決算では借方科目に「消耗品」、貸方科目に「消耗品費」と記載して1,000円分の処理を行いましょう。これにより、翌期に使用する印刷用紙の分を正確に帳簿に残すことが可能です。
【期末決算】
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 消耗品 | 1,000円 | 消耗品費 | 1,000円 |
消耗品費の仕訳をより正確に行うためのポイント
経費管理を詳細に行いたい場合、「消耗品費」の勘定科目のみでは支出の内訳がわかりにくいのが難点です。そんなときは、以下の方法での仕訳をご検討ください。消耗品費の仕訳をより正確に行うためのポイントをお伝えします。
消耗品に補助科目を設定する
補助科目とは、勘定科目をより詳細に管理するための項目です。「消耗品費」に該当する支出をさらに細かい補助科目に分類することで、経費の用途がより明確になります。例えば「事務用品」「清掃用品」「文房具」などの補助科目を設定するとよいでしょう。
以下は、「消耗品費」の補助科目に「文房具」を設定した場合の仕訳例です。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 消耗品費 (文房具) |
4,000円 | 現金 | 4,000円 |
摘要欄を活用する
経費の用途を明確にするために、摘要欄を活用するのも一つの方法です。会計帳簿の摘要欄には、取引の具体的な情報を記載できます。摘要欄に品目・使用目的・取引先などを記載しておくことで、支出の内訳がわかりやすくなります。
以下は、「消耗品費」の摘要欄に詳しい取引内容を記載した場合の仕訳例です。
| 借方 | 貸方 | 摘要 | ||
|---|---|---|---|---|
| 消耗品費 | 4,000円 | 現金 | 4,000円 | 品名:ボールペン 購入数:30本 購入店舗:◯◯スーパー |
消耗品費の勘定科目は自動仕訳機能で統一すると安心!
ここまで、勘定科目の「消耗品費」に関する基礎知識や、仕訳例、正確な記帳のポイントなどをお伝えしました。消耗品費は判断に迷いやすい項目であり、担当者ごとの処理のばらつきが懸念されるため、社内で仕訳ルールの徹底を図りましょう。煩雑な仕訳作業を効率化するなら、自動仕訳機能を搭載したクラウド型経費精算システム「楽楽精算」を活用するのがおすすめです。
「楽楽精算」には、経理業務を効率化する便利な機能が搭載されています。電子帳簿保存法やインボイス制度など最新の法律に対応しているため安心です。
便利機能1:自動仕訳機能
経費申請の内容に応じて自動で勘定科目や税区分を振り分ける機能です。あらかじめ設定した勘定科目が自動的に選択されるため、頻繁に発生する仕訳の手間をなくせる上に、担当者ごとの処理のばらつきを避けられます。
便利機能2:会計ソフト連携機能
会計ソフトとのデータ連携によって、「楽楽精算」の仕訳データを会計ソフトへ取り込む機能です。経理担当者は会計処理の度に仕訳を手入力する必要がありません。会計ソフトへの転記作業をなくし、会計業務の効率化やミス削減につながります。
便利機能3:規定違反チェック機能
社内規定に違反した経費申請を自動でブロックしたり、警告を表示したりする機能です。差し戻しの発生を未然に防ぐことで、申請者・経理担当者の負担を軽減します。また、ルールに則った経費精算を徹底することで、内部統制の強化も期待できます。
「楽楽精算」の機能や導入メリットについてさらに詳しくは、無料の資料でご紹介しています。以下からお気軽にお問い合わせください。
「楽楽精算」の
資料をメールでもらう

電子帳簿保存法対応!経費精算システム「楽楽精算」の製品概要や導入メリット、機能などが詳しくわかる資料をメールでお送りします。
この記事を読んだ方におすすめ!
オススメの人気記事
記事執筆者紹介

「楽楽精算」コラム編集部です。
経理担当者様の日々の業務にプラスとなるお役立ち情報
「楽楽精算」最新情報をお届けしていきます!
使い勝手が気になる方へ。