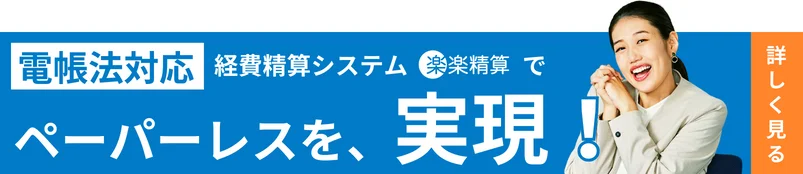コンサルタント費用の経費精算については、何費に仕訳すればいいのでしょうか?

弁護士や税理士などの専門家にコンサルタント費用や顧問料などの報酬を支払う場合は、経費精算上どの勘定科目に仕訳をして処理をすればよいのでしょうか。また個人に対して支払う場合は、どんな点に注意すればいいのでしょうか。
この記事の目次
コンサルタント費用は「外注費」もしくは「支払手数料」などが一般的
専門家への業務委託費用やコンサルタント費用、顧問料などについては、一般的には外注費もしくは支払手数料として処理をし、計上することになります。
例えば、監査報酬、経営コンサルタント料、弁護士報酬などのほかマーケティング調査委託料など市場調査を外部に委託した場合の費用などについても同様に仕訳をします。
個人に対する支払いは「源泉徴収」の必要があることに注意
弁護士や税理士など個人に対して支払う報酬については、所得税法上その報酬を支払う前に所得税を源泉徴収しなければならないため注意しましょう。この際の経費処理の方法としては、源泉徴収分を預かり金に計上することになりますので覚えておきましょう。なお、法人に対して支払う費用については源泉徴収の必要はありません。
まとめ
このようにコンサルタント費用については、一般的に「外注費」や「支払手数料」に仕訳することになりますが、これらの勘定科目は該当するものが多いため、あまりまとめすぎると一つ一つがわかりにくくなる恐れがあります。
例えば、銀行の振込手数料なども支払手数料に仕訳をするような場合は、別途別の科目を作ることをおすすめします。
また、これら経費精算や仕訳をスムーズに行うためには、経費精算システムを導入するとより効率的です。経費精算システムを導入すれば、申請者が精算時に自動で設定された勘定科目に仕訳ができるほか、請求書に対しての支払処理もスムーズに進めることができます。
>> 「楽楽精算」の便利な自動仕訳機能を見る!さらに、クラウド型経費精算システムの「楽楽精算」はCSV出力ができる会計ソフトのほぼすべてとの連携ができるので、会計ソフトに勘定科目や税区分、金額などを何度も入力する必要もなくなります。便利な自動仕訳機能、会計ソフト連携機能を是非ご確認ください。
>> うちのソフトは対応している?「楽楽精算」の会計ソフト連携機能「楽楽精算」の
資料をメールでもらう

電子帳簿保存法対応!経費精算システム「楽楽精算」の製品概要や導入メリット、機能などが詳しくわかる資料をメールでお送りします。
この記事を読んだ方におすすめ!
オススメの人気記事
記事執筆者紹介

「楽楽精算」コラム編集部です。
経理担当者様の日々の業務にプラスとなるお役立ち情報
「楽楽精算」最新情報をお届けしていきます!
使い勝手が気になる方へ。