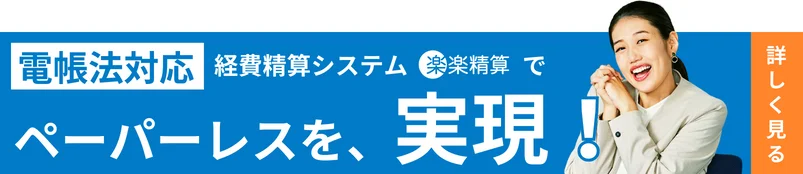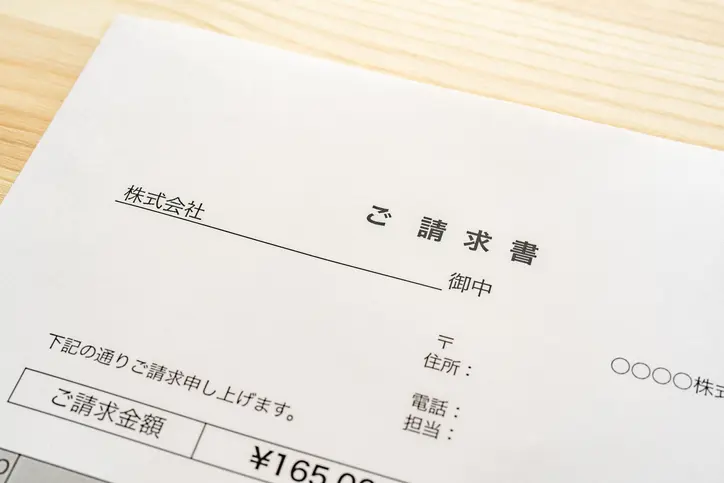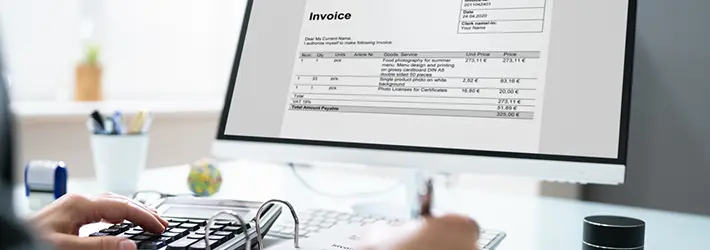経費精算で使用した書類を電子帳簿保存法に則って保管するには?
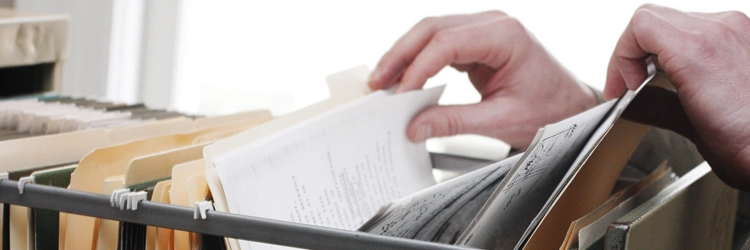
電子帳簿保存法の改正により、国税関係帳簿書類や取引に関係する書類などは、紙ではなく電子データでの保存が認められています。対象となる書類は領収書や請求書、会計帳簿、契約書などさまざまです。立て替えの際に受領した領収書やレシートなど、経費精算で取り扱う書類は電子データとして保管できます。
この記事では、経費精算書類を保管するときに気をつけたい電子帳簿保存法の保存要件や、電子データで保存するメリット、よくある質問などをご紹介します。
この記事の目次
電子帳簿保存法と経費精算の関係
電子帳簿保存法とは、領収書・請求書などの書類や帳簿の保存のコストを削減するために、電子データでの保存を認める法律です。ペーパーレス化の促進を目的として、2022年1月に改正されました。
電子帳簿保存法の改正以前から、経費精算に関連する帳簿や領収書などは、一定期間の保存が義務付けられていました。期間は原則として法人税の申告期限の翌日から7年間です。7年の間に蓄積される書類は膨大な量になり、保管場所や管理に困るケースも少なくありません。
電子データとして書類を保存すれば、こうした問題を解決できます。
ただし、経費精算書類を電子保存する場合は、電子帳簿保存法に定められた保存要件を満たさなければいけません。領収書やレシート、経費精算申請書などは、法律に則した適切な方法で保存する必要があります。求められる条件やルールを理解して、自社の経費精算フローへ反映させましょう。ルールについては、以下の見出しで詳しく解説します。
参考:国税庁「制度創設等の背景」
経費精算後の書類を保管する際に守るべき電子帳簿保存法の要件
電子帳簿保存法には、「電子帳簿等保存」「スキャナ保存」「電子取引」の3つの保存区分が存在します。以下では、それぞれの概要や満たすべき要件をご紹介します。
電子帳簿等保存
電子的に作成した帳簿・書類をそのままデータとして保存する際は、「電子帳簿等保存」の保存区分に該当します。
主な要件としては、「訂正・削除の記録が残るようにすること」「日付・取引金額・取引先で検索できること」などが挙げられます。税務調査などで提出を求められた際にすぐに対応できるようにしておきましょう。
詳しい要件は以下の通りです。
| 要件概要 | 帳簿 | 書類 | ||
|---|---|---|---|---|
| 優良 | その他 | |||
| 記録事項の訂正・削除を行った場合には、これらの事実及び内容を確認できる電子計算機処理システムを使⽤すること | 〇 | - | - | |
| 通常の業務処理期間を経過した後に入力を行った場合には、その事実を確認できる電子計算機処理システムを使⽤すること | 〇 | - | - | |
| 電子化した帳簿等の記録事項とその帳簿等に関連する他の帳簿等との間で、相互にその関連性を確認できること | 〇 | - | - | |
| システム関係書類等(システム概要書、システム仕様書、操作説明書、事務処理マニュアル等)を備え付けること | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 保存場所に、電子計算機、プログラム、ディスプレイ、プリンタ及びこれらの操作マニュアルを備え付け、記録事項を画面・書面に整然とした形式及び明瞭な状態で速やかに出力できるようにしておくこと | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 検索要件 | 1 取引年⽉日、取引金額、取引先により検索できること | 〇 | - | -※3 |
| 2 日付又は金額の範囲指定により検索できること | 〇※1 | - | -※3 | |
| 3 2以上の任意の記録項目を組み合わせた条件により検索できること | 〇※1 | - | - | |
| 税務職員による質問検査権に基づく電子データのダウンロードの求めに応じることができるようにしておくこと | -※1 | 〇※2 | 〇※3 | |
※1:検索要件➀~➂について、ダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合には、➁➂の要件が不要。
※2:「優良」欄の要件を全て満たしているときは不要。
※3:取引年月日その他の日付により検索ができる機能及びその範囲を指定して条件を設定することができる機能を確保している場合には、ダウンロードの求めに応じることができるようにしておくことの要件が不要。
参考:国税庁「はじめませんか、帳簿・書類のデータ保存(電子帳簿等保存)」
スキャナ保存
紙の書類をスキャンして電子データ化した上で保存する場合、「スキャナ保存」の区分に当てはまります。
スキャナ保存する際は、「解像度200dpi相当以上で読み取ること」「カラー画像は256階調以上で読み取ること」などの細かい条件が指定されているため注意が必要です。
具体的な要件は以下の通りです。
| 重要書類 (資金や物の流れに直結・連動する書類) |
一般書類 (資金や物の流れに直結・連動しない書類) |
|
|---|---|---|
| 書類の例 | 契約書、納品書、請求書、領収書 など | 見積書、注文書、検収書 など |
| 入力期間の制限 | 次のどちらかの入力期間内に入力すること ➀ 書類を作成または受領してから、速やか(おおむね7営業日以内)にスキャナ保存する(早期入力方式) ➁ それぞれの企業において採用している業務処理サイクルの期間(最長2か⽉以内)を経過した後、速やか(おおむね7営業日以内)にスキャナ保存する(業務処理サイクル方式) ※ ➁の業務処理サイクル方式は、企業において書類を作成または受領してからスキャナ保存するまでの各事務の処理規程を定めている場合のみ採用できます 一般書類の場合は、入力期間の制限なく入力することもできます(注) |
|
| 一定の解像度による読み取り | 解像度200dpi相当以上で読み取ること | |
| カラー画像による読み取り | 赤色、緑色及び青色の階調がそれぞれ256階調以上(24ビットカラー)で読み取ること 一般書類の場合は、白黒階調(グレースケール)で読み取ることもできます(注) |
|
| タイムスタンプの付与 | 入力期間内に、総務大臣が認定する業務に係るタイムスタンプ(※1)を、一の入力単位ごとのスキャナデータに付すこと ※1 スキャナデータが変更されていないことについて、保存期間を通じて確認することができ、課税期間中の任意の期間を指定し、一括して検証することができるものに限ります ※2 入力期間内にスキャナ保存したことを確認できる場合には、このタイムスタンプの付与要件に代えることができます |
|
| ヴァージョン管理 | スキャナデータについて訂正・削除の事実やその内容を確認することができるシステム等又は訂正・削除を行うことができないシステム等を使用すること | |
| 帳簿との相互関連性の確保 | スキャナデータとそのデータに関連する帳簿の記録事項との間において、相互にその関連性を確認することができるようにしておくこと | (不要) |
| 見読可能装置等の備付け | 14インチ(映像面の最大径が35cm)以上のカラーディスプレイ及びカラープリンタ並びに操作説明書を備え付けること 白黒階調(グレースケール)で読み取った一般書類は、カラー対応でないディスプレイ及びプリンタでの出力で問題ありません(注) |
|
| 速やかに出力すること | スキャナデータについて、次の➀~➃の状態で速やかに出力することができるようにすること 1 整然とした形式 ➁書類と同程度に明瞭 ➂拡大又は縮小して出力することができる ➃4ポイントの大きさの文字を認識できる |
|
| システム概要書等の備付け | スキャナ保存するシステム等のシステム概要書、システム仕様書、操作説明書、スキャナ保存する手順や担当部署などを明らかにした書類を備え付けること | |
| 検索機能の確保 | スキャナデータについて、次の要件による検索ができるようにすること ➀ 取引年⽉日その他の日付、取引金額及び取引先での検索 ➁ 日付又は金額に係る記録項目について範囲を指定しての検索 ➂ 2以上の任意の記録項目を組み合わせての検索 ※ 税務職員による質問検査権に基づくスキャナデータのダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合には、➁及び➂の要件は不要 |
|
(注)一般書類向けのルールを採用する場合は、事務の手続(責任者、入力の順序や方法など)を明らかにした書類を備え付ける必要があります
参考:国税庁「はじめませんか、書類のスキャナ保存」
電子取引
電子データで受領した書類は、原則として電子データのままで保存する必要があります。「電子取引」のデータ保存区分に該当し、「データの不正な改ざんを防ぐこと(=真実性)」と「データをいつでも確認できる状態にすること(=可視性)」の2つの要件を満たすことが求められます。
| 真実性の要件 (1~4のいずれかを満たす必要がある) |
1 タイムスタンプが付された後、取引情報の授受を行う |
|---|---|
| 2 取引情報の授受後、速やかに(又はその業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに)タイムスタンプを付すとともに、保存を行う者又は監督者に関する情報を確認できるようにしておく | |
| 3 記録事項の訂正・削除を行った場合に、これらの事実及び内容を確認できるシステム又は記録事項の訂正・削除を行うことができないシステムで取引情報の授受及び保存を行う | |
| 4 正当な理由がない訂正・削除の防止に関する事務処理規程を定め、その規程に沿った運用を行う |
| 可視性の要件 (すべてを満たす必要がある) |
保存場所に、電子計算機(パソコン等)、プログラム、ディスプレイ、プリンタ及びこれらの操作マニュアルを備え付け、画面・書面に整然とした形式及び明瞭な状態で速やかに出力できるようにしておくこと |
|---|---|
| 電子計算機処理システムの概要書を備え付けること | |
| 検索機能※を確保すること ※帳簿の検索要件①~③に相当する要件(ダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合には、②③不要)保存義務者が小規模な事業者でダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合には、検索機能不要 |
参考:国税庁「電子帳簿保存法が改正されました」
電子帳簿保存法に基づき経費精算に関わる書類をデータ化するメリット
経費精算で取り扱う書類を電子データとして保存すると、経理業務の効率化も実現できます。こちらでは、書類をデータ化する具体的なメリットについて解説します。
コストを削減できる
経費精算をペーパーレス化すると、コスト削減につなげられます。紙の印刷やファイリングなどが不要になるため、印刷代やファイル等の備品代を減らすことが可能です。加えて、保管スペースの確保にかかっていたコストも減らせるでしょう。
業務効率化を期待できる
電子帳簿保存法の要件を満たして電子データ化を行えば、紙の原本を破棄できます。必要書類の検索も容易に行えるようになり、特定の書類を発見しやすくなります。書類管理の効率化を実現できるのは大きなメリットです。
また、データをオンライン上で管理することで、経理担当者と申請者の双方が従来よりも手続きをスムーズに進められるようになるでしょう。経理担当者は、オフィスへ出社せずにオンラインで書類をチェックできるようになります。出張やリモートワークなどで社外にいる従業員は、外出先でスマホで書類を撮影・アップロードし、速やかに経費精算の手続きを完了できます。
加えて、データによるやり取りに切り替えることで、社内の情報を一元管理できるようになり、部署間の情報共有もスムーズになるでしょう。多岐にわたる部署とのやり取りで生じる負担を軽減し、業務効率の向上が期待できます。
紛失や劣化のリスクを低減できる
冒頭でご紹介した通り、経費精算関連の書類は原則として7年の保管が義務とされています。紙の書類の場合、人為的ミスや災害などによる紛失や劣化のリスクがあります。一方で、電子データとして保管すれば、スキャンしたときの状態を維持したまま保管しておける点がメリットだといえるでしょう。
電子帳簿保存法に基づく経費精算書類のデータ化でよくある疑問
経費精算に関する書類をデータ化する際、原本の扱いに頭を悩ませるケースは少なくありません。以下では、よくある疑問や回答をご紹介します。
書類をデータ化したらすぐに原本を破棄して問題ない?
書類を電子データ化した後、すぐに処分してしまいたいと考える方も多いのではないでしょうか。法律上は問題ありませんが、念のために紙の原本は一定期間保存しておく規定を設けるのがおすすめです。スキャン時にトラブルが発生し、内容が読み取れない、または文字が切れる場合があります。できれば精算が完了するまでの間は原本も保管しておくと安心でしょう。
電子データと紙の両方で書類を受領した場合はどうする?
同じ内容が記載された経費精算書類を電子データと紙の両方で受領したら、どちらも保管しておかねばならないケースがあります。例えば、内容に異なる部分がある場合です。
完全に同じ内容であれば、紙を原本として扱い、スキャナ保存するのが一般的です。この場合、電子データとして受け取ったほうは破棄します。
しかし、片方はカラー、片方は白黒といったように異なる部分がある場合、それぞれを原本として保存するパターンが多く見られます。保管の手間が倍になってしまうため、自社内の人員に対し、あらかじめ希望する書類の形式を伝えておいたほうがよいでしょう。
昔の書類をスキャナ保存することは可能?
2022年の電子帳簿保存法改正によって条件が緩和され、紙の原本をスキャナやスマホ撮影で電子化する場合、税務署への届け出は不要となりました。ただし、スキャナ保存の開始日よりも前の書類を保存するのであれば届け出が必要とされています。経費精算書類を遡って整理する際は気をつけましょう。
電子帳簿保存法対応の経費精算システムでさらなる業務効率化へ!
経費精算に関する書類を電子帳簿保存法に従って保存する際、知っておきたいポイントを解説しました。電子帳簿保存法では異なる保存区分が設けられており、それぞれ要件が異なります。要件自体も細かいものが多いため、一つひとつ確認しながら保管するのは大変手間がかかります。
そんなときは電子帳簿保存法に対応した経費精算システムを活用するのがおすすめです。システムを導入すれば、要件を満たしながら手軽に書類を保存できるでしょう。これから経費精算業務の効率化を図るなら、電子帳簿保存法に対応した「楽楽精算」をご検討ください。
「楽楽精算」の特徴➀ 電子帳簿保存法に対応している
領収書やレシートなどの写真を撮影してアップロードするだけで、簡単に保存要件を満たした書類保管を実現できます。法改正があれば、システム側が新たな要件に対応したアップデートを実施するため安心です。メンテナンスなどの手間も不要で、継続的かつ長期間の運用が可能です。
「楽楽精算」の特徴➁ 受領形式を問わずスムーズに保管できる
紙や電子データなどの受領形式を問わずに社内の書類を一元管理できます。文書管理業務がスムーズになり、利便性や業務効率が高まります。
「楽楽精算」の特徴➂ 経費申請された情報は自動で仕訳される
申請された情報の自動仕訳や、振り込みデータの自動作成などに対応しています。会計ソフト用の仕訳データを自動生成でき、手作業を減らせるため、人為的なミスの削減につなげられるでしょう。経費申請の自動化を進められる点も魅力です。
「楽楽精算」の特徴➃ カスタマイズ性が高い
システム側のカスタマイズ性が高いので、自社の業務に合わせて柔軟に業務フローを組み立てられます。既存の業務フローを大きく変えることなく、スムーズに導入しやすいのもポイントです。
「楽楽精算」の効率化機能やプラン料金など、気になる場合はお気軽にお問い合わせください。
「楽楽精算」の
資料をメールでもらう

電子帳簿保存法対応!経費精算システム「楽楽精算」の製品概要や導入メリット、機能などが詳しくわかる資料をメールでお送りします。
この記事を読んだ方におすすめ!
オススメの人気記事
記事執筆者紹介

「楽楽精算」コラム編集部です。
経理担当者様の日々の業務にプラスとなるお役立ち情報
「楽楽精算」最新情報をお届けしていきます!
使い勝手が気になる方へ。