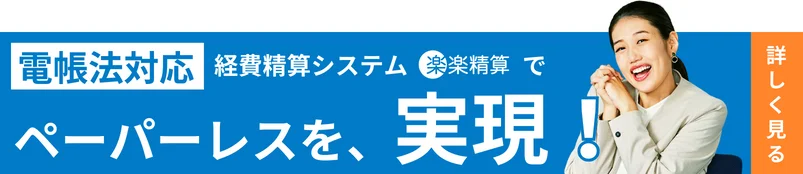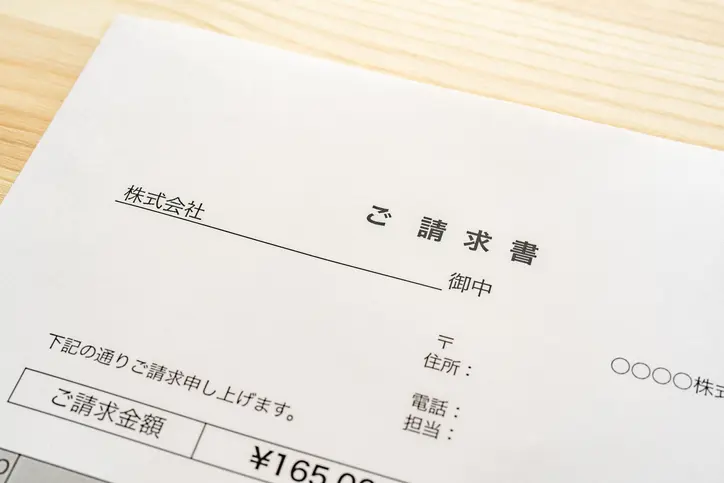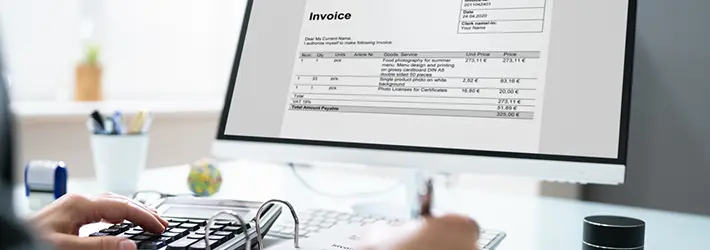経費精算した領収書はどのように保管する?法律上のルールや管理方法

経費精算の手続きでは、領収書の提出を義務付けている企業が多いと思います。申請内容の正確性を確認するためです。では、立て替えた経費の支払いが完了した後、領収書はどのように取り扱えばよいのでしょうか。
この記事では、経費精算後の領収書の保管ルールや、経理業務を効率化する方法まで基礎知識を解説します。現状の領収書の保管方法を見直し、業務効率化を実現したい経理担当者の方は、ぜひ参考にしてみてください。
この記事の目次
経費精算を終えた領収書はなぜ保管する必要がある?
社内で経費精算の手続きを終えた後も、領収書は一定期間にわたり保存する必要があります。その理由は、税務調査などで領収書を確認する可能性があるためです。場合によっては取引先とトラブルが発生した際に、使う可能性も考えられるでしょう。領収書は経費精算後も適切な方法で保管する必要があります。
そもそも領収書は“法律”で保存が義務付けられている国税関係帳簿書類の一つです。国税関係帳簿書類には、領収書・注文書・契約書・見積書・納品書といった種類の書類が含まれます。これらの書類には企業間の取引情報を記録する意味合いがあるため、一定期間保存しなければならないのです。なお、領収書の具体的な保存期間のルールについては次の見出しで詳しく解説します。
万が一、領収書がルールに基づいて適切に保管されていないことが発覚した場合、企業はペナルティを科されるおそれがあります。例えば会社法第976条においては、国税関係帳簿書類の保管ルールを守らない悪質なケースに対して、100万円以下の過料が科されるとされています。経費精算後もこうした注意点を押さえて関係書類の管理を徹底しましょう。
(過料に処すべき行為)
第九百七十六条
四 この法律の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写又は書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
経費精算を終えた領収書の保管に関する法律上のルール
先ほど述べた通り、経費精算を終えた後の領収書の保管方法に関しては法律上でルールが定められています。経理担当者の方はしっかりと理解しておきましょう。
ここでは、以下の3つについて解説します。
➀保存期間のルール
➁保管形式のルール
➂保管していた領収書を紛失したときのルール
➀保存期間のルール
領収書は法律で決められた期間保管する必要があります。原則として法人は7年間、個人事業主の場合、青色申告は7年間、白色申告は5年間にわたり領収書を保管するのがルールとなっています。
ただし、繰越欠損金の有無や仕入税額控除の適用によって期間が変わるため、以下の表で確認しておきましょう。
| 事業形態 | 欠損金の繰越控除の利用 | 保管期間 |
|---|---|---|
| 法人 | なし | 7年 |
| あり | 10年 | |
| 個人事業主(青色申告) | なし | 7年 |
| あり | 10年 | |
| 個人事業主(白色申告) | - | 5年 ※仕入税額控除の適用を受ける場合は7年 |
| - | 5年 ※仕入税額控除の適用を受ける場合は7年 |
【補足】保管期間が原則と異なるケース
・欠損金繰越控除制度を利用する場合
「欠損金繰越控除制度」は法人税の税負担を平準化し、設立から間もない法人などの安定をはかる制度です。事業年度の決算で赤字が発生した際、一定期間にわたり将来の所得と相殺し、法人税の負担を抑えることができます。青色申告の事業者が欠損金繰越控除制度を利用すると、領収書の保管期間が10年間になるのがポイントです。
・仕入税額控除の適用を受ける場合
仕入税額控除とは、仕入れにかかった消費税を控除し、課税の重複を防ぐ制度です。白色申告の事業者は、原則として5年間の領収書の保存が義務付けられていますが、仕入税額控除を受ける場合の保存期間は7年間となるため注意しておきましょう。
➁保管形式のルール
電子データで領収書を保管する場合は、「電子帳簿保存法」により細かくルールが定められています。電子帳簿保存法は、大きく以下の制度に分けられます。
【電子帳簿保存法の区分】
*電子取引
*電子帳簿・電子書類
*スキャナ保存
特に注意すべきなのは、「電子取引」の制度における電子データとして受け取った領収書は、電子保存しなければならないというルールです。
電子データを紙に印刷して保管する方法は認められていないので注意しましょう。
なお、領収書を紙で受け取るケースでは、紙と電子データのどちらの形式で保存しても問題ありません。しかし、紙の領収書はスキャナなどで電子化してしまうのがおすすめです。電子化すれば、紙の原本を処分できるため保管にかかるコストを削減できます。
➂保管していた領収書を紛失したときのルール
領収書は紛失のリスクを避けるためにしっかりと整理して保管することが大切です。しかし、紙の領収書の紛失や破損を完全に避けるのは難しいといえます。万が一、領収書を紛失してしまった場合は「取引先に領収書を再発行してもらう」もしくは、「レシートにより代替する」といった方法で対処しましょう。
上記での対処が難しいのであれば、領収書と同様の内容の出金伝票を作成し、領収書なしで処理するのも一つの対処法です。ただし、一般的に税務調査では不正防止の観点から出金伝票に不審な点がないか厳しく調査される傾向にあります。
領収書を効率的に保管する方法
ここまでお伝えしたように、領収書は長期間保管する必要がある書類です。また、日々の経理業務や税務署による調査で内容確認の必要が生じたとき、速やかに目的の書類を取り出せることも重要となります。
こうした理由から、領収書は検索性が高く、かつ紛失・破棄のリスクが低い電子データで保管するのがおすすめです。
電子データの領収書は、紙の領収書と比べて検索性が高いのが特長です。デジタル化すれば、日時・宛名・内訳・取引金額などで検索をかけて、該当する書類をすぐに見つけられます。例えば、ファイル名の付け方を統一して「202407_接待交際費_領収書_●●事業部」といった形で揃えると、膨大な領収書のデータを整理しやすくなります。
また、保管スペースを確保する必要がなく、ファイリング作業の工数がかかりません。電子化すれば保管にかかるコストを削減できます。また、電子データであれば書類が劣化しないのもポイントです。
なお、請求書の保管方法については、以下の記事で詳しく解説しています。参考にしてみてください。
経費精算で重要な領収書は正しい保管期間を守って管理しましょう!
ここまで、領収書の保管期間について解説しました。領収書の保管期間は、原則法人で7年間、青色申告の個人事業主で7年間、白色申告の個人事業主で5年間となっています。保管期間が原則と異なるケースもあるため、自社がどれに該当するのか確認してみましょう。このほかに保管形式にもルールがあり、書類の種類や受領形式によってルールが変わるため、一度国税庁のサイトを確認しておくようおすすめします。
参考:国税庁「電子帳簿等保存制度特設サイト」
領収書の電子化を考えた際、法要件を守りながら保管するのにハードルを感じる担当者の方も多いでしょう。そこでおすすめなのがシステムの導入です。法要件に対応したシステムを活用すれば、複雑なルールを一つひとつ精査する手間を減らして社内に展開することができます。
システム導入を検討する際、数あるサービスのなかでもおすすめなのはクラウド型経費精算システム「楽楽精算」です。
「楽楽精算」は、検索機能を搭載し、修正・削除の記録が残る電子帳簿保存法に対応したシステムです。スキャナ保存にも対応できるため、形式を問わず保管の仕組みを構築できます。
また、保管の効率化だけではなく、経費の申請から承認まで業務全体を効率化できるのも魅力です。書類の記入やチェックの作業を自動化する便利な機能が充実しています。
さらには電子帳簿保存法だけでなく、インボイス制度にも対応しているので、各種法律への対応も安心です。
「楽楽精算」の機能や導入メリットについて詳しくは無料の資料でご案内していますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
「楽楽精算」の
資料をメールでもらう

電子帳簿保存法対応!経費精算システム「楽楽精算」の製品概要や導入メリット、機能などが詳しくわかる資料をメールでお送りします。
この記事を読んだ方におすすめ!
オススメの人気記事
記事執筆者紹介

「楽楽精算」コラム編集部です。
経理担当者様の日々の業務にプラスとなるお役立ち情報
「楽楽精算」最新情報をお届けしていきます!
使い勝手が気になる方へ。