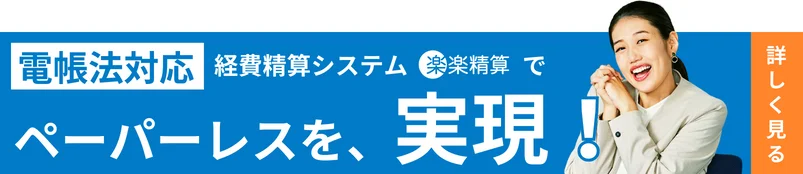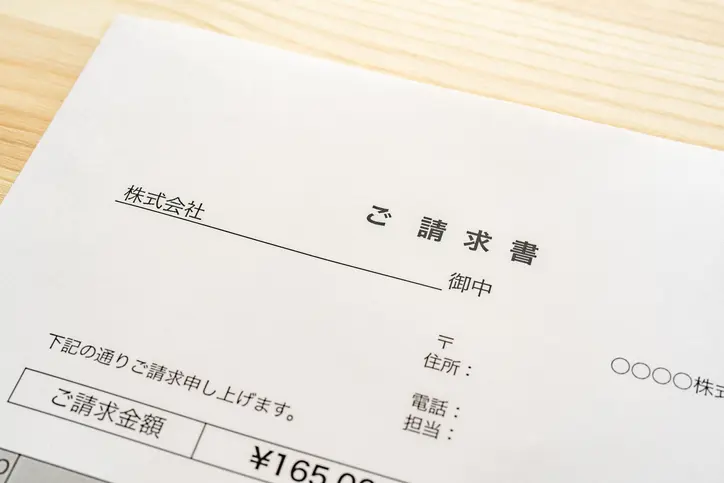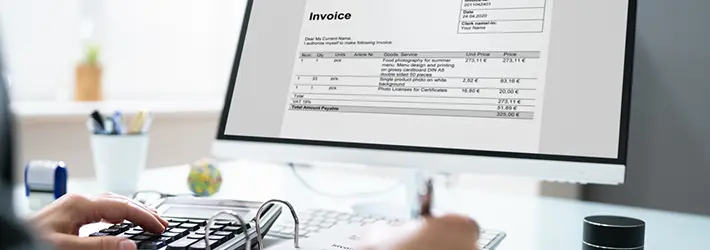経費精算で領収書が必要な理由とは?紛失してしまったときの対処法
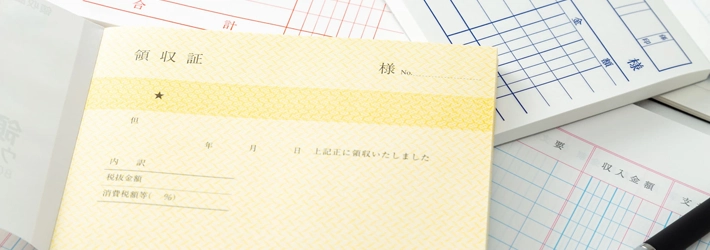
多くの企業の社内ルールでは、経費精算で領収書の提出が必須とされています。では、なぜ経費精算では領収書を提出する必要があるのかご存じでしょうか?
この記事では、経費精算における領収書の必要性を解説します。また、領収書を紛失した場合の対処法や経費計上での注意点にも触れるため、経理担当者の方はぜひ参考にしてみてください。
この記事の目次
そもそも経費精算で領収書はなぜ必要?
経費精算では領収書の提出が必須とされています。そもそもなぜ領収書が必要なのでしょうか。
主な理由として、以下の3つが挙げられます。
- 二重払いや過払いを防ぐため
- 不正な申請を防ぐため
- 経費申請された内容のファクトを確認するため
それぞれの理由について、詳しく解説します。
二重払いや過払いを防ぐため
領収書の提出を必須とすることで、経費精算における二重払いや過払いなどのミスを防ぎやすくなります。領収書の添付がある場合のみ経費の立替を行う運用体制であれば、経費を重複して支払ったり、誤った金額で支払ったりするリスクを減らせます。領収書は経費精算の正確性を高める上で大切な書類だといえるでしょう。
不正な申請を防ぐため
原則として領収書なしでの申請を認めない運用にすることで、存在しない虚偽の申請を見抜きやすくなり、社内不正の抑止につながります。領収書は商品・サービスに対して金銭を支払った事実を証明する公的な書類です。経費精算においては、従業員が「何を購入したのか」「いくら支払ったのか」を客観的に証明し、虚偽の申請を防ぐ役割があります。
経費申請された内容のファクトを確認するため
領収書に明記された取引の日付・支払先・用途などを参照することにより、経費が発生した事実を確認できます。領収書の記載内容から、「業務に関係する費用であるか」「使用した金額に誤りはないか」などを証明することが可能です。万が一、税務調査で指摘を受けた際は、領収書を根拠として提出できます。こうした背景から、適切な保管方法や保存期間を守って領収書を管理することが重要です。
経費精算でレシートではなく領収書が求められる理由は?
法律上では、領収書とレシートに明確な違いはありません。そのため、社内でレシート(利用明細)による経費精算が認められていない場合は、会社独自に定められたルールであると考えられるでしょう。
領収書には宛名が明記されており、かつ感熱紙に印字されたレシートと比べて耐久性が高い傾向にあります。こうした特徴から領収書のほうが手続きに適しているとされ、経費精算の必要書類として推奨されているケースが少なくありません。
なお、領収書の書き方には法的なルールがないものの、基本的には以下の4点が記載されていることが重要となります。
【領収書の主な記載項目】
- 取引先の氏名、名称
- 取引を行った年月日
- 取引した内容
- 取引した金額
経費精算で金銭の受領を証明する場合は、一般的に必要とされる記載項目が含まれているか確認しておきましょう。
【POINT】領収書とレシートの違い
領収書とレシートの主な違いは以下です。税法上の観点からは、領収書とレシートの間に違いはありません。
- 領収書には宛名がある
- 領収書は手書きで発行する場合があるが、レシートは自動印字で発行する
- レシートは感熱紙という熱によって色が変化する紙に印字されているため、耐久性に劣る
領収書は手書きで発行する場合があり、機械によって自動印字されるレシートのほうが正確性には勝るとされます。ただし、レシートは感熱紙に印字されている都合上、耐久性が低く、適切に保存しても数年で印字が薄くなってしまう可能性があります。そのため、経費精算では領収書の方を優先する企業が多いです。
経費精算で起きがちな問題①領収書(レシート)を紛失した場合どうすればよい?
経費精算には領収書やレシートが必要ですが、従業員が領収書やレシートを紛失してしまった、というトラブルは少なくありません。そこで、領収書やレシートを紛失した場合の対処法について解説します。
なお、レシートも領収書と同様に支払いの証明の要件を満たしています。もし領収書をなくしてもレシートがあれば基本的には問題なく経費精算を行うことが可能です。
取引先に領収書の再発行をお願いする
一般的に対応してもらえる可能性は低いものの、取引先によっては領収書の再発行を受け付けてもらえる場合があります。ただし、領収書の再発行は脱税などに不正利用されるリスクがあるので、基本的には再発行を受け付けていない会社が多いです。そもそも領収書は再発行義務がないため、取引先への依頼は控えめにし、強要は避ける必要があります。
出金伝票を作成する
領収書を再発行できない場合は、出金伝票を作成して代用する方法があります。その際は、領収書の紛失が判明した段階で、「取引先の氏名や名称」「取引日時(年月日)」「取引した内容」「取引した金額」をメモして記録に残しましょう。これらの記載事項を出金伝票や会社の所定の書類に記入し、その取引が事実であると認められた場合は、税務上で経費処理を行うことが可能です。
なお、インボイス制度の導入前は、30,000円未満(税込)の仕入れの場合に領収書や請求書がなくても仕入税額控除が認められていました。ただし、2023年10月にインボイス制度が施行された後は、原則として30,000円未満(税込)の仕入れでも領収書や請求書の保存が必要となった点に注意が必要です。
経費精算で起きがちな問題②領収書の宛名が空欄…!
お店によっては、領収書の宛名欄を空欄のまま渡す場合や、「上様」と記入して渡す場合があります。このように宛名が空欄の領収書や、宛名が「上様」の領収書でも、税法上は問題なく処理することが可能です。
ただし、宛名が空欄の領収書は、税務署でチェックを受ける場合に注意が必要となります。例えば「私的に利用した領収書が混ざっていないか」「本当にその会社の事業で必要なものを購入したか」という観点から見ると、宛名が空欄だと不信感を持たれる可能性があるでしょう。
具体的な経費の目的をしっかりと証明できるのであれば、宛名が空欄の領収書であっても問題ありません。一方で、基本的には宛名欄に会社名を記入するのが望ましいので、社内規程で宛名に関するルールを設けている企業が多いです。
経費精算で起きがちな問題③領収書に収入印紙が貼られていない
領収書の記載金額が5万円以上のときは、発行側が受取金額に応じて収入印紙を貼付し、消印する必要があります。課税文書を発行した場合、発行者は収入印紙の貼付によって印紙税を納める義務があるためです。
そのため、受領した領収書に収入印紙が貼られていない場合は、受領側から発行側へ不備を指摘してください。基本的に、領収書の受領側には収入印紙を貼付する義務はないものの、取引先が印紙税法に違反することがないよう、一言伝えるのが望ましいでしょう。
なお、領収書に収入印紙が貼られていない場合、領収書が無効となるわけではありません。受領側は経費処理することが可能です。
経費精算で起きがちな問題④領収書がそもそも発行されない
電車やバスなど公共交通機関の交通費や、取引先のご祝儀や香典などでは、基本的に領収書が発行されません。このように領収書が原則発行されないような場合でも、出金伝票を用いれば問題なく経費処理をすることが可能です。
領収書が発行されないケースでは、まず「取引先の氏名や名称」「取引日時(年月日)」「取引の内容」「取引した金額」をメモに取りましょう。取引の内容としては「ご祝儀」や「香典」などのように記載します。その後、出金伝票に記載することで経費処理が可能です。その際は、税務署のチェックに備えて証拠となる書類を併せて保存しておくとよいでしょう。例えば、電車やバスでの移動経路、結婚式や葬儀の案内状などが挙げられます。
前述したように、インボイス制度の施行後は30,000円未満(税込)の仕入れでも仕入税額控除には領収書や請求書の保存が必要とされています。ただし、電車やバスなど公共交通機関の交通費に関しては、インボイスなしでも仕入税額控除が認められています。
出典:国税庁「適格請求書の交付義務が免除される取引」
領収書を電子化すれば経費精算の業務効率がアップする!
ここまで、経費精算で領収書が必要な理由や、紛失してしまったときの対処法を解説しました。従業員が領収書を紛失するトラブルは、経費精算につきものです。こうしたトラブルの発生を防ぐなら、受領した領収書の保存方法を見直し、速やかに領収書を電子化し、効率的に保管する方法を取り入れましょう。
電子帳簿保存法に対応した専用システムを導入すれば、法要件を満たした環境を整備し、自社の経費精算業務をスムーズに電子化できます。国税関係帳簿書類を電子データ化してシステム上で保存すれば、紙の領収書原本を破棄できるので、ファイリングの手間や保管場所の確保が不要となります。経費精算の業務効率化を実現するために、専用システムを活用して業務フロー全体を電子化するとよいでしょう。
そこでおすすめなのが、経費精算業務の自動化によって経理担当者の負担を軽減する「楽楽精算」です。
特徴① 既存のフローに合わせて電子化できる
経費精算の申請項目・レイアウト・承認フローなどを自由にカスタマイズして、自社の運用に合わせて電子化できます。申請の流れを全体的に電子化すると、「担当者が出社しなくても対応できる」「紙のコスト削減につながる」「書類の検索性が向上する」など多くのメリットがあります。
特徴② 領収書の転載や入力が不要になる
交通系ICカードを専用アプリで読み取る「交通系ICカード取込機能」や、領収書を専用アプリで撮影してデータ化する「領収書読み取り機能」を搭載。スマホからAI-OCR機能で簡単に領収書を電子化でき、申請の手間やミスを削減します。
特徴③ 電子帳簿保存法にも対応
「楽楽精算」は電子帳簿保存法に対応したシステムです。法的な要件を満たして領収書など証憑書類の電子データを適切に保存できます。
「楽楽精算」の機能や導入メリットなど、詳しくは無料のダウンロード資料でご紹介しています。どうぞお気軽にお問い合わせください。
>> 経費精算業務がラクになる「楽楽精算」の機能について詳しくはこちら「楽楽精算」の
資料をメールでもらう

電子帳簿保存法対応!経費精算システム「楽楽精算」の製品概要や導入メリット、機能などが詳しくわかる資料をメールでお送りします。
この記事を読んだ方におすすめ!
オススメの人気記事
記事執筆者紹介

「楽楽精算」コラム編集部です。
経理担当者様の日々の業務にプラスとなるお役立ち情報
「楽楽精算」最新情報をお届けしていきます!
使い勝手が気になる方へ。