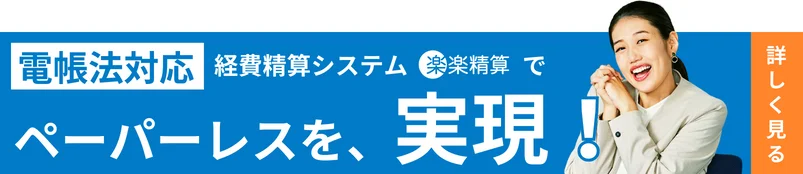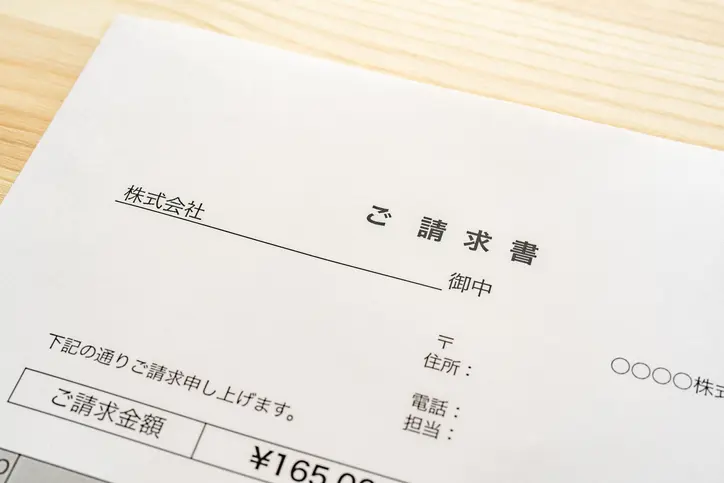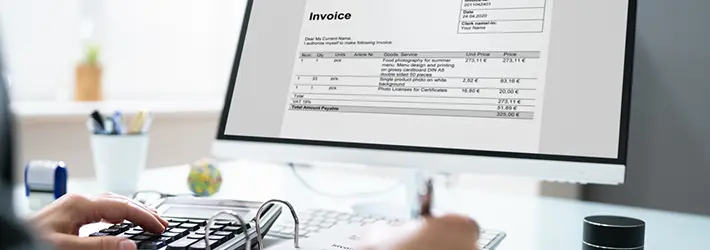経費精算におけるルールの設定目的は?規定作成のポイントや注意点

経費精算をスムーズに進める上で、ルール作りは欠かせません。従業員一人ひとりが独自の判断で経費計上を行うと、不正やトラブルが発生しやすくなるからです。また、不適切な経費計上は経理担当者の負担になるだけでなく、脱税とみなされることもあり、結果的に会社全体の信用が失われてしまいます。
そこで今回は、経費精算のルールを作成する目的や得られる効果、記載すべき項目、作成時の注意点について解説します。経理担当者の方で、経費精算のルール設定に関する概要を知りたい方は、ぜひご一読ください。
この記事の目次
経費精算ルール作成の目的
経費精算のルールを定める目的の1つは、企業の内部統制を強化することです。
内部統制とは、業務の効率性や信頼性を確保し、組織を適正に運営・発展させていくための仕組みです。健全な事業活動を実現するためには、仕組みに沿った運営が不可欠であり、経費精算の業務もルールの下に適切に行われる必要があります。
すべての従業員が経費精算の手順を正しく認識し、自分のやり方が適切であるかチェックできる体制を整備すれば、以下のような効果を期待できるでしょう。
- 各業務のリスクを減らすことができる
- 情報共有も迅速化する
- 業務の有効性・効率性を高めることができる
経費精算のルールを作成することで得られる効果
就業規則にはさまざまな種類がありますが、経費精算ルールの重要度は高いです。ここでは経費精算ルールの作成が必要な理由と得られるメリットについて、より詳しく説明します。
無駄な経費を削減できる
経費とは、本来その企業の事業に必要なものだけに使われるものです。しかし、その経費に関する規定がなければ、業務外のことに経費を使ったり、必要以上の金額を使われたりする可能性があります。経費精算のルールを設けることで経費の無駄遣いを減らし、経費削減を図ることができるでしょう。
法的リスクを避けられる
経費精算のルールがなければ、経費が不正使用されるリスクが高くなり、経費の不正使用があれば、企業が管理責任を問われる可能性があります。経費の不正使用は企業の利益を減らすだけでなく、企業の社会的信用を落としてしまう、法的リスクがあるのです。
経費精算のルールを詳細に定めることで、経費使用の妥当性について誰もが判断しやすくなり、法的リスクを回避できるようになります。
不正受給を防ぐ
きちんと経費精算のルールが定まっていないと、本来は経費とならない内容の申請を行う従業員が現れる可能性も、ゼロではないでしょう。
たとえ誤りであったとしても不正となり、法的リスクもあります。社内規定を設けることは、従業員が適正な範囲や内容で経費申請できるように導く役割もあるのです。
節税対策になる
税制上の措置を活用するためにも、規定を作ることは重要です。節税の例として、接待交際費や出張手当が一部非課税になるルールが挙げられます。具体的には、接待交際費のうち、飲食関連の費用は1人頭10,000円(税抜)以下であれば、会議費として経費計上できるのです。また、出張旅費規定にもとづいて支払われた出張手当は、所得税の課税対象外になります。
経理部門の手間を軽減できる
経費精算でありがちなのが、経費の発生から長期間経過して領収書などを提出するケースです。お金の動きが把握しにくく経費精算処理も煩雑になり、経理担当者にとっての負担も大きいです。
経費精算のルールで、領収書の提出期限や経費の申請期限を設けることで先延ばしを防ぐことができ、経理担当者の手間を軽減することができるでしょう。
社員間の不公平感を解消できる
社内の経費精算ルールがなければ、申請先の経理担当者によって判断が異なり、承認されるか否かが異なるケースもあるでしょう。また、申請者の役職が経理担当者よりも上の場合など、本来承認できない申請内容でも否認しにくいというケースも考えられます。
経費精算に関するルールがあれば、承認・否認の根拠が明確になるため、経理担当者や申請者によって承認結果が変わってしまうトラブルを防ぐことができ、社員間における不公平感も解消されるでしょう。
経費精算のルールに記載するべき項目
経費精算規定の書き方は会社によって違いますが、必要な記載項目を網羅することは大切です。一般的に、通常の経費精算における7つの項目に分けてルールを整理すると抜け漏れが減ります。
①精算できる経費の範囲
経費として適用される範囲を定めます。基本的に業務上必要なものは経費と認めますが、その詳しい範囲は企業によって異なるでしょう。
また、適用対象についても規定が必要です。役員や正社員のみを対象とするのか、非正規社員やアルバイトも含まれるのかを決めましょう。
②上限金額
一度の申請における上限金額を決めましょう。上限金額を超える場合は、事前に稟議書の提出を義務づけるなどの規定を設ければ、事前に動く費用がわかります。
③申請期限
経費の申請や精算は、処理の手間を考えてなるべく早く行うことが理想です。「経費が発生日から翌月の何日まで」など、申請期限を決めておきましょう。
④領収書がない場合の処理方法
公共交通機関の交通費や取引先への結婚祝、慶弔費など、領収書が発行されない経費もあります。また、不備により領収書を紛失してしまうこともあるでしょう。出金伝票で代用するなど、領収書がない場合の対応についても規定しておくことが必要です。
⑤フォーマット
わかりやすい申請書類があれば、申請の不備やミスを減らす効果が期待できます。スムーズな経費精算を実現できるよう、フォーマットを用意することをおすすめします。
⑥自己決裁の禁止
決裁権限を持つ従業員が、自分の申請を承認する自己裁決は、不正請求の原因となります。そのため、自己裁決を禁止し、申請にはほかの決裁者の承認が必要というルールを設けましょう。部下が上司の言いなりに申請を承認してしまうことを防ぐためにも、できるだけ上席に承認をもらう仕組みを作ります。
⑦例外の禁止
経費申請の例外を一度でも認めてしまうと、従業員間の不公平感が増し、規定が形骸化してしまいます。例外は一切認めないようにしましょう。
経費精算のルールを作成するときのポイント
経費精算のルールで重要なのは、あいまいな部分を極力減らしていくことです。ルールの大枠を作った後は、以下のような経費別の細かな規定を設定しましょう。
- 交通費規定
- 出張費規定
- 交際費規定
- 広告費規定 など
経費ごとの特性を鑑みた個別のルールを作ることで、大枠だけではカバーしきれない部分を明確にします。
例えば、以下のようなイメージです。申請をスムーズにするために、経費によってフォーマットを変えるのも効果的です。
【交通費規定の場合】
通勤手当の限度額は『月5万円』と上限を明確にする
【交際費規定の場合】
『年月日や利用した飲食店の名称、所在地、参加人数、参加した人の氏名や所属する組織』などの情報を経費精算申請書に記載する
経費精算システム「楽楽精算」ならルールに沿った申請がラクにできる!
ここまで経費精算のルールについて、目的や内容をご紹介しました。ルールを設定すると、正しく運用されているかのチェックが必要です。経費精算システムを使うことで、チェックにかかるコストを大幅に削減できます。経費精算でありがちな課題に対して、どのようにシステムを活用できるか見ていきましょう。
課題1 規定通りの申請になっているかの確認が大変…
自社に適切な経費精算ルールがあったとしても、申請が規定通りに行われるとは限りません。例えば、経費精算の中でも煩雑になりがちな交通費精算においては、定期区間の控除や最安値経路での申請がされているか注意して確認する必要があります。
課題2 申請ミスが多い…
ルールの理解があいまいな社員は、申請ミスが多くなりやすいです。上司や経理担当者からの差し戻し、再チェックの手間がかかります。
以上のように、従来型の業務フローでは、申請者や承認者にさまざまな手間が発生します。これらの負担を軽減したい場合は、クラウド型の経費精算システム「楽楽精算」のご活用をおすすめします。「楽楽精算」には以下のような便利な機能が備わっているほか、カスタマイズ性に富んでいる点が特徴です。企業独自のルールにも対応しやすいため、複雑な経費精算ルールやチェック作業の効率化が期待できます。
規定違反チェック機能(カスタムチェック)
社員の経費申請に不備があった際に、自動で規定違反の通知と申請ブロックをする機能です。経費申請のチェックや差し戻しにかかる時間を削減できます。
領収書読み取り
光学文字認識機能という技術により、領収書やレシートを撮影するだけで記載された情報をデータ化できます。取引先や受領日などの転記が不要となるため、精算漏れや記入ミスの防止に効果的です。
交際費精算
接待交際費や飲食費の精算をサポートする機能です。1人当たりの単価を計算したり、勘定科目の選択ミスを少なくしたりする効果があります。
「楽楽精算」は金融業界のように、内部統制・セキュリティ基準が高い企業様にもご活用いただいております。カスタマイズや業務改善の詳しい内容は以下の事例を参考にしてください。
トラブル回避と経費精算の効率化のためにもルール設定は大切
健全な組織を作るためには、適切な経費精算ルールを用意することが重要です。精算方法に関する明確な基準を定めることで、日々の経費管理を円滑にし、不要な支出や法的リスクを回避できます。本記事でご紹介した記載項目やポイントを押さえつつ、適切なルールを規定してみてください。
一方で、ルールを作成するだけでは精算業務に関連する業務負担は軽減しません。経理担当者はルールに沿った運用ができているかチェックする必要がありますし、不適切な申請があれば差し戻しを行う必要があるためです。
これらの確認作業を自動化したい場合は、経費精算システムの利用をおすすめします。中でも、カスタマイズ性に優れる「楽楽精算」なら、会社ごとに異なる規定にも対応可能であり、煩雑になりがちな確認作業を効率的かつ正確に実行できます。資料請求は無料です。まずはお気軽にご連絡ください。
「楽楽精算」の
資料をメールでもらう

電子帳簿保存法対応!経費精算システム「楽楽精算」の製品概要や導入メリット、機能などが詳しくわかる資料をメールでお送りします。
この記事を読んだ方におすすめ!
オススメの人気記事
記事執筆者紹介

「楽楽精算」コラム編集部です。
経理担当者様の日々の業務にプラスとなるお役立ち情報
「楽楽精算」最新情報をお届けしていきます!
使い勝手が気になる方へ。