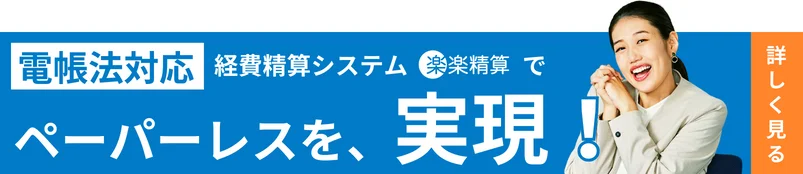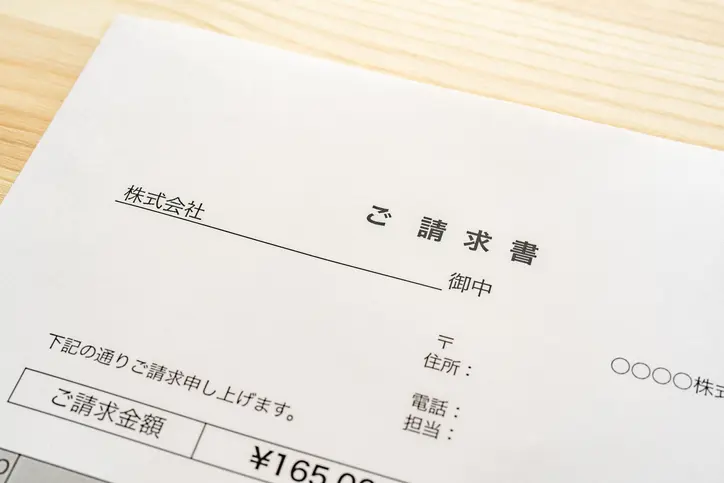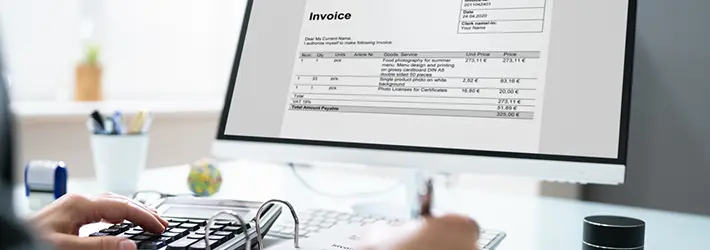【保存版】必要経費一覧!経理担当が押さえるべき項目と勘定科目の使い分け

日々の経費精算業務の中で、見慣れない経費の処理に直面し、「この支出は経費になるのだろうか?」「もし間違っていたら税務署に指摘されるのでは…」といった不安を感じた経験のある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
経費の処理を誤ると、税務調査で追徴課税の対象となったり、意図しない申告漏れが発生したりするリスクがあります。
この記事では、そうした経理担当者の悩みを解消するため、法人・個人事業主で認められる必要経費の種類と、その判断基準を詳しく解説します。本記事を読み終える頃には、業種に応じた必要経費の全体像を把握し、適切な仕訳や申請ができるようになるでしょう。
この記事の目次
必要経費の基本知識
必要経費の定義と考え方(法人・個人共通)
必要経費とは、売上や収益を得るために直接的または間接的に必要となった支出を指します。重要なのは、「業務に関連しているか」という点です。例えば、製造業であれば原材料の仕入れ費用、IT企業であればサーバー利用料や開発ツールの購入費用などがこれに該当します。
税務署が経費をチェックする際に重視するのは、私的利用との線引きです。個人的な支出と事業上の支出が混同されていないか、その支出が本当に事業活動に不可欠だったのかを厳しく確認します。経費として計上する際は、その支出が「なぜ業務に必要なのか」を合理的に説明できるよう、具体的な根拠(領収書、契約書、活動記録など)を残しておくことが不可欠です。
法人と個人事業主の必要経費で異なる点
必要経費の基本的な考え方は法人も個人事業主も共通ですが、いくつか異なる点があります。それぞれの違いについて解説します。
給与の扱い
法人の場合、役員や従業員に支払う給与は「給与手当」として経費になります。一方、個人事業主の場合、事業主自身に支払う給与は経費になりません。これは、個人事業主の生活費と事業所得が一体と見なされるためです。
家事按分
個人事業主が自宅の一部を事務所として利用したり、自宅のインターネット回線を仕事でも使ったりする場合、家事と事業の両方に係る費用を、事業で使用した割合に応じて経費として計上することができます。これを「家事按分」と呼びます。一方で、法人の場合は、会社名義での契約が基本となるため、家事按分の考え方は原則として生じません。
支出の線引き
法人の経費はあくまで「会社」に帰属するものとして、会社名義での支出が原則です。対して、個人事業主の場合は、事業主個人の支出と生活費との線引きが特に重要になります。事業用の銀行口座やクレジットカードを使い分けることで、混乱を避けやすくなるでしょう。
必要経費の一覧(カテゴリ別)
ここでは、法人や個人事業主が一般的に計上できる主な必要経費をカテゴリ別に解説します。
交通・出張費
交通・出張費は、事業に関連する移動や出張にかかる費用です。主に以下の費用が該当します。
- 電車代、バス代、タクシー代:クライアントとの打ち合わせ、仕入れ、展示会への参加など、業務のための移動費用
- 出張時の宿泊費:遠方への出張で宿泊が必要な場合のホテル代や旅館代など
- レンタカー代・ガソリン代:事業で使用する車両の費用
ガソリン代については、自家用車を事業で利用する場合は、走行距離などに基づいた家事按分が必要です。
また、日帰り出張の食費は基本的に個人の飲食と見なされ、原則として経費になりにくいケースが多いです。ただし、接待交際費として認められる特定のビジネス飲食は例外となります。
関連記事:交通費精算のやり方や申請時の注意点|経理業務でよくある課題とは?
通信費・水道光熱費
通信費・水道光熱費は、事業運営に必要な通信サービスやエネルギーにかかる費用です。
電話代・インターネット代
事業用の携帯電話料金やインターネット回線費用が該当します。自宅兼事務所の場合は、業務用割合で家事按分が必要です。
郵便料金・宅配便料金
契約書や商品の発送にかかる費用です。
水道光熱費
事務所や店舗で使用する電気代、ガス代、水道代。自宅兼事務所の場合は、事務所として使用している面積や時間に応じて家事按分を行います。
関連記事:勘定科目「通信費」とは?該当する経費や仕訳の例、注意点について
消耗品費・備品費
消耗品費・備品費は、主に事業で使用する物品の購入費用です。
消耗品費
消耗品費は、使用期間が1年未満、または取得価額が10万円未満の物品の購入費用です。 具体的には、以下のような物品が挙げられます。
- 文房具(ペン、ノート、ファイルなど)
- コピー用紙、インクカートリッジ
- PC周辺機器(マウス、キーボード、USBメモリなど)
- 清掃用品、事務用品
備品費
取得価額が10万円以上の物品は、原則として「資産」として計上し、複数年にわたって費用化する減価償却を行います。ただし、青色申告法人や青色申告の個人事業主の場合、30万円未満の減価償却資産は「少額減価償却資産の特例」により、その年の費用として一括計上できます。
参考:国税庁「No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」
接待交際費
接待交際費は、得意先や仕入れ先など、事業に関係のある方への接待、贈答などにかかる費用です。
- 得意先との会食費:事業に関する情報交換や関係構築を目的とした飲食代
- 贈答品:お歳暮、お中元、開業祝いなどの購入費用
飲食代の上限と記録要件
法人の場合、資本金1億円以下の企業は、年間800万円までか、飲食費の50%までを経費にできます。個人事業主には上限がありません。いずれの場合も、「誰と、いつ、どこで、何のために飲食したのか」を詳細に記録し、領収書と共に保管することが重要です。
会議費
会議費は、社内会議や取引先との打ち合わせに必要な費用です。
- 社内会議のお茶代・軽食代:会議中に提供する飲食物の購入費用は、会議費に含まれます。
- 取引先との打ち合わせの際の喫茶代:カフェなどでの打ち合わせ費用も、会議費に含まれます。
接待交際費との線引き
会議費は、あくまで「会議の進行上必要な費用」であり、飲食が主目的ではないことがポイントです。一般的に一人あたり5,000円以下の飲食費であれば会議費として認められることが多いですが、目的や内容によっては接待交際費と判断されることもあります。
広告宣伝費・販売促進費
自社の製品やサービスを広く知ってもらい、売上を増やすための費用です。
具体的には、以下のような費用が該当します。
- チラシ、パンフレット制作費
- Webサイト制作・運用費
- オンライン広告費(SNS広告、リスティング広告など)
- 展示会出展費用
- ノベルティ、景品類: 事業の宣伝を目的とした配布物やキャンペーン景品。
外注費・業務委託費
事業の一部を外部の個人や法人に依頼した場合の費用です。
主な費用の例は以下のとおりです。
- フリーランスへのデザイン、ライティング、システム開発依頼費用
- 士業(税理士、弁護士、社会保険労務士など)への顧問料、報酬
外注費・業務委託費は、支払いの内容によっては、支払い元が源泉徴収を行う必要がある点に注意が必要です。例えば、税理士への報酬を支払う場合は、支払い元が源泉徴収を行います。
源泉徴収義務があるにもかかわらず怠ると、ペナルティの対象になるため、事前に確認が必要です。
福利厚生費
従業員の慰安、医療、健康保持、能力向上、文化活動などのために支払う費用です。
以下のような費用が当てはまります。
- 社員の健康診断費用
- 社内イベント費用(社員全員が対象の懇親会、社員旅行など)
- 慶弔見舞金(結婚祝い、出産祝い、香典など)
福利厚生費に該当するかの判断基準は、「全社員が対象であるか」です。特定の従業員だけを対象とした制度の費用や、福利厚生とは言えない個人的な支出は経費になりません。 原則として、すべての従業員が平等に利用できるものでなければならない点に注意しましょう。
経費として認められにくいグレーゾーンの事例
経費の判断はケースバイケースで、税務署との見解の相違が生じやすい「グレーゾーン」も存在します。経理担当者としては、これらの事例におけるリスクを理解し、適切な対応を検討することが重要です。
ここからは、グレーゾーンに当てはまる具体的な事例をいくつか紹介します。
家族との飲食代
家族との食事は基本的に「家事費」と見なされ、経費にはなりません。しかし、家族が会社の役員や従業員として事業に深く関わっており、その業務に関する明確な打ち合わせや会議が目的であれば、会議費や接待交際費として認められる可能性もあります。
ただし、この場合でも、日時、場所、参加者、会議内容を具体的に記録し、事業関連性を明確に説明できる証拠を残しておくことが必須です。
通勤用スーツ・化粧品
業務で使用する衣類や美容品であっても、私用との区別がつきにくいものは経費として認められにくいのが現状です。一般的なスーツや化粧品は、仕事以外でも着用・使用できるため、「個人的な支出」と見なされることが多いです。
ただし、以下のような場合は例外として経費となる可能性があります。
- 特定の業種で業務上必須と認められる作業着やユニフォーム:建設業の作業服や医療従事者のスクラブなど、特定の業務に特化した衣装。
- タレントやモデルなど、特定の職業で衣装やメイクが直接的に売上につながる場合:業務の性質上、衣装やメイクが「表現の一部」と認められるケース。
これらのグレーゾーンの支出については、税務署との見解の相違が生じるリスクが高いため、支出内容を詳細に記録するのはもちろんのこと、税理士など専門家への相談を検討することをおすすめします。
経費精算ミスを防ぐための実務対策
経費精算におけるミスは、企業の税務リスクを高めるだけでなく、経理業務の効率を低下させてしまうおそれがあります。ここでは、ミスを未然に防ぐための具体的な実務対策をご紹介します。
社内ルールの整備
最も基本的な対策は、社内での経費分類(勘定科目)を明確にし、統一された経費精算のルールを定めることです。具体的なポイントについて、以下で詳しく解説します。
経費の分類表を社内で共有する
どの支出がどの勘定科目に該当するのかを具体例とともに示した「経費精算ガイドライン」のようなものを作成し、従業員に周知徹底しましょう。
経費精算の手順をルール化する
経費精算に関連する領収書やレシートの保存方法、記載すべき事項(例:利用目的、参加者など)を明確に定め、社内で徹底することが重要です。また、電子帳簿保存法に対応した形で保管できているかも必ず確認するようにしましょう。
迷ったときの相談先を周知する
社内の経理部門や顧問税理士など、判断に迷う経費が発生した場合の相談窓口を明確にし、社内で共有しましょう。気軽に質問できる体制を整えることで、誤った計上を防ぎやすくなります。
業種に応じた経費の考え方
業種によって発生する経費の種類や性質は大きく異なります。自社の業種に特有の経費を正確に把握し、適切に計上することが重要です。
具体的な業種とポイントは以下のとおりです。
- 建設業界の場合:材料費、外注費、重機レンタル費用、現場までの交通費などが主要な経費となります。
- IT業界の場合:サーバー費用、ソフトウェアライセンス費用、開発ツールの購入費用、クラウドサービス利用料、エンジニアへの外注費などが多く発生します。
- コンサルティング業界の場合:交通費、出張費、書籍購入費(新聞図書費)、セミナー参加費(研修費)、情報収集のための通信費などが主要な経費です。
業界団体費、専門誌の購読料、特定の機材レンタル費用など、その業種ならではの経費は、漏れなく計上できるようにリストアップしておくことがおすすめです。
経費精算システムの活用
手入力による経費精算は、ヒューマンエラーの温床となりがちです。経費精算ツールの導入は、これらのミスを減らす効果があります。
入力による分類ミスを防止できる
経費精算システムの中には、スマートフォンで撮影するだけで領収書の内容をAIが自動で読み取り、適切な勘定科目に仕訳してくれる機能を持つ製品があります。これにより、従業員の入力負担が減るだけでなく、経理担当者の確認作業も効率化できます。
承認・ワークフローの一元管理でミスを削減できる
経費申請から承認、精算までのプロセスをシステム上で一元管理することで、申請の不備や承認漏れを防ぎ、業務の透明性を高めることができます。
経費精算システムなら「楽楽精算」
数ある経費精算ツールの中でも、「楽楽精算」は、中小企業をはじめとするさまざまな業種の経理担当者から高い評価を得ています。その主な機能と導入メリットを見ていきましょう。
「楽楽精算」の機能1:領収書読み取り機能(AI-OCR)
楽楽精算には、AI-OCR機能があり、専用アプリから領収書を撮影すると、領収書内の金額、取引先や受領日が自動でデータ化されます。そのまま申請に利用できるので、申請者側の手入力の手間・ミスが削減されます。経理知識がない従業員でも正確な申請が可能です。
「楽楽精算」の機能2:ICカード連携機能
楽楽精算は、SuicaやPASMOなどの交通系ICカードを専用アプリにかざすだけで、利用履歴を自動で取り込む機能を搭載しています。さらに、AI入力補助によって過去の精算履歴より訪問先や負担部門などの情報を自動で追記。申請者の手入力作業を極限まで減らします。
「楽楽精算」の機能3:自動仕訳機能
楽楽精算を使えば、申請の内容からそのまま勘定科目や税区分が振り分けられ、自動で仕訳が完了します。立替金や仮払いの仕訳も可能です。
自動仕訳された内容は、「楽楽精算」内の画面上で確認でき、貸方・借方の内容があっているかをチェックするだけで仕訳業務が完了します。
まとめ
必要経費の計上は、企業の節税対策として非常に重要ですが、その判断基準は「業務との関連性」が基本となります。税務調査で指摘を受けないためには、領収書と内容の記録を徹底し、なぜその支出が業務に必要だったのかを明確に説明できる準備をしておくことが不可欠です。
また、日々の経費精算業務の効率化とミス削減のためには、経費精算ツールの活用を積極的に検討することをおすすめします。「楽楽精算」のような経費精算ツールを導入することで、手入力によるミスを防ぎ、経理業務の負担を軽減し、より正確な経費処理を実現できるでしょう。
経費精算システムの導入を検討するなら、どうぞお気軽に「楽楽精算」へお問い合わせください。
「楽楽精算」の
資料をメールでもらう

電子帳簿保存法対応!経費精算システム「楽楽精算」の製品概要や導入メリット、機能などが詳しくわかる資料をメールでお送りします。
この記事を読んだ方におすすめ!
オススメの人気記事
記事執筆者紹介

「楽楽精算」コラム編集部です。
経理担当者様の日々の業務にプラスとなるお役立ち情報
「楽楽精算」最新情報をお届けしていきます!
使い勝手が気になる方へ。