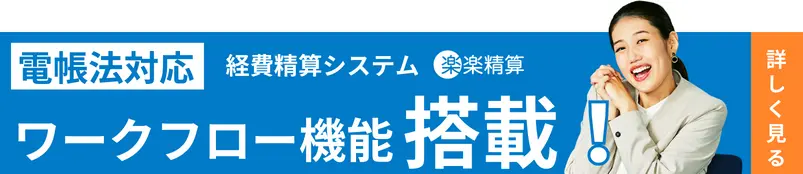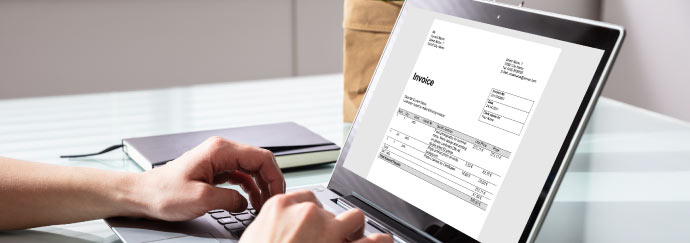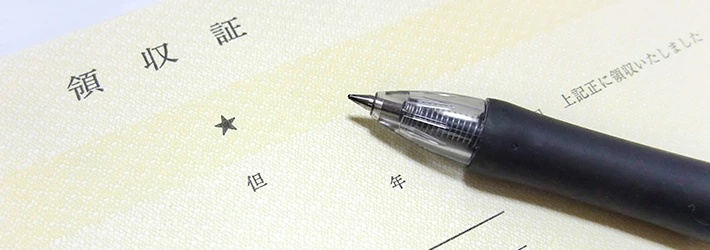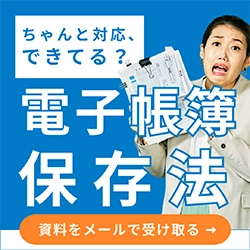「楽楽精算」国税庁公認JIIMA認証取得!電子帳簿保存法対応がより安心に

この記事の目次
「楽楽精算」国税庁公認JIIMA認証取得!電子帳簿保存法対応がより安心に
「楽楽精算」は国税庁公認の機関であるJIIMAの認証を取得しています。(https://www.rakurakuseisan.jp/function/ebooks_maintenanceact.php)このJIIMAの認証とはいったいどのようなものなのか、JIIMA認証を受けている「楽楽精算」を導入するユーザーのメリットはどのようなものかを紹介します。
>> 電子帳簿保存法とは?対応方法と必要なことを分かりやすく解説
国税庁認定の第三者機関「JIIMA」による認証とは?
まず、国税庁が認定している第三者機関JIIMAについてご説明をします。「JIIMA(公益社団法人日本文書情報マネジメント協会)」とはその名の通り、文書情報のマネジメント普及を推進する公益団体です。文書情報マネジメントの中でも特に電子文書の信頼性と文書情報流通基盤の整備、人材育成等を重視しており、これらを通じて電子文書情報社会の構築を目指しています。
このJIIMAでは「電子帳簿保存法スキャナ保存ソフト法的要件認証制度」を設けています。「楽楽精算」はこの認証を受け、国税庁公認の「電子帳簿保存法の求める法的要件に適合している」という“お墨付き”をいただいた経費精算システムです。
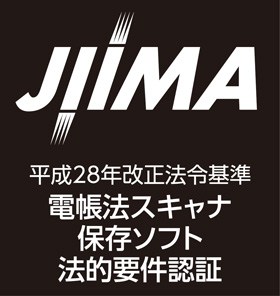
取得日:2019年7月19日
認定機関 公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)
※JIIMA認証を受けた製品のみがこのロゴを使用することができます。
今さら聞けない「電子帳簿保存法」のいろは
前項で「楽楽精算」は「電子帳簿保存法に適合しているという認証を取得した経費精算システムである」とご紹介しました。そこで、電子帳簿保存法について改めて振り返り、「楽楽精算」がJIIMAの電子帳簿保存法認証を受けていることで、どのようなメリットがあるのか確認します。
電子帳簿保存法とはそもそもどういうものか
電子帳簿保存法とは、国税に関する書類の全部、または一部を電子データで保存することを認めた法律です。ただ、この法律の施行当時は、実際の電子帳簿保存法運用に対する規制が厳しく、法律自体は存在しているものの、制度としては形骸化している部分が少なからずありました。しかし、近年の法改正により、電子帳簿保存法が少しずつ実用に即したものになってきており、再度注目を集めています。2022年1月に法改正が行われ、この法改正でさらに電子帳簿保存法運用のハードルが下がりました。2022年の改正については後述します。
電子帳簿保存法導入のメリット
電子帳簿保存法を導入するとどのようなメリットがあるのでしょうか。紙による書類の保存から電子データによる保存に移行した場合のメリットだけでも以下のようなものがあります。
・郵送や印刷のコスト、保管のためのスペースのコスト削減
・書類の紛失や、盗難、情報漏えいなどのリスク低減
・書類の検索性向上、システムを利用する場合の生産性向上 など
紙で書類を保存することに比べて、電子化するだけでもこのようなメリットが得られます。
ただし、どのようなシステムを採用してもこのようなメリットが得られるというわけではありません。電子帳簿保存法に対応して、社内でも国税関係書類の取り扱いを簡素化するためには、正しく電子帳簿保存法の要件を満たしたシステムを選定する必要があります。
電子帳簿保存法の必要要件をもう一度確認
電子帳簿保存法の必要要件とはどのようなものか、今一度確認します。先ほど記載しましたが、電子帳簿保存法にもとづいて、社内の国税関係書類を保存するには、守らなければならない法的な要件があります。
その要件とは非常に大きく分けると「真実性の確保」「可視性の確保」の2つです。その詳細の説明は国税庁のHP(https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/05.htm)をご確認ください。この要件を満たしていなければ、電子帳簿保存法を自社に適用することができません。
また、この要件を満たしていないシステムを利用している場合も当然電子帳簿保存法を適用することはできないので、システムを導入しても、継続して紙での書類管理をする必要があります。
2020年10月に電子帳簿保存法が再改正し要件が緩和
2020年10月施行の電子帳簿保存法改正では、電子帳簿保存法対応要件である「真実性の確保」の条件が緩和されたことが大きな改正点のひとつでしょう。
国税関係書類を電子データ保存するためにはそのデータにタイムスタンプを付与する必要です。以前はそのタイムスタンプは発行者が付与していても、付与していなくても受け取り手の方で付与が必要でした。しかし、2020年10月の改正では発行者がタイムスタンプを付与していれば、受け取り手側ではタイムスタンプの付与が不要になりました。
さらに受け取り手でデータを勝手に改変できないクラウドシステムなどのサービス利用も認められました。これにより経費精算システムを利用する経費精算がますます便利になったので、このタイミングでのシステム検討をされる企業も多かったです。
ただし、電子帳簿保存法対応済みというシステムでJIIMA認証がない場合には以下のような懸念があるので、システム選定は慎重に行うことをおすすめします。
JIIMA認証がないとこんな問題が…
改めて「楽楽精算」はJIIMA認証を受けているので、電子帳簿保存法対応をしたい企業にも安心して利用していただくことができます。しかし、JIIMA認証を受けていないシステムが「電子帳簿保存法対応済み」と表記している場合にはやや注意が必要です。
電子帳簿保存法の要件は大きく分けて「真実性の確保」と「可視性の確保」と説明しましたが、これを紐解くと実際にはより複雑な要件があります。この要件を全て満たしていないと電子帳簿保存法に正しく対応しているとは見なされず、仮にJIIMA認証を受けていないシステムによる運用を開始した場合、国税庁からの税務調査時に不備を指摘されるリスクが大きくなります。
そのため、電子帳簿保存法の対応をしたい企業ではJIIMA認証を受けたシステムを利用することをおすすめしています。
JIIMA認証を受けることで「楽楽精算」と導入ユーザーはどう変わる?
最後に「楽楽精算」がJIIMAの認証を受けていることにより、導入を検討しているユーザーにどのようなメリットがあるのか確認します。
より安心して電子帳簿保存法対応ができる
この記事で何度もお伝えしたとおり、「楽楽精算」はJIIMAによる「電子帳簿保存法スキャナ保存ソフト法的要件認証」を受けています。そのため、電子帳簿保存法対応に際し、国税庁からシステムに関する不備を指摘されるリスクはありません。
システム検討や社内交渉の有利な材料になる
経費精算システムを導入する際に、様々な要素が社内で検討されるでしょう。使用感や費用などは当然ですし、これまでの運用にどれだけ近づけて、社内の反発が少なく導入までこぎつけられるかということも非常に重要です。
近年、領収書等をスマートフォンで写真に撮れば自動的にデータを取り込める機能の精度が飛躍的に向上しており、さらに電子帳簿保存法の改正が進めば、領収書などの電子データによる保存は当たり前のものになってきます。これを考えると、導入段階ですでに電子帳簿保存法に対応できているシステムかどうかということを比較検討するのもまた当然の流れになるでしょう。
その中で、すでにJIIMA認証を受けている「楽楽精算」を選択していただければ、社内での反発もより少なく、スムーズに導入を進めていただけると思います。
経費精算システムの導入を検討する際は、是非今後のトレンドとなる電子帳簿保存法に正しく対応をしているという証拠のあるもの、すなわちJIIMAによる認証を受けているシステムを選択することをおすすめします。
まとめ
今回の記事では「楽楽精算」が国税庁公認のJIIMAによる「電子帳簿保存法スキャナ保存ソフト法的要件認証」を取得していること、そして、それにより電子帳簿保存法対応に際してこれまで以上に安心してご利用いただけるようになったことについてご説明をしました。
JIIMAという国税庁公認の第三者機関が電子帳簿保存法に適合した経費精算システムであると認証している「楽楽精算」を採用して、スムーズな電子帳簿保存法対応を実現目指しましょう。
「楽楽精算」の
資料をメールでもらう

電子帳簿保存法対応!経費精算システム「楽楽精算」の製品概要や導入メリット、機能などが詳しくわかる資料をメールでお送りします。
この記事を読んだ方におすすめ!
オススメの人気記事
記事執筆者紹介

「楽楽精算」コラム編集部です。
経理担当者様の日々の業務にプラスとなるお役立ち情報
「楽楽精算」最新情報をお届けしていきます!
使い勝手が気になる方へ。