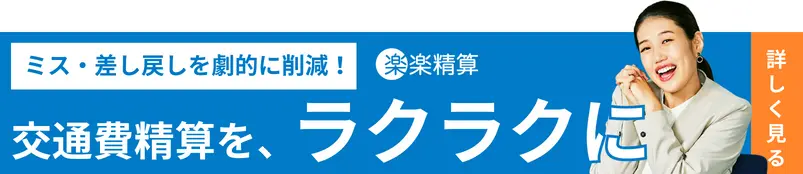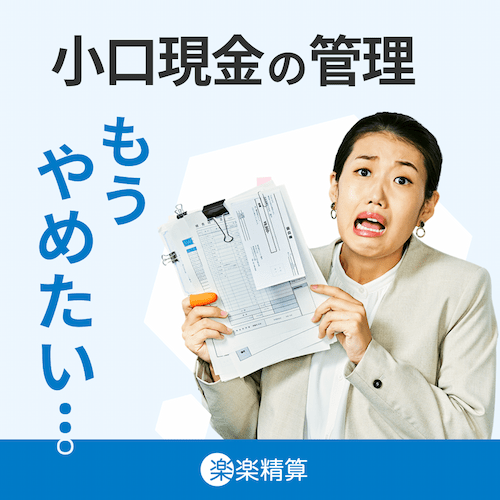交通費と通勤手当では非課税範囲が変わる!限度額や支給の注意点

企業の経理業務では「交通費」と「通勤手当」をそれぞれ扱います。交通費と通勤手当は、いずれも自動車や公共交通機関などの乗り物を利用した移動にかかる費用です。ただし、移動が発生する状況に応じて区別され、課税に関する違いがあります。経理部門の担当者の方は、経費精算の基礎知識として交通費と通勤手当の違いを押さえておきましょう。
この記事では、交通費と通勤手当の違いについて解説します。課税に関する違いから、経理処理で注意すべきポイントまでお伝えするため、ぜひ参考にしてみてください。
この記事の目次
交通費と通勤手当の違いとは?
交通費とは、業務上での移動にかかる経費のことです。具体的には、従業員が取引先を訪問する際や、出張をする際など、鉄道・バス・飛行機といった交通機関を利用したときの料金が交通費として扱われます。交通費の支給方法は、基本的に従業員が一時的に実費を立て替え、後日経費精算を行って立て替えた費用を支払う流れとなります。
一方通勤手当とは、従業員の自宅から勤務先までの通勤費用を補助する手当です。具体的には、従業員の通勤手段である電車やバスの通勤定期券のほか、車通勤におけるマイカーのガソリン代などが該当します。通勤手当は法律において支給義務のある手当ではありません。多くの企業では、従業員の働きやすさにつながる福利厚生制度の一環として通勤手当が支給されています。
通勤手当を支給する際は、金額が一定の範囲内であれば給与所得の対象ではないため、一定額までは課税対象となりません。課税に関する違いは、次の見出しで詳しく解説します。
交通費と通勤手当の課税に関する違い
日本では、給与に対して所得税や住民税などが課税されます。前述した交通費と通勤手当は、それぞれ似ている費用ではあるものの、課税に関して以下の違いがあるので押さえておきましょう。
交通費=非課税
交通費は全額非課税となります。そもそも交通費は、企業が事業活動で利益をあげるために必要な経費に該当します。経費は課税の対象にならないので、交通費も非課税の扱いとなるのです。仕訳する際の勘定科目は、一般的に「旅費交通費」が用いられます。
通勤手当=課税/非課税
通勤手当は一定額まで非課税となります。通勤手当は、あくまでも通勤に必要な費用を補填するために支給される手当です。給与とは支給される目的が異なり、一定額までは非課税の扱いとなります。なお、税区分を区別する必要がない免税事業者などの場合は、勘定科目に「給与手当」を用いて運用しても問題ありません。
一定額を超えた分の通勤手当について
一定額を超えた分の通勤手当は「給与」とみなされ課税対象となる点に注意しましょう。仕訳する際の勘定科目は、一般的に「旅費交通費」が用いられ、課税対象である給与と区別されます。
通勤手当の非課税範囲は?
前述した通り、通勤手当は一定額まで非課税の扱いです。非課税の上限額は通勤方法によって異なります。
区分ごとの通勤手当の非課税限度額は、以下の表のとおりです。
例えば、公共交通機関を利用する場合の非課税限度額は月15万円までです。一方、マイカー通勤や自転車通勤の場合は、通勤距離に応じた非課税限度額が設定されています。
【通勤手当の非課税限度額】
| 区分 | 非課税限度額(平成28年1月1日以降適用) | |
|---|---|---|
| 1.交通機関または有料道路を利用している人に支給する通勤手当 | 1カ月当たりの合理的な運賃等の額(最高限度150,000円) | |
| 2.自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当 | 片道55キロメートル以上 | 31,600円 |
| 片道45キロメートル以上55キロメートル未満 | 28,000円 | |
| 片道35キロメートル以上45キロメートル未満 | 24,400円 | |
| 片道25キロメートル以上35キロメートル未満 | 18,700円 | |
| 片道15キロメートル以上25キロメートル未満 | 12,900円 | |
| 片道10キロメートル以上15キロメートル未満 | 7,100円 | |
| 片道2キロメートル以上10キロメートル未満 | 4,200円 | |
| 片道2キロメートル未満 | 全額課税 | |
| 3.交通機関を利用している人に支給する通勤用定期乗車券 | 1カ月当たりの合理的な運賃等の額(最高限度150,000円) | |
| 4.交通機関または有料道路を利用するほか、交通用具も使用している人に支給する通勤手当や通勤用定期乗車券 | 1カ月当たりの合理的な運賃等の額と2の金額との合計額(最高限度150,000円) | |
出典:国税庁「通勤手当の非課税限度額の引上げについて」
通勤手当および交通費を支給する際の注意点
通勤手当や交通費を支給する際は、支給対象や社内手続きなどに関して注意すべき点があります。経理部門の担当者の方は、以下のポイントに注意して業務を進めるようにしましょう。
通勤手当は社会保険料の算定対象になる
通勤手当は、社会保険料の算定基礎賃金に含まれます。そのため、通勤手当の全額を社会保険料の計算に含めなければなりません。一方、「取引先へ行くために利用するタクシー代」「出張で利用する新幹線代」などの交通費は、経費として扱われます。これらの業務上の移動で発生した経費は、社会保険料の算定対象ではありません。
パートタイム労働者や契約社員にも通勤手当や交通費は支給する
正社員に通勤手当を支給している場合は、パートタイム労働者や契約社員にも通勤手当を支給する必要があります。その理由は、「同一労働同一賃金」の原則があるためです。同じ労働を行っている従業員に対しては、雇用形態による不合理な賃金格差が生じないよう、法律で定められています。「同一労働同一賃金」は基本給や賞与だけでなく、通勤手当をはじめとした各種手当にも該当することを理解しておきましょう。
参考:厚生労働省「同一労働同一賃金特集ページ」
通勤手当や交通費の不正受給を防止する
経理部門では、社内で発生する可能性がある通勤手当の不正受給に注意しなければなりません。よくある不正受給の具体例として、最寄り駅やルートを偽って申請する「通勤経路の虚偽申告」や、交通機関利用を偽って徒歩や自転車で通勤する「交通機関利用の偽装」などが挙げられます。会社として公明で正確な経理処理を行うためにも、不正防止対策を強化することが重要です。例えば、支給対象者への定期的な通勤経路の確認や申告内容の見直しを実施すると良いでしょう。
交通費と通勤手当の違いを理解して正しい経理処理を行いましょう!
ここまで、交通費と通勤手当の違いを解説しました。交通費は業務上の移動で発生する経費を指すのに対し、通勤手当は自宅から勤務先までの通勤費用を補助する手当のことを指します。また、交通費は経費であり全額非課税となりますが、通勤手当は一定額まで非課税となる点に明確な違いがあります。
交通費と通勤手当の違いを理解して、それぞれ適切な方法で算出できるようにしておきましょう。
交通費精算の手続きで生じる手間やミスを削減し、煩雑な計算を自動化するなら、経費精算システム「楽楽精算」の活用をおすすめします。
「楽楽精算」には以下のような特徴があります。
特徴➀ 交通系ICカードをリーダーにかざすと履歴の読み取りができる
交通系ICカード取込機能により、手入力の手間やミスを削減できます。ICカードからデータを直接取り込むので、不正受給の防止にもつながります。
特徴➁ 定期区間を登録するだけで控除金額を自動計算してくれる
事前に従業員の定期区間を登録することで、定期券代の控除金額を自動計算できます。交通費精算の際、申請者の作業工数や、経理担当者の確認工数を削減できます。
特徴③ 交通手段や金額などのルールに反する申請はすべて自動でブロックする
社内の賃金規程に違反する申請は自動でブロックします。規程違反・記入漏れ・二重申請による差し戻しの手間をなくし、経理業務をラクにします。
「楽楽精算」の導入メリットや機能について、詳しくは資料でご案内しています。どうぞお気軽にお問い合わせください。
「楽楽精算」の
資料をメールでもらう

電子帳簿保存法対応!経費精算システム「楽楽精算」の製品概要や導入メリット、機能などが詳しくわかる資料をメールでお送りします。
この記事を読んだ方におすすめ!
オススメの人気記事
記事執筆者紹介

「楽楽精算」コラム編集部です。
経理担当者様の日々の業務にプラスとなるお役立ち情報
「楽楽精算」最新情報をお届けしていきます!
使い勝手が気になる方へ。