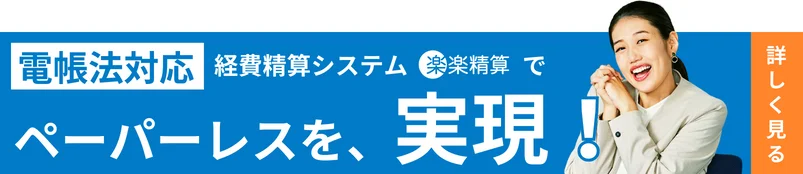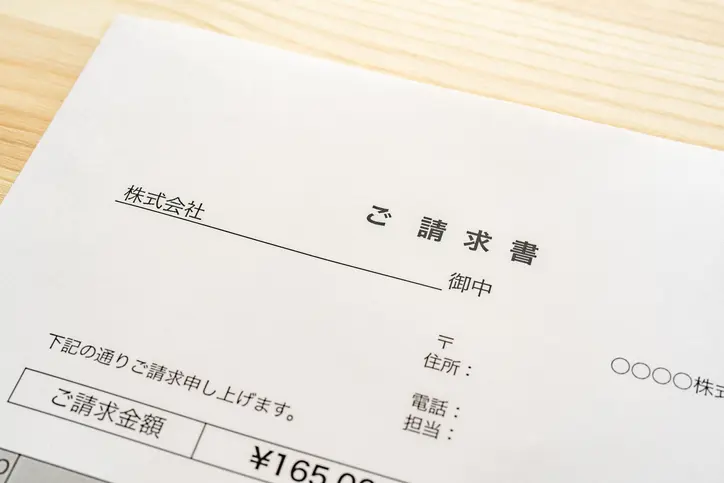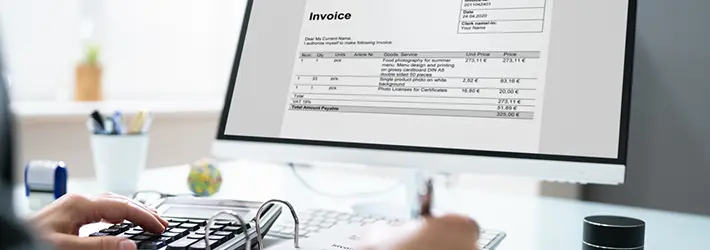「2025年の崖」とは?経産省レポートから読み解く日本のデジタル化の未来

経済産業省(経産省)から「2025年の崖」に関するレポートが2019年に発表されました。今なお「2025年の崖」という言葉は注目され、そのリスク、またそれにどう対応するかということが議論されています。この記事では「2025年の崖」という言葉を改めて振り返りながら、なぜ日本にこの崖があるのか、それを生き残るためのポイント、経費精算システムがどのように企業のDXを助けるかということをご紹介します。
この記事の目次
「2025年の崖」とは?
「2025年の崖」は経産省が2019年に発表した「DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」克服とDXの本格的な展開~」の中で提唱されました。日本企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)(※)が進まなければ2025年から2030年までの5年間、毎年年間およそ12兆円の経済的損失が日本経済で発生するリスクがあるというのが「2025年の崖」の概要です。
(※)デジタルトランスフォーメーションとは…
言葉の定義が明確ではなくいろいろな解釈がありますが、ここでは企業実務のIT化、とりわけ各企業独自のシステムを利用したIT化ではなく、最新トレンドに則ったグローバルスタンダードなITシステム、ソフトなどの活用を指します。
日本経済に損失があるというのは当然ながら日本企業にも大きく影響があり、企業内でのDXが進まないことが原因となって、コストは増加するものの売上は伸ばしにくいという状況が続くと考えられております。
なぜ日本には「2025年の崖」があるのか?
次になぜ日本には「2025年の崖」が生まれてしまうのかを確認します。経産省のレポートではその要因はいくつか紹介されていますが、ここでは「技術的な要因」「人材的な要因」を中心に取り上げます。
「2025年の崖」が発生する技術的な要因
「2025年の崖」の技術的な要因として日本には企業毎に独自のレガシーシステム(旧システム)が非常に多いということがあります。ここでいう「独自」というのは要件や使用しているプログラミング言語が独自であるということを指し、グローバルスタンダードからはやや外れているという意味です。
このような企業毎に独自のレガシーシステムが多く存在することでさまざまなリスクが発生します。例えば、長期運用を継続する中でシステムの改修を繰り返すことになります。この度重なる改修によりシステムの中身がブラックボックス化し、全容を把握できる人材がいなくなってしまいます。そして、更新や保守管理に非常に大きな工数や費用がかかるようになります。その結果、本来は新システムへの投資として利用すべき会社の資本が、レガシーシステムを維持する(ラン・ザ・ビジネスの)ためだけに使われてしまうということが多くの日本企業で発生している問題です。
「2025年の崖」が発生する人材的な要因
技術的な側面と同様に人材的な要因もあり「2025年の崖」の発生が懸念されます。日本企業はスクラッチ開発やカスタマイズ機能を好む特性があり、個別企業ごとに独自のシステムやノウハウが蓄積されてしまうという特徴があると経産省のレポートでは指摘されています。そのため、企業毎の独自技術に対応していた人材の定年退職の時期(2007年)が過ぎ、人材の退職とともに企業にノウハウがなくなってしまいました。これにより前述のシステムのブラックボックス化が加速します。
そこで企業はIT人材の確保を急ぎます。しかし、企業独自のシステムへのノウハウに対応している人材は市場にはいません。さらに、先進技術を持った若い人材を確保してもレガシーシステムのメンテナンス業務を主業務としてしまうために、業務が魅力的ではなく離職が増えます。そして、当初のIT人材が不足しているという問題が解決されず、企業内での人材の継続的な確保、育成が難しい環境が続いているというのが現状です。
こういった背景があり、日本企業は独自のシステムを維持するためにベンダー企業に頼ることになります。そのため、新規投資を行うために使う費用がシステム維持の費用として消化されてしまうという悪循環が発生し、レガシーシステムからの脱却がさらに難しくなってしまっています。
「2025年の崖」生き残るために必要なこと
では、日本企業がDXに対応し「2025年の壁」を乗り越えるためには何が必要なのか、具体的に確認します。この場合も必要なことは多岐にわたりますが、まずはレガシーシステムから先進システムへの刷新だけに注目してご説明します。
必要な業務、機能の見極め
レガシーシステムは仕様やプログラミングのノウハウが失われていることに加え、不要な機能が非常に多く備わっていることも問題として挙げられます。現在のユーザーが一度も使ったことがない機能であるのにも関わらず、システムとしては存在するので維持コストがかかっているものはないでしょうか。また、その機能を使うために新人の学習期間が必要だったり、他のシステムとデータ連携ができずに不要な業務が増えているという本末転倒な業務状況になってしまっていることはないでしょうか。不要な機能や業務を判断し、本当に必要なものだけを抽出することは企業がDX対応するためのはじめの一歩です。
レガシーシステムの刷新
必要な機能、必要な業務を見極めたら、レガシーシステムを先進システムに刷新していくようにしましょう。導入にかかる費用と、その後にかかる運用コストを算出して、現在のレガシーシステムを維持するコストと比較します。このとき、社内の運用稼働、人件費も計算するようにしましょう。新システム導入と運用のコスト、旧システムを運用するコストを比較した上で旧システムを維持するよりも新しいシステムに移行するほうがメリットが大きいと判断されたら、システムの刷新を実施します。社内で必要な業務、それを遂行するための機能は事前に確認しているはずなので、その後の業務は問題なく進行できるはずです。
また、旧システムがオンプレミス型のシステムだった場合、これをクラウド型に変えることも現在では一般的になってきています。クラウド型のシステムを利用することでいろいろなメリットがあります。最も分かりやすいものはコストメリットです。クラウド型のシステムは初期費用や保守費用が安価であることが多く、会社規模やユーザー数などに応じた柔軟な価格設定ができます。従量課金制をとるシステムが多いので、人数が少なければその分導入、運用コストを抑制することができます。
さらにクラウド型のシステムならシステムを管理する手間も削減できます。オンプレミス型のシステムは開発会社に比較的大きな保守費用を支払って保守管理してもらったり、自社で管理者を雇ったりしてシステムを管理する必要がありました。しかし、クラウド型のシステムなら管理、保守はサービス提供会社が行います。そのため、ユーザー企業では管理の手間もなく、バージョンアップ対応の必要などもありません。例えば税制改正などでシステムに軽減税率などを反映する必要がありましたが、それも「楽楽精算」側で作業をするのでお客様は手を動かすことなくシステムの法適用を実施できます。セキュリティも万全なので、専門家のいない状態で自社システムを利用しているよりは、エキスパートが開発したシステムを使うほうが安全です。
運用コストを改革コストへ
旧システムから新規システムへ移行を決定したということは、コストか稼働、あるいはその両方が削減されたはずです。そこで、その削減された稼働やコストをまた別のシステム選定や導入に利用しましょう。この循環を繰り返すことで、業務はますますスリム化され効率が上がり、従業員の稼働も無駄な業務から本来集中するべき売上をあげるためのコア業務に割くことができるようになります。
ある程度業務のスリム化、効率化が落ち着いたときには企業の収益性はこれまでと変わってくるでしょう。不要なシステムに支払っていた費用が削減され、従業員の業務効率が改善されているので、収益性が良くなっているという企業が多いはずです。
「2025年の崖」で落ちていく企業にならないために
社会のDXの流れに取り残されて、「2025年の崖」で落ちていく企業にならないために、できる部分からで構わないので先進システムの導入を検討することが必要です。「楽楽精算」は経費精算において最新のクラウドシステムであり、経費精算の無駄を大きく削減できるシステムとして企業様からご好評をいただいています。
既存のシステムでの経費精算に無駄が多いと感じている企業や、現時点ではシステム化もできていないという企業であれば、まずは経費精算からDXを始めてみるのはいかがでしょうか。
>>「楽楽精算」の詳細ページはこちら!「楽楽精算」の
資料をメールでもらう

電子帳簿保存法対応!経費精算システム「楽楽精算」の製品概要や導入メリット、機能などが詳しくわかる資料をメールでお送りします。
この記事を読んだ方におすすめ!
オススメの人気記事
記事執筆者紹介

「楽楽精算」コラム編集部です。
経理担当者様の日々の業務にプラスとなるお役立ち情報
「楽楽精算」最新情報をお届けしていきます!
使い勝手が気になる方へ。