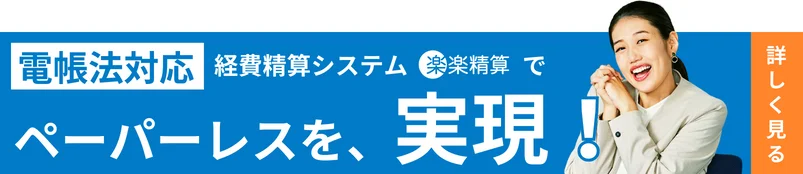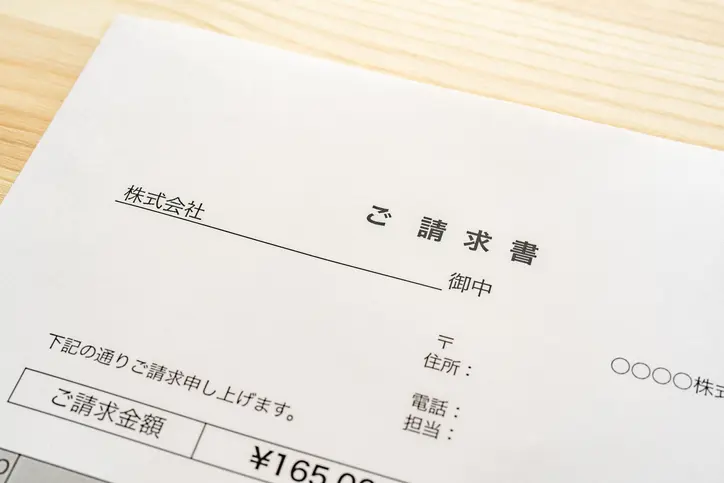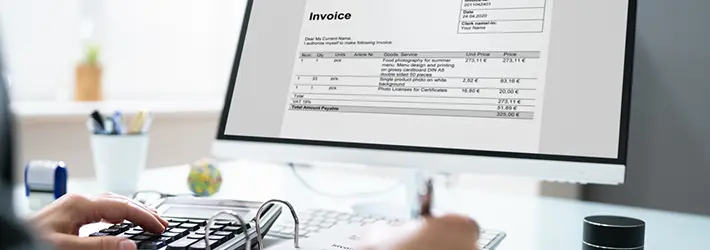年度またぎの経費精算は可能?仕訳から注意点、効率化のコツまで解説

経理担当者の中には、「年度またぎでの経費精算は可能なのだろうか」と疑問に思ったことのある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、年度をまたいでの経費精算の仕訳方法や注意点、スムーズに経費精算を行うためのポイントについて解説します。
この記事の目次
年度またぎでの経費精算は可能
年度またぎの経費精算とは、従業員が立て替えた交通費や経費などを、年度をまたいで計算することを指します。
基本的に、経費精算を行う際は、その経費が発生した年度内に処理をする必要があります。一方で、会計の基本ルールである発生主義に基づけば、費用は「利用日」や「サービス提供日」に計上すべきです。したがって、たとえ精算処理が翌年度にずれ込んでも、費用の計上自体は前年度に行うことが可能です。
例えば、年度末が3月の企業において、本年度の3月に商品の仕入れを行い、翌年度の4月に支払いを行った場合、本年度の経費として処理します。具体的なケースについては、以下で詳しく解説します。
年度またぎの経費精算が発生するケース
年度またぎの経費精算が発生するケースとして、どのような状況が考えられるでしょうか。
具体的な例を挙げながら解説します。
利用期間が年度をまたぐ場合
経費を使用した期間が年度をまたぐ場合、経費精算は翌月に行います。
例えば、3月31日から4月1日にかけて出張した場合、往路は前月分、復路は当月分として精算する必要があります。
年度末の経費を請求する場合
年度末の最終日に経費を立て替えた場合などに、経費精算の申請が当日中に間に合わない場合、年度またぎの経費精算が発生します。
経費申請を忘れていた場合
経費が発生したにも関わらず、従業員が年度末の忙しさで経費申請を失念・遅延するケースも少なくありません。年度をまたいだ場合、該当する事業年度での経費精算は難しいため、次年度での経費精算として処理することになります。
年度またぎの経費精算における仕訳例
年度をまたいで経費精算をする際、主な会計処理の方法としては、先払いと後払いの2通りが挙げられます。ここからは、それぞれの方法における仕訳例を紹介します。
先払いの場合
経費を先払いした場合は、「前払金」という勘定科目を用いて処理します。
例えば、3月31日から4月1日にかけての出張費2万円を3月中に支払った場合の仕訳は以下の通りになります。
| 日付 | 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3月31日 | 旅費交通費 | 10,000円 | 現金 | 20,000円 |
| 前払金 | 10,000円 | |||
| 4月1日 | 旅費交通費 | 9,000円 | 前払金 | 9,000円 |
後払いの場合
年度またぎで経費が発生し、後で精算を行った場合は、「未払金」という勘定科目を用いて処理します。
例えば、3月28日に片道18,000円の航空券を往復で購入し、3月28日に往路、4月1日に復路を利用した場合の仕訳の方法は以下のとおりです。
| 日付 | 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3月28日 | 旅費交通費 | 18,000円 | 未払金 | 18,000円 |
| 4月2日 | 旅費交通費 | 18,000円 | 現金 | 36,000円 |
| 未払金 | 18,000円 | |||
年度またぎの経費精算における問題点
年度またぎで経費精算を行うことは、会計処理の原則に基づき可能ではありますが、多くの問題点やリスクを伴います。主要な問題点について、以下で解説します。
決算・月次決算の正確性の低下
大きな問題として、費用が本来計上されるべき月や年度とは異なる期間に計上されてしまうことがあります。発生主義会計の原則では、費用は発生した時点で認識されるべきです。月またぎや年度またぎの精算が増えると、この原則が守られにくくなり、月次決算や年度決算の正確性が損なわれます。
また、経費精算の遅延は、リアルタイムでの正確な経営状況の把握を妨げます。月々の経費の発生状況が正確に把握できないと、予算と実績の比較が難しくなり、適切な経営判断が遅れる可能性があります。
経理業務の負担増大
月またぎや年度またぎの経費精算が発生すると、「前払費用」や「未払費用」といった経過勘定科目を用いた仕訳処理が必要になります。これは通常の経費精算よりも複雑であり、経理担当者の手間と時間が増加します。
さらに、年度またぎで多額の経費精算が遅れると、既に確定した決算書や税務申告書を修正する必要が生じる場合がある点にも注意が必要です。修正のための手続きに伴い、経理部門に膨大な労力を強いることになります。
監査・税務調査での指摘リスク
費用の計上時期のずれは、税務調査において所得の過少申告とみなされ、追徴課税や加算税の対象となるリスクがあります。正確な会計処理が行われていないと判断されれば、企業の信頼性にも悪影響を及ぼしかねません。なかでも、上場企業など会計監査を受ける企業の場合、月またぎや年度またぎの経費精算が多いと、内部統制の不備を指摘される可能性があります。
年度またぎの経費精算の発生を抑える方法
年度またぎの経費精算をできるだけ抑えるためには、どのような方法があるのでしょうか。以下で詳しく解説します。
経費精算の締切を決める
月次での経費精算の締切日を明確に定め、従業員に周知徹底することで、精算の遅延を防ぐことができるでしょう。特に年度末は、従業員側も業務に追われて対応を忘れてしまうといったケースが考えられるため、通常の月次締切よりも前倒しで設定するなどの工夫が必要です。
社内規定を整備し、従業員に周知する
年度またぎの経費精算に関する社内規定を明確に定め、全従業員に周知することも重要です。いつまでに、どのように申請すればよいのか、どのような費用が年度またぎの対象となるのかなどを明記することで、従業員の理解を深め、適切な運用を促します。単にマニュアルを配布するだけでなく、説明会を開いたり、解説動画を共有したりすることで、理解してもらいやすくなるでしょう。
経費精算システムを導入する
経費精算システムは年度またぎの経費精算の発生を抑えるための非常に有効な手段です。システムによる自動化と可視化により、申請漏れや遅延のリスクを大幅に削減し、経理業務の効率化と正確性の向上に貢献します。
例えば「楽楽精算」には、未精算や未承認の伝票がある場合に、申請者や承認者に精算や承認を促すメールを送信できる機能があります。また、承認依頼や承認通知などの自動送信設定もできるため、申請状況の確認や催促連絡のコミュニケーションから解放されます。
その他の詳しい機能については、以下のページで紹介しています。ぜひ参考にしてみてください。
まとめ
年度またぎの経費精算は、経費の発生時期と精算時期が異なることで生じます。会計上は可能ですが、決算の正確性低下や経理業務の負担増大、税務調査での指摘リスクなど、多くの問題点を伴います。
これらのリスクを抑えるには、精算締切日の設定、明確な社内規定の整備と周知が不可欠です。特に、経費精算システムの導入は、申請漏れや遅延を防ぎ、経理業務の効率化と正確性向上に大きく貢献するため、積極的に検討することをおすすめします。
「楽楽精算」の
資料をメールでもらう

電子帳簿保存法対応!経費精算システム「楽楽精算」の製品概要や導入メリット、機能などが詳しくわかる資料をメールでお送りします。
この記事を読んだ方におすすめ!
オススメの人気記事
記事執筆者紹介

「楽楽精算」コラム編集部です。
経理担当者様の日々の業務にプラスとなるお役立ち情報
「楽楽精算」最新情報をお届けしていきます!
使い勝手が気になる方へ。