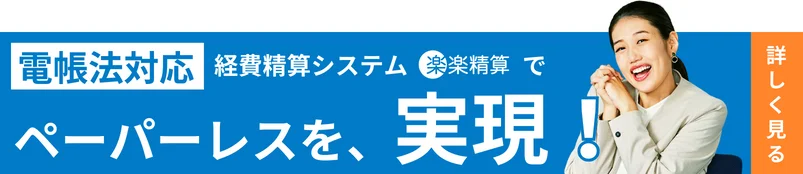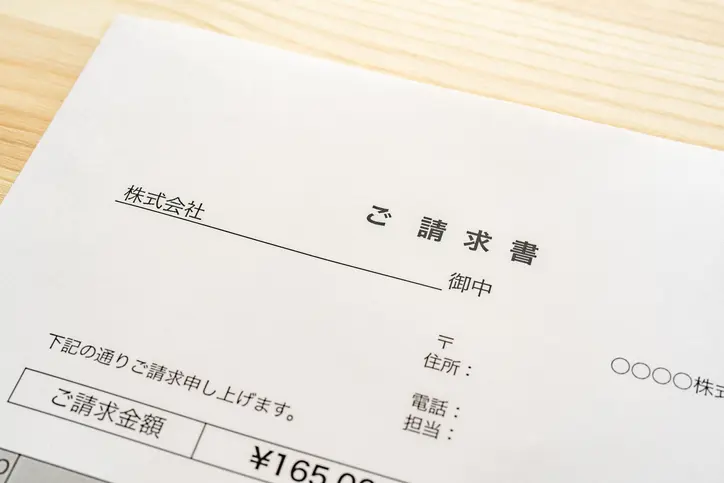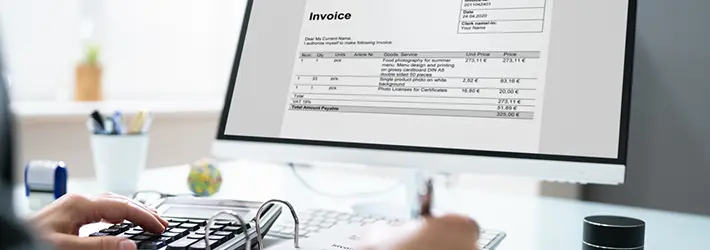パスポート取得費用は経費になる?会社負担と税務リスクの注意点を解説
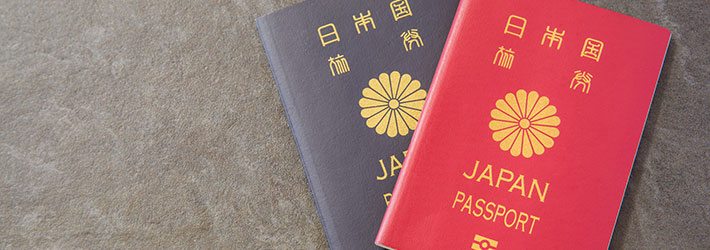
「海外出張が決まったけれど、パスポートの取得費用って会社の経費にできるの?」
中小企業の経理担当者であれば、一度はこのような疑問を抱いたことがあるかもしれません。海外出張が増える中で、社員のパスポート取得費用をどう処理すべきか、頭を悩ませている方もいるのではないでしょうか。
「出張で使うのだから経費になるはず」と安易に考えていると、後々、税務調査で思わぬ指摘を受けたり、会社や社員が不利益を被ったりする可能性もあります。
この記事では、パスポート取得費用の経費処理に関する疑問を解消し、税務リスクを避けるための判断基準や注意点、さらに適切な申請管理について解説します。この記事を読めば、あなたの会社でパスポート費用に関する明確なルールを整備し、安心して海外出張に社員を送り出せるようになるでしょう。
この記事の目次
パスポート取得費用は「業務上の必要性」が経費計上のカギ
パスポートの取得費用は、その性質上、「業務上の必要性」が極めて明確な場合に限り、会社の経費として計上できる可能性があります。しかし、その判断には慎重な見極めが必要です。
国税庁の基本的な見解では、パスポートは運転免許証や健康保険証などと同様に「個人の身分を証明する書類」、つまり個人の資格証明と見なされます。そのため、原則的には個人が取得すべきものとされています。しかし、海外出張や海外赴任など、業務の遂行上、パスポートの取得が真に必要不可欠であると客観的に判断できる場合には、その費用を会社の経費として認める余地が出てきます。この「業務上の必要性」が、経費計上の可否を分ける重要なポイントとなります。
では、なぜ「業務で使うのだから経費でいいのでは?」と安易に判断できないのでしょうか。その理由は、パスポートが私的要素が非常に強く、かつ資産的価値も持つためです。
パスポートは業務での海外渡航だけでなく、社員が個人的な海外旅行で使用することも可能です。つまり、その用途は業務に限定されません。また、一度取得すれば5年または10年の有効期限があり、その期間中は繰り返し使える「資産」としての側面も持ちます。個人の財産と見なされるため、その費用を会社の経費として計上するには、前述の「業務上の必要性」を厳格に証明する必要があるのです。
特に、単発の海外出張のために取得した場合でも業務上の必要性が明確であれば経費計上が可能ですが、その後の私的利用の可能性も考慮されるため、より継続的・恒常的に業務で必要とされるケースの方が、税務上の妥当性が認められやすい傾向にあります。
したがって、たとえ海外出張のために取得したパスポートであっても、業務上の明確な必要性が認められない限り、その費用は個人の負担となります。これは、印紙代(手数料)、写真代、さらにはパスポートの更新費用についても同様の考え方が適用されます。
パスポートの「会社負担」が認められるケースとは?
パスポート費用の会社負担が認められるケースについて、具体的な例を挙げて詳しく解説します。ただし、「会社負担=経費計上できる」とは限らない点に注意が必要です。
業務上不可欠な場合(海外赴任や短期出張が頻繁にある)
最も代表的な例としては、その社員の業務にとってパスポートの取得・保持が極めて不可欠であると客観的に判断されるケースがあります。具体的には、以下のような状況が考えられます。
・海外赴任の場合
海外に赴任する社員にとって、パスポートは業務遂行上、必須の書類です。この場合、赴任準備の一環として会社が取得費用を負担することが認められる場合があります。
・短期出張が極めて頻繁にある場合
通常の業務として、年間を通じて極めて頻繁に海外出張が発生し、パスポートの取得・更新が事業活動に直接的に結びついていると判断できる場合です。例えば、海外の顧客との商談が日常的に行われる部署の社員や、海外の工場への定期的な技術指導を行う社員などが該当する可能性があります。
採用条件に「パスポート取得を要件」として明示している場合
新卒採用や中途採用において、特定の職種(例えば国際営業職など)で「パスポート取得を入社条件とする」と求人票や労働契約書に明記しているケースも会社負担が認められる場合があります。この場合、パスポートの取得が業務に直結し、その費用が会社が事業を行う上で必要な支出と見なされやすくなります。
重要なのは、採用時に明確な要件として提示されていることです。入社後に急遽海外出張が必要になったからといって、後付けで会社負担にするのは難しいでしょう。
入社前に会社が代理で取得する必要があるケース
稀なケースですが、入社前に会社が新入社員のパスポートを代理で取得する場合があります。例えば、入社後すぐに海外研修や海外勤務が予定されており、採用手続きと並行してパスポートを準備する必要があるような場合です。
このようなケースでは、会社が費用を立て替えて支払い、その後、社員に返還を求める(給与から控除するなど)のが原則です。ただし、前述の「業務上不可欠な場合」や「採用条件に明示している場合」に該当すると判断できる場合は、会社が負担し、福利厚生費や旅費交通費(海外出張に直接紐づく場合)として処理できる可能性もあります。この判断は慎重に行う必要があります。
パスポート発行費用を経費にできないケース
「業務上必要な場合に限り」経費として認められるパスポート費用ですが、以下のようなケースでは経費計上が困難となります。
出張の予定がないのに申請したパスポート費用
具体的な海外出張や海外赴任の予定が決まっていない段階でパスポートを申請した場合は、私用目的とみなされる可能性が高く、その費用を経費にすることはできません。例えば、「もしかしたら将来海外出張があるかもしれないから」という理由での取得は、経費としては認められません。
パスポートの申請から発行までには時間がかかるため、計画的に取得する必要がありますが、それが即座に業務上の必要性につながるわけではない点に注意が必要です。
プライベート用に取得したパスポート発行費用
すでに個人的な海外旅行などのためにパスポートを取得しており、それを業務上の海外出張に流用するケースも考えられます。この場合、たとえそのパスポートを業務で使ったとしても、取得時の目的が私的であったため、その発行費用を経費として計上することは難しいと判断されます。
このような状況での不公平感を解消するため、会社によっては一律の出張準備金を支給するなどの対応を検討するケースもあります。
社員旅行を目的としたパスポート発行費用
海外への社員旅行を目的としてパスポートを取得した場合も、その費用は経費として認められません。社員旅行は通常、福利厚生費として交通費や宿泊費が計上されることがありますが、パスポートは個人の資格証明であるため、原則として私的費用とみなされます。
経費計上の対象は、あくまでビジネスを目的とした海外出張や海外赴任のために取得した場合に限定されることを理解しておきましょう。
パスポート取得にかかる費用と金額、申請の基本
パスポートの取得費用を経費計上できる可能性がある場合、具体的にどのような費用が含まれるのでしょうか。また、申請手続きの概要も確認しておきましょう。
パスポート申請・発行にかかる主な費用
パスポートの申請・発行にかかる費用は、主に以下の2種類です。
- 申請手数料
- 証明写真代
・申請手数料
パスポートの申請時には、国や地方自治体に手数料を支払う必要があります。具体的な費用は、10年用パスポートの場合16,000円、5年用パスポートの場合11,000円です。このうち、国に納める手数料は収入印紙で、地方自治体に納める手数料は収入証紙や現金で支払うことが一般的です。
これらの費用は、業務上の必要性が認められれば経費として処理可能です。
・証明写真代
パスポート申請には、規定のサイズの証明写真が必要です。写真代も、パスポート取得に付随する費用として経費計上できる可能性があります。
駅などに設置されている証明写真機の場合、800円~1,000円程度、写真館で撮影する場合は2,000円~3,000円程度の費用がかかります。
パスポートを申請する際に必要な書類
パスポート申請には、以下の書類が必要です。漏れなく準備しましょう。
- 一般旅券発給申請書
- 戸籍謄本または戸籍抄本(発行から6ヶ月以内のもの)
- 住民票の写し(住民登録をしている都道府県で申請する場合は原則不要)
- 証明写真(6ヶ月以内に撮影されたもの)
- 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
これらの書類に不備があると、申請が受け付けられず、発行が遅れる原因となります。海外出張の予定が決まっている場合は、余裕をもって準備を進めることが重要です。
パスポートの申請費用を支払うタイミング
パスポートの申請費用は、申請時に支払います。具体的には、申請書類を提出し、窓口で収入印紙や手数料を支払う流れが一般的です。収入印紙は、事前に郵便局などで購入しておく必要がある場合や、申請窓口の近くで購入できる場合など、自治体によって異なりますので、事前に確認しておきましょう。
支払いが確認されることで、正式に申請手続きが受理されます。パスポートの発行には、申請から最短で1週間程度(土日祝日を除く)かかることが多いため、海外出張のスケジュールを考慮し、余裕を持って申請することが不可欠です。
パスポート発行費用の適切な勘定科目と処理方法
パスポート発行費用を会社の経費として処理する場合、適切な勘定科目の選択が重要になります。費用の性質に応じて、主に以下の勘定科目を用いることができます。
租税公課
パスポート発行費用の一部は「租税公課」として計上します。「租税公課」は、政府や地方自治体に支払う税金や手数料を含む勘定科目です。パスポート申請においては、パスポートセンターで支払う収入印紙代や地方自治体への手数料がこれに該当します。これらは国や地方公共団体への支払であるため、租税公課として処理するのが適切です。
旅費交通費
業務上の出張や移動に直接関連する費用として「旅費交通費」に計上することも可能です。 海外出張や海外赴任のためにパスポートを取得した場合、その取得費用は海外での業務遂行に不可欠な費用と見なせるため、旅費交通費の一部として処理できます。特に、ビザの取得費用と合わせて計上するケースも多いでしょう。あくまで業務に必要な範囲に限られる点に注意が必要です。
雑費(証明写真の撮影代金など)
パスポート用の証明写真代は「雑費」として計上することが一般的です。 雑費は、他の主要な勘定科目に明確に分類できない細かい費用や、金額的に重要性が低い費用を処理する際に使用します。証明写真代は、パスポート発行費用そのものではなく、その準備に必要な付随費用であるため、雑費に分類するのが適切です。領収書もパスポートの申請費用とは別に発行されることが多いため、処理がしやすいでしょう。
課税/非課税の分類にも注意
パスポート取得費用のうち、収入印紙代などの租税公課で処理する費用は、通常、非課税となります。しかし、会社が社員に給与として支給する形で負担した場合などは課税対象となる可能性もあります。
各費用項目をどの勘定科目で処理するかを明確にし、それぞれが課税対象となるのか非課税となるのかをきちんと分類しておくことが、税務上のトラブルを避ける上で重要です。
会社がパスポート費用を負担する際の注意点
会社がパスポート費用を例外的に負担する場合、税務リスクを避けるために細心の注意が必要です。特に、社員への「給与」認定を避けるための明確な証拠作りと、社内ルールの整備・徹底が不可欠です。
給与認定を避けるための「業務上の必要性」証明と記録保管
会社がパスポート費用を負担した場合、税務調査で社員への「給与」と認定されるリスクがあります。これを回避するためには、以下の徹底が不可欠です。
・業務上の必要性の具体化
なぜその社員のパスポート取得費用を会社が負担するのか、その業務上の必然性や目的を具体的に明文化します。例えば、特定プロジェクトのための海外出張の必須性など、客観的な理由を明確にしましょう。
・関連記録の徹底的な保管
実際にパスポートが業務に使われたことを示す、宿泊先の領収書、海外取引先とのやり取り記録、出張報告書などの関連証拠を全て保管しましょう。これにより、業務との関連性を客観的に証明できます。
就業規則や出張規定への明確なルール設定
パスポート費用を会社が負担する可能性を設ける場合は、その旨を就業規則や出張規定などの社内規程に明確に記載することが非常に重要です。これにより、社内での一貫した運用と、税務当局への説明責任を果たしやすくなります。
・費用負担条件の明文化
「どのような場合に」「どの範囲で」会社がパスポート費用を負担するのかを具体的に定めます。例えば、「海外赴任者」「年間〇回以上の海外出張が恒常的に発生する社員」など、客観的な条件を設定しましょう。
・対象費用と申請・精算フローの明確化
印紙代や写真代など、具体的な対象費用を明記し、領収書の取得・保管方法、申請・承認プロセスなどの精算フローも定めます。これにより、社員の申請ミスを防ぎ、経理担当者の処理もスムーズになります。また、公平なルールに基づいて処理していることの証拠にもなるでしょう。
社員間の不公平感をなくすルール統一
会社がパスポート費用を負担する際は、一貫したルールを全社員に適用し、公平性を保つことが不可欠です。「あの人は会社にパスポート代を出してもらったのに、私は自腹。なぜ?」といった不公平感は、社員のモチベーション低下や不満の原因となりかねません。特定の役職者や部署の社員だけが対象となる場合は、その業務上の理由を明確にし、誰もが納得できるような説明ができるようにしておくべきです。
経費申請ミスを防ぐには、経費精算システムの活用が効果的
パスポート費用のように例外的な処理が必要な項目については、個別の判断やチェックが増え、経理担当者の負担が大きくなります。
また、社員側も規定を完全に把握していない場合があり、誤った申請をしてしまう可能性も考えられます。
そこで効果的なのが、経費精算システムの導入です。
なかでも「楽楽精算」は、以下のような機能を搭載しており、パスポート費用をはじめとする経費申請のミスを低減できます。
楽楽精算の機能1:規定違反チェック機能
規定違反チェック機能は、あらかじめ設定した社内ルールに反する経費申請に対して、警告の表示や申請ブロックをする機能です。たとえば「1人あたりの金額が5,500円を超える場合、交際費を選択しないと申請不可とする」「規定外の宿泊代が発生した場合に、理由の記載を必須にする」など、社内規定にあわせてさまざまなルールを設定できます。
申請のチェック・差し戻しの作業が削減されるのはもちろん、 内部統制の強化やコンプライアンスの順守にもつながるでしょう。
楽楽精算の機能2:汎用ワークフロー機能
汎用ワークフロー機能とは、稟議や押印申請などの社内で発生する様々な申請を「楽楽精算」上でシステム化する機能です。
汎用ワークフローで作成した稟議申請と経費精算の紐づけも可能。 社内で必要な手続きすべてを「楽楽精算」で電子化&一元管理できるので、 申請からチェック、承認までの時間を削減し、内部統制強化にもつながります。
このように、経費精算システムは、パスポート費用のような複雑な経費処理を安全かつ効率的に行うための強力なサポートとなります。気になる方は、ぜひ以下のフォームからお問い合わせください。
「楽楽精算」の
資料をメールでもらう

電子帳簿保存法対応!経費精算システム「楽楽精算」の製品概要や導入メリット、機能などが詳しくわかる資料をメールでお送りします。
この記事を読んだ方におすすめ!
オススメの人気記事
記事執筆者紹介

「楽楽精算」コラム編集部です。
経理担当者様の日々の業務にプラスとなるお役立ち情報
「楽楽精算」最新情報をお届けしていきます!
使い勝手が気になる方へ。