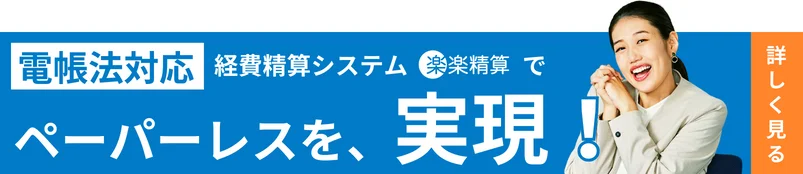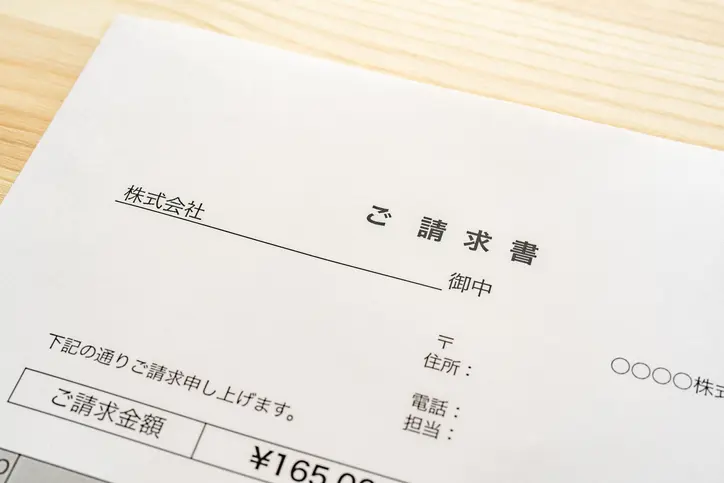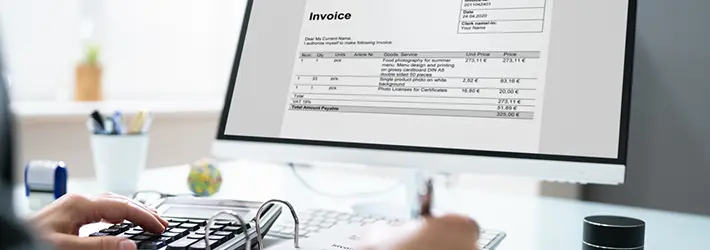領収書は分割して発行できる?可能なケースや注意が必要なケース

業務で発生した経費を複数の社員が立て替えたときや、業務に必要な商品・サービスの代金を分割払いしたときなど、領収書を分けて発行するシーンがあると思います。ですが、そもそも領収書を分割することに問題はないのでしょうか?また、分割した領収書が経費精算で提出された場合は、どのように処理すればよいのでしょうか?
この記事では、分割可能なケースや分割時の注意点などを詳しく解説します。特に経理担当者の方は、経費を正確に計上するために、正しい対応方法やルールを確認しておきましょう。
この記事の目次
そもそも領収書は分割して発行できる?
結論として、経費を正確に計上する目的で分割するのであれば、一度の会計で領収書を複数枚に分けて発行することが認められています。 ただし、こうした分割発行が認められるのは、あくまでも経費精算を適切に行う必要があるときのみです。
では、実際はどのような場合に分割が認められるのでしょうか。領収書の分割が認められる具体的なケースについて、詳しくは次の見出しで解説していきます。
領収書の分割が認められる主なケース
領収書の分割が認められるのは、主に以下の3つのケースです。
- ケース1:割り勘・複数人で支払いをした場合
- ケース2:分割払いの場合
- ケース3:会計が別の組織や団体が共同で支払いをした場合
ここでは、それぞれのケースにおける領収書発行の方法をご紹介します。
ケース1:割り勘・複数人で支払いをした場合
割り勘で支払った場合や、複数人で支払った場合は、領収書の分割が認められています。
例えば、プロジェクトの円滑な進行を目的とした食事会で、6人のメンバーが3万円の飲食費をそれぞれ5,000円ずつ支払うようなケースが挙げられます。この場合、1人あたり5,000円分の領収書を受け取ることが可能です。
このように「誰が」「いくら払ったか」が明確で、取引の実態に基づいていれば、各自がそれぞれの支払額に応じた領収書を受け取ることができます。
ポイント
- 「誰が」「いくら払ったか」が明確な場合は分割が可能
- 各自が支払った金額分の領収書をそれぞれ受け取る
ケース2:分割払いの場合
代金を分割払いした場合も、支払った金額ごとに領収書を分けることが認められています。 これは、領収書が「実際に支払った金額」を証明する書類であるという原則に基づくものです。
例えば、総額150万円の社員研修プログラムを3回に分けて支払う場合、それぞれの支払い時点で50万円ずつの領収書が発行されるのが適切です。領収書の但し書きには「総額150万円のうち、今回分50万円」といったように、分割払いであることが明記されることもあります。
ポイント
- 分割した代金を支払う都度、支払った分の領収書が発行される
補足:分割によって額面が5万円未満となったら収入印紙の貼付は不要
分割した領収書の額面が5万円未満となったら、発行側による収入印紙の貼付は不要です。通常、記載金額が5万円以上の紙の領収書には収入印紙を貼付する必要があります。ただし、領収書の金額が5万円未満である場合や、電子的に発行された領収書の場合は、収入印紙がなくても問題ありません。
ケース3:会計が別の組織や団体が共同で支払いをした場合
会計処理を別に行う組織や団体が共同で費用を負担する場合も、それぞれの支払額に応じて領収書を分割発行することが認められています。
例えば、社内の異なる部署同士や、複数の法人がセミナーを共同開催するようなケースでは、各支払い元が負担した金額に応じて、それぞれの名義で領収書を受け取ることが可能です。
このような分割発行を行う際には、会計処理上の根拠を明確にするためにも、分担比率や支払内容を示す明細書や契約書などの補足書類を併せて保管しておくことが望ましいとされています。
ポイント
- 各支払い元の会計処理上必要な場合に分割できる
- 明細書・契約書などの書類で分担比率の裏付けがあるのが望ましい
補足:クレジットカード決済では売り手側に領収書発行の義務がない
クレジットカードの分割払いを利用するケースでは、売り手側が領収書発行に対応しない可能性があります。 その理由は、クレジットカード決済ではクレジットカード会社が代金を受領するので、売り手側には法的に領収書発行の義務がないためです。あらかじめ領収書発行の方針を確認しておくとよいでしょう。
領収書を分割する際の注意点
ここまで、領収書の分割が認められるケースをご紹介しましたが、その反対に、領収書の分割が認められないケースもあります。
原則として、領収書発行は実際の支払金額に基づいて行うのが望ましいとされています。そのため、実際の支払金額と相違のある領収書の発行は避けなければなりません。例えば、以下のようなケースでは不適切な分割と見なされるおそれがあるため注意が必要です。
- NGパターン1:金額調整のための不自然な分割
- NGパターン2:実際の支払者が1人だった場合の分割
詳しく見ていきましょう。
NGパターン1:金額調整のための不自然な分割
金額の調整を目的とした不自然な領収書の分割は、税法上の違反行為と見なされるおそれがあるため注意が必要です。
例えば、税額控除(例:医療費控除、ふるさと納税など)で控除対象となるために、意図的に金額を操作して領収書を分割する行為は不適切です。また、支払いの実態とは異なるにもかかわらず、「1人あたり〇万円になるように領収書を発行してもらう」といった金額調整も経費処理上問題となる可能性があります。
このほかに、10万円以上の物品(固定資産に該当するもの)を分割購入したように装い、10万円未満の領収書を複数に分けて発行することも厳重な注意が必要です。税務調査で減価償却の回避や脱税と疑われるリスクがあります。
経費管理を担う経理部門の担当者は、こうした不正のリスクを踏まえて経費申請の事実確認を行うことが重要です。 実際の支払いと領収書の内容に齟齬がないか、チェックを徹底しましょう。
参考:国税庁「No.2100 減価償却のあらまし」
NGパターン2:実際の支払者が1人だった場合の分割
実際の支払者が1人であるにもかかわらず、あたかも複数人で支払ったかのように見せかけて領収書を分割することも虚偽の申告にあたります。
例えば、社員Aと社員Bが出張に行き、実際にはAが全額を支払ったにもかかわらず、領収書を分割してAとBのそれぞれが受け取るといったケースは、不適切な経費処理とされます。
このような不正は、経費の実態把握を困難にするだけでなく、虚偽申告によるコンプライアンス違反や税務上の問題にもつながるおそれがあります。経費精算や税控除の便宜を目的として領収書を形式的に分割することのないよう、経理部門の担当者は社内でのルールや注意点について明確に周知・徹底することが重要です。
まとめ:領収書の分割はルールに則って適切に行いましょう
ここまで、領収書の分割に関するルールを解説しました。経費の正確な計上につながる場合には領収書の分割発行が認められています。その際、経理担当者は経費精算における不正がないよう、申請書の金額や利用目的を一つひとつ確認し、ルールに則って適切に手続きを行わなければなりません。
ただ、経費精算業務はチェック作業に手間がかかる上に、目視確認では見逃しのリスクもあるでしょう。そんなときは、専用システムで業務全体を電子化する対策が有効です。クラウド型経費精算システム「楽楽精算」には、自動チェックで経費精算業務を効率化する便利な機能が搭載されています。
「楽楽精算」に搭載された以下の機能を使えば、経費精算業務がラクになります。
機能1:規程違反チェック機能
社内ルールに違反する申請を自動でブロックしたり、警告表示を行ったりする機能です。自動チェックによって内部統制の強化やコンプライアンス遵守を実現できます。また、差し戻しの削減により、承認者・経理担当者の負担を軽減します。
機能2:AI-OCR機能
光学文字認識にAI技術を融合した「AI-OCR」の技術を用いることで、領収書を自動で読み取ってデータ化する機能です。専用アプリから領収書を撮影するだけで、日付・金額・取引先などの情報を読み取り、そのまま経費申請を行えます。申請者の手入力によるミスや不正の削減につながります。
機能3:自動仕訳機能
申請内容から勘定科目や税区分を自動で割り振る機能です。自動で仕訳できるので、貸方・借方の内容チェックのみで業務が完了します。手間のかかる仕訳作業が自動化されるため、経理担当者がラクになります。
さらに、「楽楽精算」は電子帳簿保存法やインボイス制度に対応しているため、速やかに法対応を実現できる点も大きなメリットです。その他の機能や魅力については、無料の資料で詳しくご案内しています。以下のフォームからお気軽にお問い合わせください。
「楽楽精算」の
資料をメールでもらう

電子帳簿保存法対応!経費精算システム「楽楽精算」の製品概要や導入メリット、機能などが詳しくわかる資料をメールでお送りします。
この記事を読んだ方におすすめ!
オススメの人気記事
記事執筆者紹介

「楽楽精算」コラム編集部です。
経理担当者様の日々の業務にプラスとなるお役立ち情報
「楽楽精算」最新情報をお届けしていきます!
使い勝手が気になる方へ。