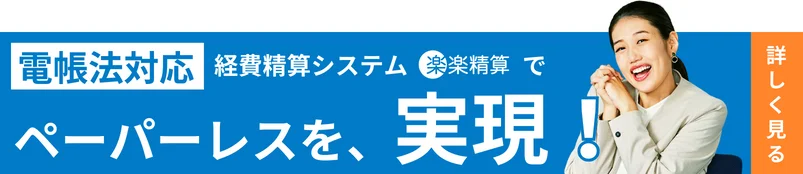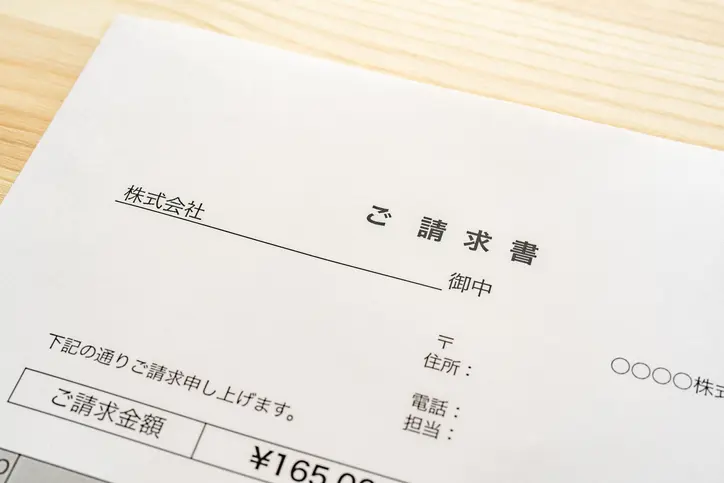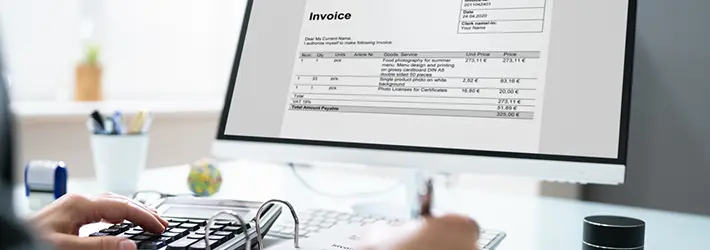食事代の経費分類で迷わない!会議費や交際費の正しい仕訳と税務対策

経理担当者の皆様は、「この食事代、何費になるの?」と頭を悩ませた経験が一度はあるのではないでしょうか。社内会議、出張、取引先との接待など、さまざまな場面で発生する食事代は、その目的や参加者によって適用される勘定科目や税務上の扱いが大きく異なり、分類の判断に迷いが生じやすい費用です。分類のバラつきは、社内の認識齟齬を生むだけでなく、結果として税務調査で思わぬ指摘を受けるリスクを高めるという懸念につながっています。
この記事では、食事代を実態と目的に応じていかに正しく分類するか、その明確な基準を解説します。また、各勘定科目の税務上の取り扱い、特に損金算入の可否や適用される特例について深く掘り下げ、節税と税務リスク回避のための知識を提供します。
この記事の目次
食事代が経費になるかどうかの判断基準とは?
食事代を経費として計上する上で、最も重要な原則が「事業関連性」です。これは、その支出が事業活動のために必要不可欠であると認められるかどうかを判断する基準となります。事業に関連しない個人的な食事代は、いかなる場合も経費として認められることはありません。
たとえば、仕事の合間に個人的に摂るランチや、業務終了後に友人や家族と楽しむ食事は、仮に仕事の疲れを癒す目的であったとしても、事業活動に直接関連するとはみなされません。これらは個人の生活費に該当するためです。
一方で、取引先との打ち合わせが長引いた際に用意した弁当代や取引先とのミーティングを兼ねた食事代、新たな取引の獲得や良好な関係維持を目的とした接待飲食費用、従業員の慰労を目的とした食事会などは、事業活動に直接関連すると判断され、経費として認められる可能性があります。たとえば、通信環境が整った喫茶店で、次の取材までの空き時間に仕事をする際に発生したコーヒー代などは、事業関連性が認められれば雑費として処理することが可能です。
この「事業関連性」の判断基準が曖昧であると、経理担当者がどの勘定科目で処理すべきか迷い、結果として分類に一貫性がなくなってしまいます。また、申請者と経理担当者の間で「これは事業に必要な食事だ」という認識に齟齬が生じることも少なくありません。このような状況は、税務調査の際に指摘を受けるリスクを高めるだけでなく、社内の経費精算プロセスにおける混乱や非効率の原因となります。そのため、各食事代の具体的な目的と内容を明確にし、その事業関連性を客観的に説明できる状態にしておくことが極めて重要です。
食事代の経費処理で用いる勘定科目と分類のポイント
食事代の経費処理において、その目的と対象者によって適用される勘定科目は大きく異なります。ここでは、主要な勘定科目とその分類のポイントを概観します。
食事代の勘定科目別比較表
以下の表は、食事代に関する主要な勘定科目の目的、対象者、税務上の扱い、そして主な注意点を比較したものです。
| 勘定科目 | 主な目的 | 対象者 | 税務上の扱い(損金算入の可否、特例) | 1人あたり基準の有無 | 主な注意点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会議費 | 会議・打ち合わせ | 社内外問わず | 原則全額損金算入。1人あたり10,000円以下(R6.4.1以降)の飲食費は交際費等から除外され、全額損金算入可能。 | あり(10,000円) | 飲食は「昼食程度」など常識的な範囲。会議の目的が明確であること。 |
| 交際費 | 接待・供応・親睦 | 取引先など社外関係者 | 原則損金不算入。中小企業は「年間800万円まで」または「接待飲食費の50%」の有利な方を選択し損金算入可能。1人あたり10,000円以下の飲食費は交際費等から除外。 | あり(10,000円) | 目的は「接待・親睦」が主。10,000円基準は税務上の特例であり、本質的な目的は変わらない。 |
| 福利厚生費 | 従業員の慰労・福利 | 全従業員(または部署単位) | 全額損金算入。 | なし(社会通念上の妥当性) | 「賃金ではない」「全従業員対象」「社会通念上妥当」の3条件を満たすこと。特定の従業員のみは給与とみなされる可能性。 |
| 旅費交通費 | 出張に伴う費用 | 従業員 | 全額損金算入。 | なし | ホテル代に含まれる朝食など。出張先での個人的な食事は対象外。 |
| 雑費 | その他事業関連費 | 従業員(個人事業主) | 全額損金算入。 | なし | 他の勘定科目に該当しない少額な事業関連費用。例:喫茶店での作業中のコーヒー代。 |
科目別の詳細について、以下で詳しく解説します。
会議費:社内外の会議・打ち合わせでの飲食
会議費は、社内外で行われる会議や打ち合わせに付随して発生する費用を指します。これには、会議室の利用料や資料作成費だけでなく、会議中に提供される弁当、飲み物、お菓子などの飲食費も含まれます。会議の参加者が取引先であっても従業員であっても適用可能です。飲食は「昼食を超えない程度の飲食物」であり、社会通念上妥当な範囲であることが条件となります。
会議費は、後述する交際費と混同されやすい勘定科目です。両者を区別する上で、目的に違いがある点に注意しましょう。
- 会議費:主目的が「商談や会議」であり、飲食はそれに付随する「昼食程度」の費用
- 交際費:主目的が「接待、供応、親睦」であり、事業関係者との良好な関係構築や維持に重点が置かれている費用
交際費:取引先との接待・供応
交際費は、得意先や仕入先など、事業に関係のある外部の者に対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出される費用です。法人の場合、原則として損金に算入されない費用ですが、一定の特例が設けられています。
具体的には、資本金1億円以下の法人(中小法人)では、以下のいずれか有利な方を選択して損金算入が可能です。
- 年間800万円までの交際費等を全額損金算入する。
- 交際費等のうち、接待飲食費(社外の者との飲食費)の50%相当額を損金算入する。
この特例措置は、令和6年度税制改正により3年間延長され、令和9年3月31日までに開始する事業年度まで適用が継続されます。
なお、個人事業主の場合は、法人とは異なり、交際費に上限額は設定されていません。
参考:中小企業庁「交際費課税の特例」
福利厚生費:従業員向けの飲食
福利厚生費は、従業員の慰労や健康増進など、従業員の福利厚生を目的として支出される費用です。たとえば、忘年会や新年会、社員旅行に伴う飲食費などがこれに該当します。
ただし、福利厚生費として認められるためには、以下の3つの条件を満たす必要があります。
- 賃金ではないこと
- 全従業員を対象範囲としていること
- 金額が社会通念上、妥当であること
「全従業員対象」という条件は、単に形式的な参加資格だけでなく、実質的に多くの従業員が参加できるような配慮が求められることを示唆しています。たとえば、特定の部署だけが頻繁に高額な食事会を開いている場合、たとえ「全従業員対象」と謳っていても、税務上は給与とみなされるリスクがあります。
この「社会通念上の妥当性」と「実質的な公平性」のバランスが、経理担当者にとって判断の難しいポイントとなります。
旅費交通費:出張中の飲食(ホテル代込みの場合など)
旅費交通費は、出張に伴う交通費や宿泊費が主な内訳ですが、宿泊費に朝食が含まれている場合、その朝食代は宿泊費の一部とみなされ、旅費交通費として計上されます。しかし、出張先での個人的な食事代は原則として経費にはなりません。出張中に取引先との会議や接待が行われた場合の食事代は、その目的によって会議費や交際費として別途計上されることになります。
雑費:その他(喫茶店での作業など)
雑費は、事業に関連する費用でありながら、他のどの勘定科目にも当てはまらない少額な支出に用いられます。たとえば、通信環境が整っている喫茶店で、次の取材までの空き時間に仕事をする際に発生したコーヒー代などは、事業関連性が認められれば雑費として処理することが可能です。ただし、昼食が主目的であったり、飲酒を伴う場合は、個人的な費用とみなされる可能性が高まります。
食事代の経費処理における勘定科目ごとの仕訳例
ここからは、主要な勘定科目について、具体的な仕訳例を紹介します。
会議費
社内会議の弁当・飲み物
社内会議中に提供される弁当や飲み物、茶菓子などの費用は、会議費として全額計上できます。
仕訳例:会議用弁当代5,000円を現金で支払った場合
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 会議費 | 5,000円 | 現金 | 5,000円 |
取引先とのランチミーティング
取引先との商談や会議が主目的で、その中でランチを摂る場合、その食事代は会議費として計上可能です。
仕訳例:取引先とのランチミーティング代15,000円(3名参加、1人あたり5,000円)を現金で支払った場合
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 会議費 | 15,000円 | 現金 | 15,000円 |
交際費
取引先を招待した会食や懇親会
取引先や仕入先を招いて開催する会食や懇親会の費用は、その目的が接待や親睦であれば交際費に該当します。飲食代だけでなく、会場代、参加者へのプレゼント代、帰りのタクシー代なども含まれることがあります。
仕訳例: 取引先との接待飲食費50,000円を現金で支払った場合
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 交際費 | 50,000円 | 現金 | 50,000円 |
取引先とのゴルフや旅行
事業の発展や関係維持を目的として取引先をゴルフや旅行に招待した場合の費用も、交際費として処理されます。
仕訳例:取引先とのゴルフ接待費用30,000円を現金で支払った場合
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 交際費 | 30,000円 | 現金 | 30,000円 |
福利厚生費
忘年会、新年会、親睦会等
役員や社員全員に参加資格があり、相当数の人数が参加していること、そして社会通念上妥当な金額であることが条件です。高額すぎる場合や開催頻度が高い場合は、交際費または給与とみなされる可能性があります。
仕訳例:全従業員参加の忘年会費用200,000円をクレジットカードで支払った場合
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 福利厚生費 | 200,000円 | 未払金 | 200,000円 |
残業時の食事代
勤務時間外の業務に対するもので、内容が通常の範囲内であれば福利厚生費として計上できます。ただし、お酒が含まれる場合は福利厚生費として認められない可能性が高まります。また、勤務時間内の食事提供の場合、従業員が半分以上を負担し、会社負担が月額3,500円以下であれば福利厚生費となります。
仕訳例:残業時の食事代3,000円を現金で支払った場合
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 福利厚生費 | 3,000円 | 現金 | 3,000円 |
なお、個人事業主の場合、一人で事業を行っている場合や家族と一緒に仕事をしている場合は、経費を福利厚生費として計上することはできません。家族以外の従業員を雇用している場合に限り、その従業員のために支出した費用を福利厚生費として計上することが認められます。
これは、法人の経理担当者が個人事業主の経費処理をサポートする際や、自身が個人事業主である場合に誤解しやすい点であり、法人と個人事業主で税務上の扱いが異なる典型例として注意が必要です。
食事代を経費として処理する際の注意点・ポイント
食事代は、その性質上「食べてしまったら後に残らない」費用であり、税務調査の際に使途不明金と疑われやすい項目の一つです。そのため、領収書やレシートといった証拠の保管だけでなく、その支出の「事業関連性」を明確に証明できる記録を徹底することが重要なポイントになります。
領収書・レシートを保管する
食事代を経費として計上する際には、必ず領収書やレシートを受け取り、保管することが基本です。領収書には、飲食等のあった年月日、費用額、飲食店名、所在地などが記載されていることを確認してください。
「誰と・何のために」をメモする
領収書やレシートだけでは、「いつ、どこで、いくら使ったか」という支出の事実しか証明できません。税務調査では、その支出が「なぜ事業に必要だったのか」「誰と、どのような目的で飲食したのか」という事業関連性や目的が問われます。
このギャップを埋めるために、領収書やレシートの裏面、または別途作成する経費精算書やメモに、以下の情報を記録しましょう。
- 参加者の氏名、会社名、役職、そして自社との関係性(例:取引先、仕入先、従業員など)
- 参加者の人数
- 飲食した背景・目的(会議であれば「〇〇プロジェクトに関する定例会議」、接待であれば「新規取引先〇〇社との懇親会」など、具体的な目的や内容を記載)
近年増加しているリモートワーク環境でのオンライン会議に伴う食事代など、プライベートとの区別がつきにくい費用については、さらに具体的な証拠を残すことが求められます。会議の議事録、参加者リスト、会議のスクリーンショットなどを保管し、その食事が事業のために購入されたことを明確に示せるようにしておくことをおすすめします。
「楽楽精算」で食事代の経費処理を効率化
食事代の経費処理は、その複雑な分類、税務上の特例、そして厳格な証憑管理が求められるため、経理担当者にとって大きな負担となりがちです。このような課題を解決し、経費処理を劇的に効率化・正確化するための強力なツールが、経費精算システム「楽楽精算」です。
特徴1:自動仕訳機能
「楽楽精算」の最も大きなメリットの一つが、自動仕訳機能です。申請者が入力した内容に応じて、勘定科目や税区分が自動で振り分けられるため、経理担当者による手動での仕訳作業が不要になります。これにより、手入力による転記ミスや勘定科目選択ミスといった人為的なエラーが根本から排除され、経理業務の処理スピードが飛躍的に向上します。
この自動仕訳機能は、単なる手間削減に留まりません。事前に設定されたルールに基づいて処理が行われるため、属人化しがちな勘定科目判断をシステムが代行し、経理業務全体の品質が標準化されます。これにより、誰が担当しても同じ正確性で処理できるようになり、経理業務の信頼性が向上します。
1人あたり単価自動算出と規定違反チェック機能
食事代の経費処理で特に判断が難しいのが、交際費における1人あたり10,000円基準の適用です。楽楽精算では、交際費の申請画面で参加人数を入力すると、1人あたりの単価が自動で算出されます。さらに、この機能は規定違反チェック機能と組み合わせることが可能です。これにより、10,000円基準などの社内規定や税法上の判断をシステムが自動でチェックし、科目選択のミスや規定違反を未然に防ぐことができます。
この機能は、経理担当者が抱える「税務調査での指摘が心配」という不安を大きく軽減する強力なツールとなるでしょう。複雑な税法上のルールを手動で確認する手間が省け、申請段階で自動的にコンプライアンスが担保されるため、税務リスクの事前防止に直結します。
まとめ
食事代の経費処理は、一見すると単純なように見えても、その目的、対象者、金額によって適用される勘定科目や税務上の扱いが複雑に絡み合っています。本記事で解説したように、食事代の経費処理を正しく行うためには、その「目的」と「誰と」という2つの軸で勘定科目を判断することが極めて重要です。
特に「会議費」「交際費」「福利厚生費」の定義と、それぞれの税務上の特例を正確に理解し、適切に活用することで、損金算入できる費用を最大化し、企業の税負担を軽減することが可能になります。
これらの複雑な判断や記録の手間を劇的に効率化し、人為的なミスを削減する強力な味方が、経費精算システム「楽楽精算」です。具体的な導入メリットについて詳しくは無料の資料でご紹介しているため、以下のフォームからぜひお問い合わせください。
「楽楽精算」の
資料をメールでもらう

電子帳簿保存法対応!経費精算システム「楽楽精算」の製品概要や導入メリット、機能などが詳しくわかる資料をメールでお送りします。
この記事を読んだ方におすすめ!
オススメの人気記事
記事執筆者紹介

「楽楽精算」コラム編集部です。
経理担当者様の日々の業務にプラスとなるお役立ち情報
「楽楽精算」最新情報をお届けしていきます!
使い勝手が気になる方へ。