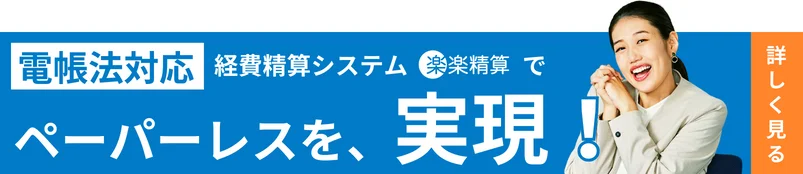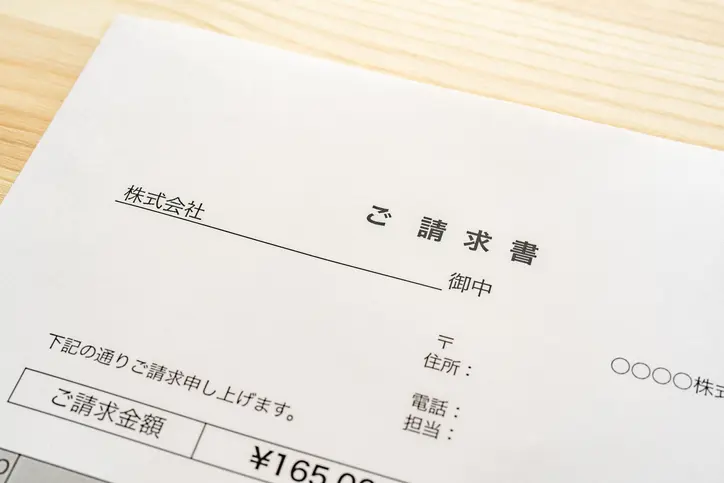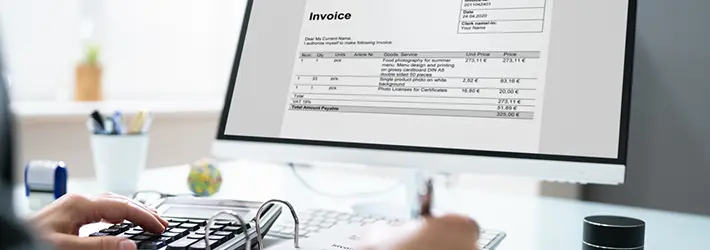スマホ関連費用は経費で落とせる?勘定科目や按分の考え方を解説

テレワークやチャット・電話での業務連絡が当たり前になった今、多くの企業では社員が個人のスマートフォンを業務に使っている状況です。しかし、「会社貸与と個人スマホの線引きが曖昧」「通信費や端末購入費の経費処理ルールが整備されていない」といった課題を感じている経理担当者もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、スマホ関連の費用について「どこまで経費で落とせるか」「どの勘定科目が適切か」「どう按分・申請・管理すればよいか」をわかりやすく解説します。
この記事の目次
業務で使うスマホ費用はどこまで経費になる?
まず初めに、業務で使うスマホ費用が経費になる範囲について解説します。
経費にできるスマホ関連費用の種類
業務に直接関係する費用であれば、基本的に経費として認められます。具体的な費用の例は、以下のとおりです。
- スマホ本体の購入費
- 月額通信費
- 業務用アプリの利用料
スマホ本体の購入費は、業務専用として購入した場合や、私用と業務との利用割合が明確な場合に経費計上が可能です。また、SlackやZoom、有料のセキュリティソフトなど、業務に必要なアプリの月額利用料も経費になります。
経費にできない・なりづらい費用
一方で、経費として認められない、または認められにくいケースもあります。以下のようなケースが該当します。
- 私的利用がメイン
- 家族で共用のスマホを利用している
- 経費と認められる根拠(合理性・業務関連性)が欠如している
たとえば、業務で使うのはごく一部で、私的な利用がほとんどの場合は経費計上が困難です。また、税務調査で「なぜこの費用が業務に必要なのか?」と問われたときに、明確に説明できない費用は経費として認められません。経費計上には合理的な根拠と業務関連性が必要です。
会社貸与と個人スマホの業務利用、それぞれの経費処理手順
スマホの経費処理は、会社が貸与しているか、個人が所有するスマホを業務利用(BYOD) しているかで大きく異なります。それぞれのケースにおける経費処理の手順について、以下で詳しく解説します。
会社貸与スマホの場合
会社がスマホを用意して貸与する場合は、基本的に費用の全額を会社側で処理できます。
購入費
取得価額が10万円未満であれば、消耗品費として一括計上できます。10万円以上であれば工具器具備品などの固定資産として減価償却を行います。
通信費・利用料
月々の通信費は通信費として処理します。業務に必要なアプリの利用料は、支払手数料や通信費として処理するのが一般的です。
この証憑(領収書や請求書)は会社で一括管理し、私的利用をどこまで認めるか、事前に社内ルールを定めておくことが重要です。
個人スマホの業務利用(BYOD)の場合
近年では、コスト削減の観点から、会社からスマホを貸与せず、BYOD(Bring Your Own Device)、つまり従業員が個人で所有する端末を業務に利用するという手法を取る会社もあります。スマホ本体代は原則経費計上は難しいですが、業務利用割合によっては一定額を補助することは可能です。通信費については、会社と個人での按分処理が必要です。
按分処理の方法
全体の費用から、業務に利用した割合(按分率)を算出し、その分のみを経費として計上します。
経費計上額 = 費用総額 × 業務利用割合
たとえば、月額5,000円の通信費のうち業務利用が50%なら、2,500円を経費計上します。業務利用の割合を算出するためには、通話履歴、使用データ量、業務内容の記録など、合理的な根拠が必要です。
証憑
個人名義の領収書や請求書でも、業務利用の事実が証明できれば経費として認められます。申請時に原本やコピーを提出してもらいましょう。
上述したスマホ関連の費用について、勘定科目と処理時の注意点を表にまとめました。
仕訳の際に参考にしてみてください。
| 費用内容 | 経費にできるか | 主な勘定科目 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| スマホ本体 | ○ | 消耗品費・工具器具備品 | 社用携帯として購入する場合、経費処理が可能。 金額によって資産計上が必要 |
| 通信費 | ○ | 通信費 | BYODの場合、私用分との区別が必要 |
| アプリ利用料 | ○ | 支払手数料・ソフトウェア | 業務用であることが明確な場合のみ計上可能 |
個人スマホ利用時の按分ルールと社内整備のポイント
個人スマホを業務に利用する際は、認識の齟齬やトラブルが起きないよう、事前にルールを定めておくことが重要です。ここからは、ルールを設定する時の観点や、整備するべき事項について解説します。
按分方法の考え方
按分率は、業務での利用実態に基づいて設定する必要があります。例えば、「通話時間の6割が業務関連」であれば6:4、「データ利用量の7割がテレワーク」であれば7:3といった割合を設定します。
重要なのは、その割合が合理的に説明できることです。口頭での申告だけでなく、稟議書や使用目的の記録、利用実績のスクリーンショットなどを提出してもらうと良いでしょう。
社内ルールとして整備すべき事項
トラブル防止と経費処理の効率化のため、以下のルールを明確に定めましょう。
- 申請フローと必要書類:「業務利用申請書」や「按分理由書」など、何を用意すれば良いか明確にします。
- 証憑保存ルール:領収書の原本や、明細書のスキャンデータなど、証憑の保存方法を定めます。
- 按分率の決定方法:誰が、どのような基準で按分率を判断するのかを明確にすることで、属人化を防ぎます。
スマホ関連費用の経費処理は経費精算システムで効率化
手作業やExcelで経費精算に対応している企業では、以下のような課題を抱えがちです。
- 手作業での確認・按分計算が面倒
- 証憑の不備や申請ミスが発生しやすい
- 仕訳の判断基準が特定の担当者に依存し、属人化している
このような課題を解決するのにおすすめなのが、クラウド型経費精算システム「楽楽精算」です。特に便利な機能についてご紹介します。
自動仕訳機能
事前に社内ルールに合わせて設定しておくことで、申請内容に応じて勘定科目や税区分の割り振りが行われる機能です。仕訳の属人化を防ぐとともに、経費申請の処理スピードを加速させ、業務効率化に貢献します。
電子帳簿保存法対応を効率化する機能
領収書や請求書は「楽楽精算」にアップロードするだけで、取引先や受領日を自動でデータ化。そのまま申請に利用できるので、手入力の手間・ミスが削減されます。紙や電子など、様々な形式の書類を一元管理できるため、申請漏れや証憑の不備を削減できます。
クレジットカード・プリペイドカード連携機能
法人クレジットカードの利用明細データをそのままシステムに取り込み、経費申請に活用できます。スマホの通信費やアプリ利用料を法人クレジットカードで支払う場合、支払いデータに基づいて経費申請を行えるため、申請者の入力にかかる時間・手入力で発生するミスの双方を削減することが可能です。
まとめ
スマホの購入費や通信費、アプリ利用料は、経費として処理できる場合があります。会社の費用負担と個人のプライベート利用が混在しがちなスマホ費用は、「事業との関連性」を証明できるかが経費計上の鍵となります。
この記事で解説したように、会社貸与か個人スマホ(BYOD)かで処理方法や必要なルールが大きく異なります。自社の状況に合わせ、経費計上の可否や適切な勘定科目、按分ルールを明確に定めることが第一歩です。
そして、そのルールを社員全員に周知・徹底し、手作業でのチェックやミスをなくすために、楽楽精算のようなクラウド経費精算システムを導入することで、経理業務の効率化と税務調査対策を同時に進めることができます。
煩雑になりがちなスマホ経費のルールを見直して、スマートな経理体制を構築していきましょう。
「楽楽精算」の
資料をメールでもらう

電子帳簿保存法対応!経費精算システム「楽楽精算」の製品概要や導入メリット、機能などが詳しくわかる資料をメールでお送りします。
この記事を読んだ方におすすめ!
オススメの人気記事
記事執筆者紹介

「楽楽精算」コラム編集部です。
経理担当者様の日々の業務にプラスとなるお役立ち情報
「楽楽精算」最新情報をお届けしていきます!
使い勝手が気になる方へ。