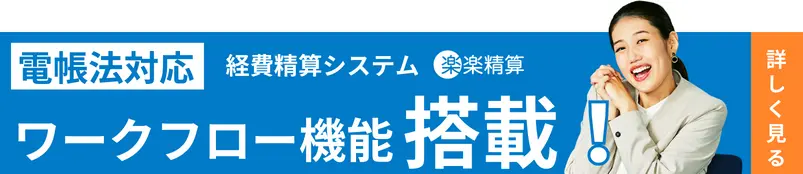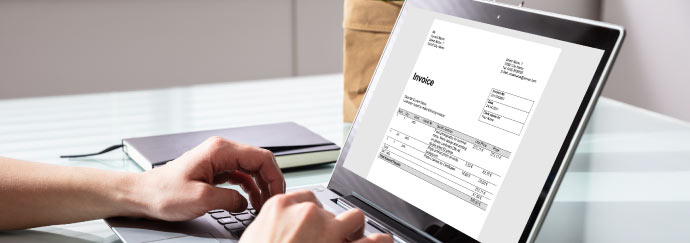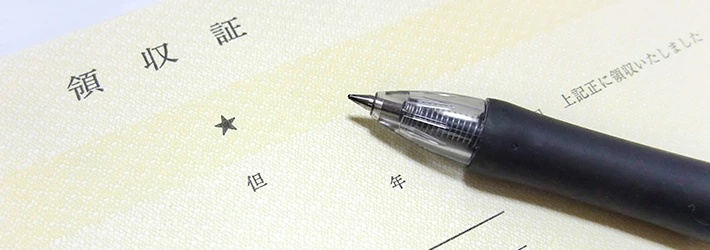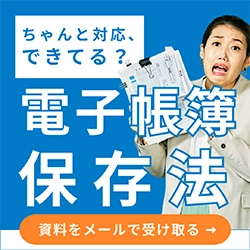領収書を電子化して保管する際のルールとは?守るべき要件や注意点

受領した紙の領収書の保管に多くの手間がかかり、電子化の必要性を感じていませんか?昨今は、業務効率化のために紙ベースの経理業務を見直して、電子化を推進する企業が多くなっています。このように受領した領収書を電子化する場合は、法律のルールを守って適切に運用することが大切です。
そこで本記事では、領収書を受領する側の企業が押さえておきたい、領収書を電子化して保管する際のルールについて解説します。お伝えする基礎知識を踏まえて、経理業務の電子化へ向けて取り組み始めましょう。
この記事の目次
領収書は電子化して保管しても問題ない?
結論からお伝えすると、領収書は「電子帳簿保存法(=国税関係帳簿書類のデータ保存に関して定めた法律)」で定められている要件に則って保存すれば、問題なく電子化することが可能です。具体的な保存要件は、「電子取引データの保存」「スキャナ保存」「電子帳簿等保存」の3つに分けて定義されています。
まずは、3種類の保存方法とは何かを整理していきましょう。
電子取引データの保存
「電子取引データの保存」では、領収書・請求書・見積書・契約書などの書類を、電子的な方法でやり取りし、受領した場合の保存要件が定められています。例えば、メールやクラウドのように、インターネットを介して領収書を受領した場合は、「電子取引データの保存」に該当します。
【「電子取引データの保存」に該当する具体例】
- メールで送付された領収書
- Webサイトやオンラインプラットフォームからダウンロードした領収書
- 銀行のオンライン明細やクレジットカードの利用明細データ
参考:国税庁「電子取引関係」
スキャナ保存
「スキャナ保存」では、紙で発行された領収書・請求書・見積書・契約書などの書類を、スキャナやスマートフォンのカメラなどでデータ化し、保存する際の要件が定められています。画像データの解像度・出力装置の備え付け・検索性の確保など複数の要件がありますが、きちんと満たせば紙の原本を破棄し、電子データで保存できるようになります。
【「スキャナ保存」に該当する具体例】
- 紙で受領した後、複合機のスキャナで読み取ってデータ化した領収書
- 紙で受領した後、スマートフォンのカメラで撮影してデータ化した領収書
参考:国税庁「スキャナ保存関係」
電子帳簿等保存
「電子帳簿等保存」では、帳票発行システムや会計ソフトなどで作成した領収書・請求書・見積書・契約書などの書類を、印刷せずにデータのまま保存する際の要件が定められています。その際は、改ざん防止の措置・出力装置の備え付け・検索性の確保など、複数の要件を満たす必要があります。
【「電子帳簿等保存」に該当する具体例】
- 帳票発行システムや会計ソフトで作成した領収書データ
- エクセルなどの表計算ソフトで作成した領収書データ
参考:国税庁「電子帳簿・電子書類関係」
電子帳簿保存法の詳細は以下の関連記事でも解説しています。さらに詳しく知りたい方は、本記事と併せてご覧ください。
領収書を電子化して保管する際に守るべきルール
ここまでご紹介した電子帳簿保存法の「電子取引データの保存」「スキャナ保存」「電子帳簿等保存」には、それぞれ詳細な要件が定められていますが、要点をわかりやすくまとめると、大まかに以下の3つのルールが挙げられます。電子帳簿保存法やその他の法律の概要として押さえておきましょう。
ルール1: 真実性の確保
電子的に保存される帳簿や書類の内容が、正確かつ改ざんされていないことを保証するために設けられている要件です。具体的には、以下のような方法で真実性を担保する必要があります。
・タイムスタンプの付与
タイムスタンプは、特定の時刻以降に改ざんされていない事実を証明する技術です。「タイムスタンプが付与されたデータを受領する方法」と「受領したデータにタイムスタンプを付与する方法」があります。
・管理機能のあるシステムの利用
訂正・削除の履歴が残る専用システムで授受または保存する方法です。電子帳簿保存法に対応した経費精算システムを導入しましょう。
ルール2:可視性の確保
電子帳簿保存法において「可視性」とは、保存した電子データを必要な場合に速やかに表示・出力できる状態を指します。可視性の確保のために、以下のような措置を講じることが必要です。
・見読可能性の確保
データを画面に表示するディスプレイや、印刷するプリンターを備え付けます。税務調査官が求めたときにすぐにディスプレイで表示できるように準備しておきましょう。
・検索性の確保
保存した領収書データを、速やかに検索できる仕組みを整備します。基本的には「日付」「取引金額」「取引先名」の3つの要素で検索できる状態にしましょう。
・操作説明書などの備え付け
システムの操作説明書や仕様書などの書類を備え付けます。保存する際に、誰でも適切に操作できる状態にしておきましょう。
参考:国税庁「Ⅱ 適用要件【基本的事項】」
ルール3:保管期間の遵守
領収書を電子化した際は、紙の領収書と同様に、法律で保管期間が定められています。「法人税法」においては、法人の場合で原則7年間の保存義務があります。以下の通り保存期間が定められていることを押さえておきましょう。
| 事業種の種類 | 保存期間 |
|---|---|
| 法人 | 原則7年間 |
| 個人事業主(青色申告) | 原則7年間 |
| 個人事業主(白色申告) | 原則5年間 |
なお、インボイス制度に対応した領収書の場合は、法人・個人事業主ともに原則7年間の保存が必要です。
参考:国税庁「No.5930 帳簿書類等の保存期間」
領収書を電子化するルールと合わせて押さえておくべきポイント
領収書は上記で述べた大きく3つのルールに則って保管する必要がありますが、それに加えて気をつけてほしい細かなポイントがあります。電子化する際は、下記のポイントを押さえて適切な方法で保管するよう注意しておきましょう。
ポイント1:電子取引で受領した領収書を紙で保存することはできない
電子帳簿保存法においては、電子取引で受領した領収書のデータを、紙に印刷して保存することは認められていません。2024年1月から電子取引の電子データ保存が完全義務化されているためご注意ください。なお、紙で受領した領収書に関しては、紙と電子データのいずれの形式で保存しても問題ないとされています。
出典:国税庁「電子取引データの保存方法をご確認ください」
ポイント2:改ざんができない形式で保管する
領収書を電子化する際は、改ざんされにくいデータ形式で保管するのが望ましいでしょう。一般的には、セキュリティ対策を講じやすい「PDF形式」が推奨されています。PDFファイルにはセキュリティ機能が搭載されているため、パスワードを設定したり、暗号化して保護したりすることが可能です。
紙で管理している領収書を電子化するメリット
ここまで電子化のルールやポイントを確認してきました。現状、紙の領収書で運用している場合は、電子化にハードルを感じてしまったかもしれません。しかし、実際には以下のようなメリットがあります。
領収書の保管にかかるコストを削減できる
領収書を電子化すると、紙の原本を保管する必要がなくなります。電子データ化によって、紙媒体の保管に関わるコスト削減を実現できるのがメリットです。例えば、「領収書を保管する倉庫の維持コスト」「領収書をしまうファイルやキャビネットの経費」などを削減できます。
業務を効率化できる
領収書の電子化により、ファイリングや書類の出し入れの手作業をなくし、業務効率化を実現できます。具体的には「領収書をファイリングする作業」「領収書の入ったファイルを保管場所へ搬入する作業」「必要な領収書をキャビネットから探して取り出す作業」などの手間と労力が不要となります。
領収書の紛失・破損などを防ぐことができる
紙の領収書には、物理的に紛失したり、破損したりするリスクが存在します。それに対して、電子データはバックアップが可能で、紙と比べて物理的に生じるリスクを避けやすくなります。紙の文書のように、誤った場所に保管して失くしてしまったり、災害によって消失・損壊してしまったりする心配がありません。
このように、領収書の電子化は長期的な視点では電子化するメリットが大きいといえるでしょう。
法律のルールに則って領収書を電子化しましょう!
ここまで、領収書を電子化して保管する際のルールや、注意点、電子化のメリットまでお伝えしました。ルールが多く、電子化にハードルを感じてしまった担当者の方もいるかもしれません。とは言え、昨今のペーパーレス化や法改正の影響によって電子化を余儀なくされている企業も少なくありません。
独力で法要件に則った電子化の運用を整備するのは負担が大きいため、困ったときは電子帳簿保存法の要件を満たしたシステムを導入するようおすすめします。なかでもクラウド型経費精算システム「楽楽精算」には、初めてのシステム導入でも安心できるポイントがたくさんあります。
「楽楽精算」の魅力1:法律のルールへの対応が簡単!
電子帳簿保存法やインボイス制度など、最新の法律のルールに対応したシステムです。導入するだけで法律のルールを守って運用でき、将来的な法改正にも対応できるようになります。
「楽楽精算」の魅力2:手厚いサポートで初めてでも安心
専任のサポート担当が導入準備から運用開始後まで手厚くサポートします。お客様の不安に寄り添うサポート体制が充実しているので、初めてのシステム導入でも安心してご利用いただけます。
「楽楽精算」の魅力3:経理業務のペーパーレス化を実現
インターネット環境があれば、システム上でいつでもどこでも申請・承認が可能です。経理業務のペーパーレス化を実現し、テレワーク(リモートワーク)にも対応できます。
「楽楽精算」の詳しい資料は、以下のフォームから無料で配布しております。どうぞお気軽にお問い合わせください。
「楽楽精算」の
資料をメールでもらう

電子帳簿保存法対応!経費精算システム「楽楽精算」の製品概要や導入メリット、機能などが詳しくわかる資料をメールでお送りします。
この記事を読んだ方におすすめ!
オススメの人気記事
記事執筆者紹介

「楽楽精算」コラム編集部です。
経理担当者様の日々の業務にプラスとなるお役立ち情報
「楽楽精算」最新情報をお届けしていきます!
使い勝手が気になる方へ。