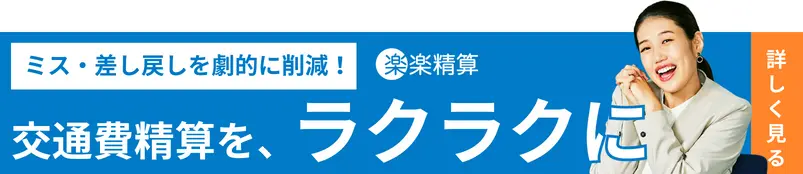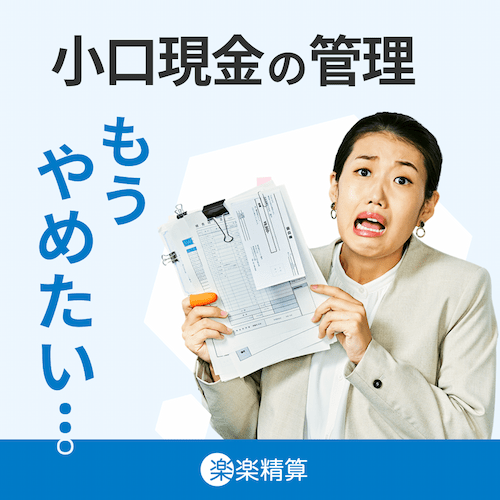退職時の交通費精算のポイントとは|返金の必要性などケース別に解説

従業員に通勤用の定期券代やガソリン代といった交通費を前払いで支給している企業の場合、その従業員が退職したとき、どのように精算するのでしょうか?
基本的に会社の就業規則(賃金規程)に記載された通りに退職者の経理処理を行うことになります。具体的にどのような手続きを行うかは、会社ごとのルールや個別の状況によって異なるので、一つひとつ確認してみましょう。
この記事では、従業員の退職時の交通費精算で押さえておきたいポイントを解説します。ケース別に返金の必要性や経理部門での手続きについてご紹介するため、経理担当者の方はぜひ参考にしてみてください。
この記事の目次
従業員退職時の交通費の扱い方とは?
多くの企業では、従業員の通勤にかかる交通費を「通勤交通費(または通勤手当)」として毎月支給しています。具体的には、電車やバスなどの公共交通機関の定期券代、マイカー通勤での通勤距離に応じたガソリン代などが該当します。
通勤にかかる交通費を支給している従業員が退職した場合、退職時は就業規則(賃金規程)に則って交通費を精算しましょう。
例えば、就業規則で1カ月に支払う交通費の金額が定められている場合は、月の途中で従業員が退職したケースでも交通費を全額支払うのが一般的です。その一方で、就業規則で実出勤日に合わせて交通費を算出すると定められている場合は、出勤日数分の交通費を支払いましょう。このように、経理担当者の方は自社のルールに従って精算を行ってください。
以降では、ケース別に退職時の交通費の処理方法を解説します。退職手続きにおけるトラブルを防ぐために、考え方を押さえておきましょう。
ケース1:通勤定期が1カ月以上残っている場合は返金が一般的?
ここでは、従業員に支給した通勤定期券の有効期間が1カ月分以上残っているケースについて解説します。例えば、数カ月分の定期券代をまとめて支給している企業でよく発生する事例です。
この場合、就業規則で交通費精算に関して「出勤日数分の交通費を支払う」といった定めがあれば、退職する従業員に交通費の返金を求めることができます。
一般的な公共交通機関では、通勤定期券の有効期間が1カ月分以上残っていれば、手数料がかかりますが払い戻しに対応していることが多いです。
対応の可否は公共交通機関によって異なるため、会社で就業規則を作成する際には注意が必要です。
ケース2:有給消化中の交通費精算はどうする?
ここでは、退職する従業員が有給消化する期間の交通費精算について解説します。
この場合、就業規則で有給休暇中に交通費を支給する定めがなければ、企業は法的に交通費を支払う義務はありません。ただし、「有給休暇中も交通費を支給する」と就業規則で定めている場合は、その分の交通費は全額支払う必要があります。
従業員の有給休暇残日数によっては、有給消化が数週間以上にわたり続くことがあるので、交通費の金額も大きくなるでしょう。
また、就業規則で定められているにもかかわらず交通費の返金を求めると違法となる可能性があるため、経理担当者は注意しておきましょう。
ケース3:交通費を会社からの預り金として事前に支払っている場合はどうする?
ここでは、事前に従業員へ預り金として交通費を支払っているケースについて解説します。そもそも預り金とは、従業員が会社から一時的に預かっているお金のことです。将来的に発生する経費の支払いに充てる目的で、あらかじめ会社が従業員へお金を前払いして預けておくことがあります。
このように会社が従業員に預り金として交通費を支払っているときは、従業員の退職時に業務で使用した金額以外の返金を求めることが可能です。預り金はもともと、業務で使用した金額以外は返金する決まりとなっています。そのため、退職日までの通勤で使用した金額を除き、余った分は返金してもらいましょう。
退職者の交通費は会社のルールに沿って正しく処理しましょう
ここまで、従業員の退職にともなう交通費精算について解説しました。退職者の交通費は、基本的に会社の就業規則に従って処理を行います。そのため、経理部門では自社の就業規則の内容を確認した上で、ルールに沿って退職者の交通費を正確に精算しましょう。
退職者の交通費精算では、前述したように煩雑なイレギュラー対応が発生することが少なくありません。経理部門では給与計算や経費精算といった日常の仕事と並行して退職者の対応を行うので、業務負担が大きくなりがちです。こうした職場の問題を解決するなら、経費精算システムの活用による全体的な業務効率化を検討するとよいでしょう。
数あるシステムの中でも「楽楽精算」には、経理担当者の仕事をラクにする機能がたくさん搭載されています。
「楽楽精算」の魅力1:「乗換案内」機能が内蔵されている
システムに「乗換案内」の機能が内蔵されているので、瞬時に最適なルートで交通費を計算できます。経理担当者がルートを検索して運賃を計算したり、申請内容をチェックしたりする手間を省けます。
「楽楽精算」の魅力2:定期区間の登録が可能
あらかじめ従業員の定期区間を登録しておくことで、利用ルートから定期区間を自動で控除して交通費を計算できます。申請ミスが減って経理担当者の差し戻しの手間がなくなるだけでなく、交通費の過払いなど不正防止にもつながります。
「楽楽精算」の魅力3:規定違反チェックなどの機能も充実
社内規定に違反する申請内容を自動でブロックする機能により、確認作業の効率化を実現できます。差し戻しの発生を未然に防げるので、申請者との無駄なやり取りがなくなり、交通費のチェックがラクになります。
「楽楽精算」の機能や導入メリットについて、詳しくは無料の資料でご案内しています。お気軽にお問い合わせください。
「楽楽精算」の
資料をメールでもらう

電子帳簿保存法対応!経費精算システム「楽楽精算」の製品概要や導入メリット、機能などが詳しくわかる資料をメールでお送りします。
この記事を読んだ方におすすめ!
オススメの人気記事
記事執筆者紹介

「楽楽精算」コラム編集部です。
経理担当者様の日々の業務にプラスとなるお役立ち情報
「楽楽精算」最新情報をお届けしていきます!
使い勝手が気になる方へ。